- トップページ
- 事業について
- JICAグローバル・アジェンダ
- 教育
- アフリカにおける理数科教育支援−アフリカ理数科教育域内連携ネットワーク−
- SMASE-WECSAについて
(1)概要
SMASE-WECSA(SMASE-WECSA:Strengthening of Mathematics and Science Educationin Western, Eastern, Central and Southern Africa)は、ケニアにおける現職教員研修を通じた理数科教育改善の経験をアフリカ諸国で共有し、アフリカ地域内の理数科教育の振興および域内の連携促進を目的として設立されたネットワークです。
各国の教育関係者(教育省中心)が参加主体となり、2001年にケニアで開催された第1回SMASE-WECSA域内会合を契機に発足しました。"SMASE-WECSAAssociation"は2003年にケニアにおいてNPO法人として登録された団体で、事務局はケニア教育省・アフリカ理数科・技術教育センター内に置かれています。JICAは、本団体のパートナーとして、ケニア教育省と協力して、ケニアを拠点に実施されるメンバー国向け研修(第三国研修)や、メンバー国に対する技術支援、経験共有ワークショップ等に対する支援を行っています。
(2)メンバー国
正式メンバー国(参加年)
| 参加年 | 新規参加国数 | 国・地域名 |
|---|---|---|
| 2003 | 11 | ガーナ、ケニア、レソト、マラウイ、モザンビーク、ルワンダ、スワジランド、タンザニア、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエ |
| 2004 | 4 | ボツワナ、ブルンジ、ニジェール、ナイジェリア |
| 2005 | 1 | セネガル |
| 2006 | 3 | カメルーン、エチオピア、シエラレオネ |
| 2007 | 3 | ブルキナファソ、ガンビア、ザンジバル(注1) |
| 2008 | 2 | アンゴラ、南スーダン(注2) |
| 2009 | 0 | |
| 2010 | 1 | マリ |
| 2011 | 2 | ベナン、ナミビア |
| 合計 | 27 |
- (注1)ザンジバル教育省は、タンザニア教育省とは別組織のため、別々に登録
- (注2)2011年7月 南スーダン共和国独立に伴い「南スーダン」に変更
SMASE-WECSAメンバー国数の推移
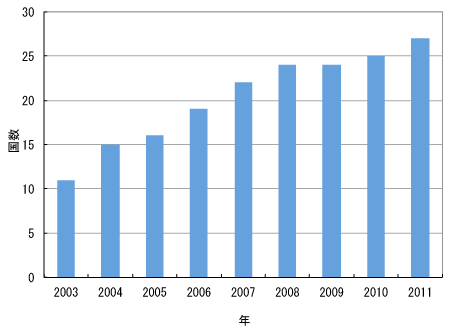
オブザーバー参加国(アルファベット順)
コンゴ共和国、コートジボワール、エジプト、マダガスカル、モーリシャス、セイシェル、南アフリカ、スーダン
(3)活動内容・実績
JICAは、SMASE-WECSA活動の発展のため、ケニアを拠点とするSMASE-WECSA加盟国に対する研修の実施、ケニアにおけるプロジェクト活動を通じて育成されたケニア人専門家のWECSAメンバー国への派遣、WECSAメンバー国間の経験共有のための会議・ワークショップ開催などを支援しています。これらの活動は、ケニア理数科教育強化計画プロジェクト(SMASEプロジェクト)活動の一部(域内連携活動)として実施されています。
概要および実績は以下の通りです。
第三国研修
WECSAメンバー国を対象とする第三国研修は、JICAおよびケニア教育省の共同事業として、ケニア「アフリカ理数科・技術教育センター(Center forMathematics, Science and Technology Education in Africa: CEMASTEA)」において実施されています。この研修は、ケニアSMASSEプロジェクトフェーズ1、フェーズ2の実施を通じて蓄積された理数科教育改善のノウハウを元に、CEMASTEAの研修講師(ナショナルトレーナー)陣によって計画、実施されています。SMASEプロジェクトに派遣されている日本人専門家も、研修教材作成や研修実施、評価に対する技術指導を行っています。
第三国研修の概要
| 対象国 | SMASE-WECSA正式メンバー国 |
|---|---|
| 研修テーマ | 「アフリカの理数科教育におけるASEI-PDSIアプローチの強化」 Activity, Student, Experiment, Improvisation and Plan, Do, See, Improve (ASEI & PDSI)Approach in Mathematics and Science Education in Africa |
| 研修回数 | 年3コース(英語圏向け2コース[初等/中等]、仏語圏向け1コース[初等]) |
| 研修期間 | 2週間〜4週間(コースにより異なる) |
| 対象者 |
|
| 研修目標 |
|
-
(注1)ASEI-PDSIアプローチとは?
ケニアSMASSE/SMASEプロジェクトが目指す教授法改善のアプローチを標語化したもの。ケニアSMASSEのカウンターパートと日本人専門家との議論の中から生み出されたもので、生徒の積極的な参加を通じて、生きた知識をともに育てるとともに、科学的・論理的思考の発達と科学的態度の育成を促す授業に変えていこうという授業改善の方向性とそのための方法論を表したものです。
ASEI/PDSIアプローチとは
- 目指す授業:ASEI授業
- Activity:活動に基づいて知識を得る授業へ
- Student:教師中心の授業から生徒中心の授業へ
- Experiment:講義中心から実験や実習を取り入れた授業へ
- Improvisation:身近な教材を使った簡易実験のある授業
- 授業改善のプロセス:PDSIアプローチ
- Plan:授業の計画作成、準備
- Do:実践
- See:評価
- Improve:フィードバック、改善
(詳細はJICA国際協力総合研修所(2007)『キャパシティ・ディベロップメントに関する事例分析 ケニア中等理数科教育強化計画プロジェクト』p.20を参照。)
2004年度から2011年度までの間に実施された第三国研修の実績は次の通りです。ケニアでは、以下の集団型研修のほか、WECSAメンバー国の個別の要望に応じて、個別研修も随時実施しています。
第三国研修の実績(2004〜2011)
| 回 | 研修時期 | 期間 | 参加国数 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2004年 1〜2月 | 5週間 | 7ヵ国 | 42名 |
| 第2回 | 2004年 11〜12月 | 5週間 | 15ヵ国 | 85名 |
| 第3回 | 2005年 11〜12月 | 5週間 | 14ヵ国 | 95名 |
| 第4回 | 2006年 10月 | 4週間 | 11ヵ国 | 81名 |
| 第5回 | 2006年 11〜12月 | 4週間 | 6ヵ国 | 83名 |
| 第6回 | 2007年 9〜10月 | 4週間 | 6ヵ国 | 76名 |
| 第7回 | 2007年 10〜11月 | 4週間 | 7ヵ国 | 67名 |
| 第8回 | 2008年 10月 | 4週間 | 12ヵ国 | 83名 |
| 第9回 | 2008年 11月 | 2週間 | 3ヵ国 | 31名 |
| 第10回 | 2008年 11月 | 3週間 | 7ヵ国 | 50名 |
| 第11回 | 2009年 9〜10月 | 4週間 | 10ヵ国 | 76名 |
| 第12回 | 2009年 10月 | 2週間 | 3ヵ国 | 31名 |
| 第13回 | 2009年 10〜11月 | 3週間 | 7ヵ国 | 52名 |
| 第14回 | 2010年 9〜10月 | 4週間 | 12ヵ国 | 82名 |
| 第15回 | 2010年 10〜11月 | 2週間 | 7ヵ国 | 30名 |
| 第16回 | 2010年 10〜11月 | 3週間 | 10ヵ国 | 50名 |
| 第17回 | 2011年 10〜11月 | 3週間 | 11ヵ国 | 62名 |
| 第18回 | 2012年 1月 | 2週間 | 6ヵ国 | 30名 |
| 第19回 | 2012年 1〜2月 | 4週間 | 8ヵ国 | 52名 |
| 計 | 30ヵ国 | 1,158名 | ||
集団型研修および個別研修の実績を合わせると、計30ヵ国から1,503名がケニアでの研修に参加しました。
メンバー国に対する技術支援
ケニアSMASEプロジェクトでは、WECSAメンバー国からの要望に応じて、現職教員研修制度の立上げ、研修教材や研修プログラムの開発、研修の評価、プロジェクトの評価などに対する技術支援を行うため、ケニアSMASEプロジェクトのカウンターパートであるCEMASTEA研修講師やSMASEプロジェクト専門家を各国に派遣しています。アフリカ理数科教育支援における先行事例であるケニアにおける経験を元に、実践的な助言を行っています。
ケニアからのWECSAメンバー国に対する技術支援実績(2005〜2010)
| 年度 | 対象国数 | 対象国名 | ケニアからの派遣者数 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 4 | ブルンジ、マラウイ、ナイジェリア、ニジェール | 21 |
| 2006 | 6 | マラウイ、ニジェール、ナイジェリア、ルワンダ、タンザニア、ウガンダ | 43 |
| 2007 | 11 | ブルキナファソ、ブルンジ、ガーナ、レソト、マラウイ、ニジェール、ナイジェリア、ルワンダ、セネガル、ウガンダ、ザンビア | 50 |
| 2008 | 13 | アンゴラ、ブルキナファソ、マラウイ、ニジェール、ナイジェリア、ルワンダ、シエラレオネ、セネガル、スーダン、スワジランド、タンザニア、ウガンダ、ザンビア | 64 |
| 2009 | 8 | アンゴラ、ブルキナファソ、ニジェール、ナイジェリア、ルワンダ、セネガル、スーダン、タンザニア | 18 |
| 2010 | 8 | アンゴラ、ブルキナファソ、ニジェール、ナイジェリア、ルワンダ、セネガル、スーダン、タンザニア | 20 |
| 合計 | 216 | ||
SMASE-WECSA域内会合
WECSAメンバー国間の情報共有や各国が直面する課題解決のための経験共有、理数科教育に携わる関係者のネットワーク構築などを目的として年1回メンバー国が集まる域内会合を実施しています。開催実績は次の通りです。
SMASE-WECSA域内会合開催実績(2001〜2011)
| 回 | 開催地 | 開催期間 | テーマ | 参加国数/人数(注1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国数 | 人数 | ||||
| 第1回 | ナイロビ(ケニア) | 2001年 2月 |
Mathematics and Science Education : Enhancing Classroom Activities for QualityTeaching and Learning in Eastern, Central and Southern Africa Region. | 12 | 73 |
| 第2回 | ナイロビ(ケニア) | 2002年 6月 |
Enhancing Classroom Activities for Quality Teaching and Learning in Eastern,Central and Southern Africa Region. | 15 | 68 |
| 第3回 | アクラ(ガーナ) | 2003年 6/7月 |
Enhancing Classroom Activities for Quality Teaching and Learning in Africa. | 20 | 90 |
| 第4回 | ムプマランガ(南アフリカ) | 2004年 5/6月 |
Enhancing Classroom Activities for Quality Teaching and Learning in Eastern,Central and Southern Africa Region. | 21 | 111 |
| 第5回 | ギタラマ(ルワンダ) | 2005年 6月 |
Enhancing Classroom Activities for Quality Teaching and Learning in Eastern,Central and Southern Africa Region. | 30 | 133 |
| 第6回 | サレイ(セネガル) | 2006年 5/6月 |
Enhancing classroom activities for quality teaching/learning of Mathematics,Science and Technology in Africa. | 30 | 93 |
| 第7回 | ルサカ(ザンビア) | 2007年 6月 |
Enhancing Classroom Activities for Quality Teaching and Learning of Mathematics,Science through Lesson Study. | 31 | 167 |
| 第8回 | ナイロビ(ケニア) | 2008年 5月 |
Successful and Sustainable SMASE-WECSA Association for Better Teaching andLearning of Mathematics and Science in Africa. | 26 | 96 |
| 第9回 | ナイロビ(ケニア) | 2009年 11月 |
Successful and Sustainable INSET Activities and Government Support for QualityTeaching and Learning. | 23 | 68 |
| 第10回 | ナイロビ(ケニア) | 2010年 11月 |
A Reflection on a Decade of Promoting Mathematics and Science Education inAfrica. | 29 | 108 |
| 第11回 | ナイロビ(ケニア) | 2011年12月 | The Way Forward of SMASE WECSA (Sustainability beyond 2013) | 26 | 75 |
- (注1)オブザーバー参加を含む











scroll