【ブース出展報告】第11回おかやま環境教育ミーティング

そしてクリーンに
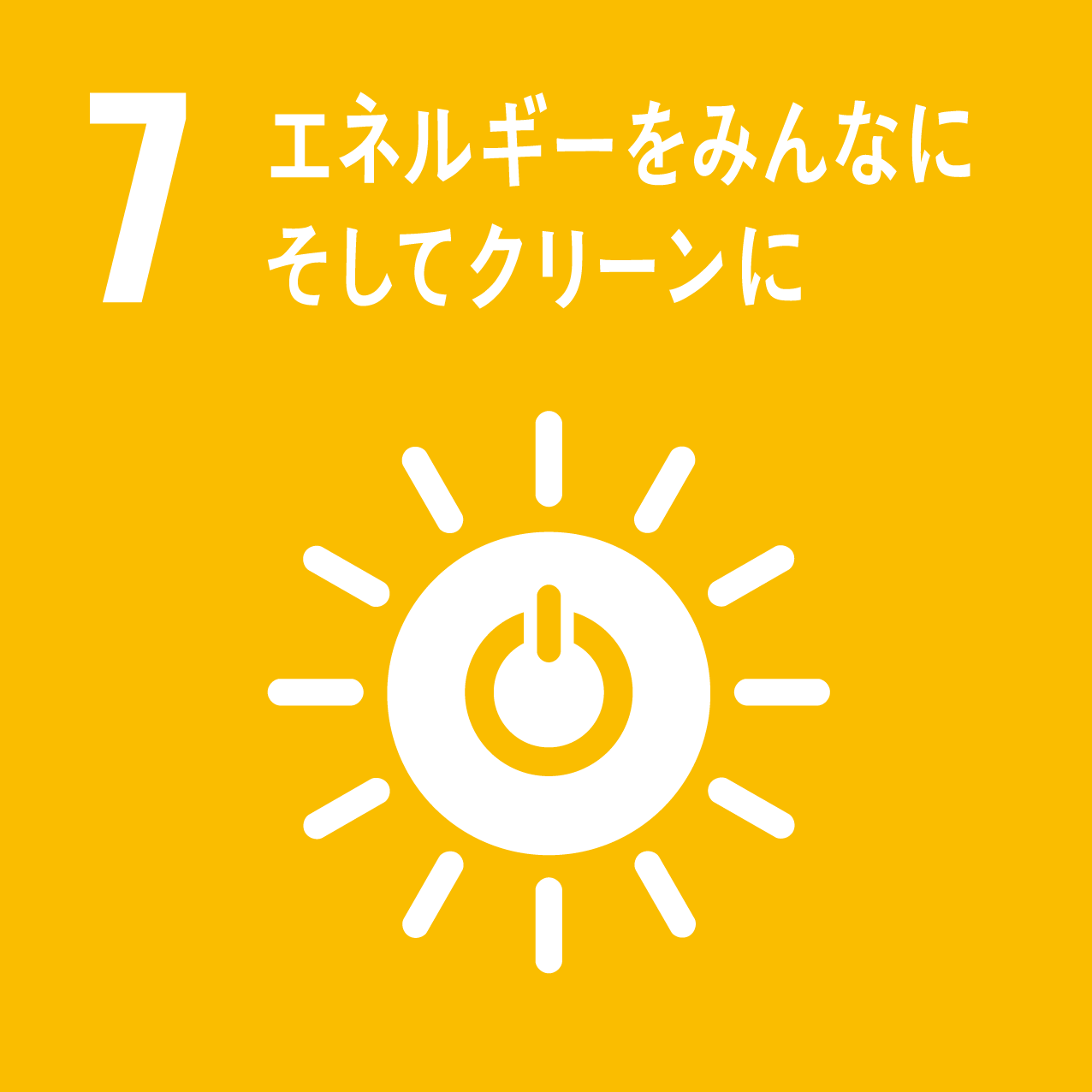

2024.10.18

分科会の様子
2024年9月23日(月)に、第11回おかやま環境教育ミーティングが岡山国際交流センターで開催されました。(主催:おかやま環境教育ミーティング実行委員会、岡山県、岡山県環境保全事業団)
おかやま環境教育ミーティングは、持続可能な社会に向けて、
・環境教育に関係する人同士がつながる場
・環境教育の意義ややりがいを共有し、お互いに学び合い高め合う場
・それぞれの環境教育活動を理解し認め合い、協働が生まれる場
の創出を目指して、毎年岡山市で開催されています。
学校、企業、行政、NPOや環境団体等、環境問題や環境教育に関心のある子どもから大人まで幅広い世代が参加しました。
午前はつながりの場として計29のブース展示、午後は学び合いの場として5つのテーマで分科会・全体会という構成でした。今年で11回目の開催となりJICA中国のブースでは、県内の企業や教育機関等がJICAとの協働で開発途上国における環境課題にも取り組んでいることを紹介するパネルを掲示しました。水や廃棄物の問題に関心を持つ中学生・高校生が多くブースへ立ち寄って下さいました。
分科会の1つでは、「地球にやさしい選択、エシカル消費へ ~世界を変える力はあなたにも~」というテーマで、JICA海外協力隊経験者の田賀朋子さん(派遣国:セネガル/職種:コミュニティ開発)がスピーカーとして登場しました。
田賀さんが派遣されていたセネガルでは、自分好みの布を買って仕立て屋に持ち込み、服をオーダーメイドするのが一般的とのことで、アフリカ布で作った服を着ると現地の人がとても喜んでくれ、おしゃれの話題に花が咲くこともあったそうです。ある時田賀さんは、仕立て屋の路地裏に布の切れ端が落ちていることに気づき、布の切れ端とビニールゴミを使った商品づくりを試みました。その後、その商品の企画を通じ、のちに現地の責任者となる方と出会ったそうです。
学生時代から国際協力に関心があり、国際機関で働くことも考えていたという田賀さんは、この商品作り経験から「持続的且つ、対等な関係性の中で繋がりを持てる活動」を模索するようになりました。その中で、現地の人と継続して関わりたいという思いを再確認し、現地と繋がりつつ自らも楽しめる服を作りたいと改めて思うようになりました。
JICA海外協力隊としての活動中は商品の販売まで至りませんでしたが、帰国後にまず自分のできる範囲で服作りを始めました。試行錯誤する中で今の活動形態に至り、現在は店舗を持たずイベントなどへ出向き1人1人と対話し、商品が出来た背景等説明を交えながら販売するスタイルが出来上がったことを率直にお話されました。また、自分が好きなものを無理なく製作・販売し、人と人がやさしく繋がれるような活動を続けたいと語られました。
田賀さんのお話をうけ、「私たちはどういう価値観で消費をしているか」をテーマにグループで考えを共有しました。価格や品質、安全、デザインなど様々な意見が挙げられましたが、安く大量に購入することへの疑問提起を通じ、「目先の情報にとらわれすぎず、適正価格で対等に売買できる関係に目を向けること」や「作る人、使う人双方が幸せになれるよう考える消費ができれば」と言った意見が挙げられました。
最後は、会場全体の振り返りとして、学生、企業、団体、行政関係者などで構成された小グループに分かれ、今後取り組みたいことや、そのためにどのような行動をするかなどを話し合いました。今後につながる新たな出会いが生まれ、環境分野を通じた岡山の強みを存分に感じられた1日でした。
(報告:岡山県JICAデスク 橋本千明)

きっかけは布の切れ端とビニールゴミを使った商品開発

JICAと協働して環境課題に取組む企業をパネルで紹介
scroll