【岡山県:出前講座レポート】異文化コミュニケーション


2024.11.19
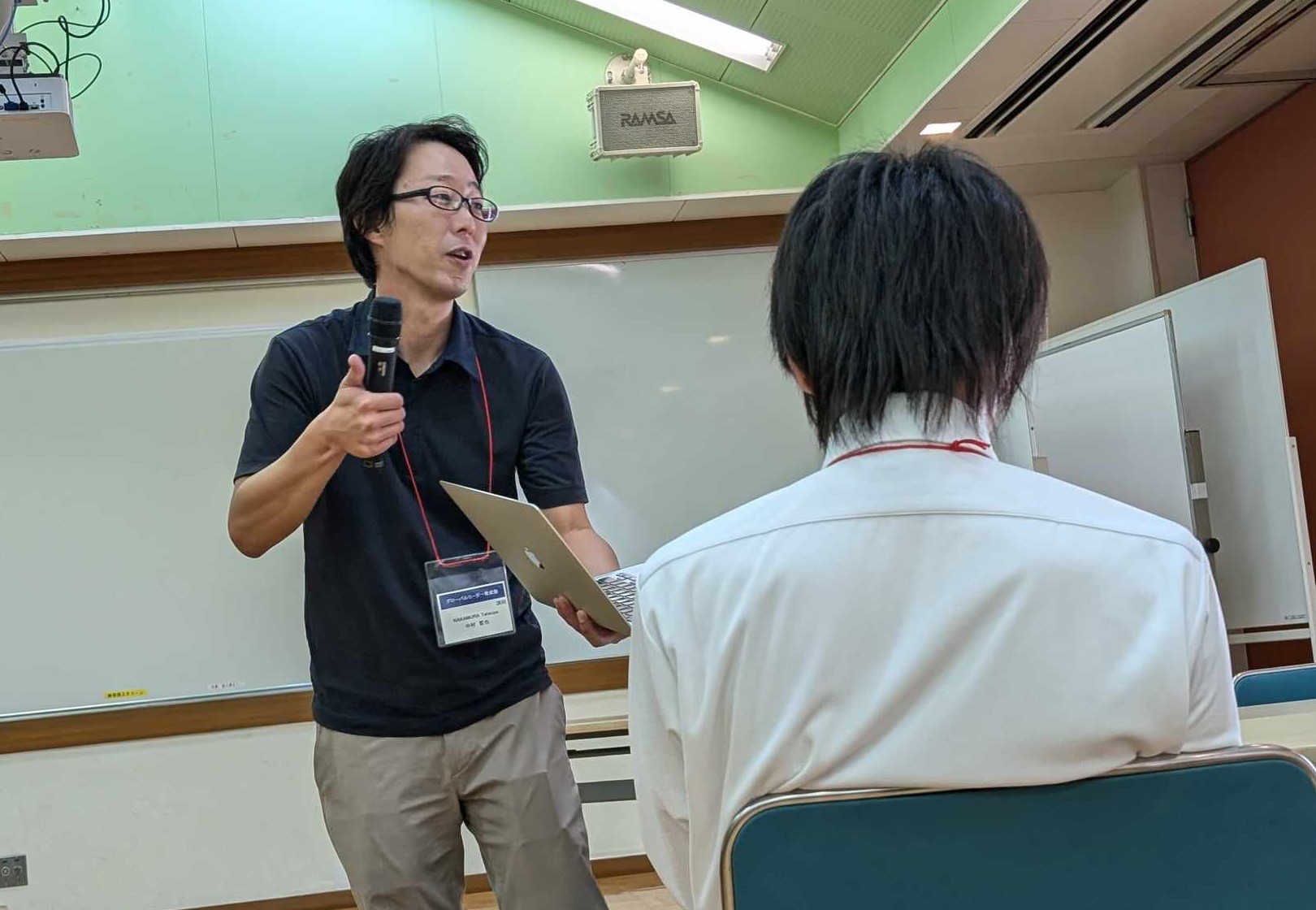
学生に語りかける講師
2024年10月5日(土)、岡山県青少年教育センター閑谷学校にて、「グローバルリーダー育成塾2024」の初日プログラムとしてJICA国際協力出前講座を行いました。「中国地区高専学生国際交流支援コンソーシアム」主催のもと、中四国の高等専門学校生16名(うち留学生4名)が参加し、JICA海外協力隊経験者・中村哲也さん(派遣国:モンゴル/職種:コミュニティ開発)を講師に、異文化理解の学びを深めました。
当初は緊張感が漂う中でスタートした講座でしたが、参加者たちは徐々に打ち解けていきました。最初のワークショップは、3つのグループに分かれて行われたトランプゲーム。各グループで異なるルールを設定し、その後メンバーが他グループへ移動するという形式で、実際の異文化との接触を模擬的に体験しました。
振り返りでは、グループ間を移動した参加者から貴重な気づきが共有されました。「ルールの違いに戸惑いながらも、新しいグループのメンバーがジェスチャーで丁寧に説明してくれた」、「場の雰囲気を読みながら、自分なりにグループの方法に適応しようと努めた」といった声が聞かれ、異文化コミュニケーションの本質に触れる機会となりました。
イギリスで平和学を学んだ後、JICA海外協力隊として活動した中村さんは、派遣国だったモンゴルを「第二の故郷」と呼ぶほどの愛着を持つようになったといいます。特に印象的だったのは、現地での約束に関する文化の違い。後から入った予定が優先されるという現地の習慣に対し、中村さんは毎日こまめに連絡を取り続けるという工夫で対応したそうです。一方で、完全には慣れない文化があることも率直に語り、日本と異なる文化や価値観と、その理解の難しさに向き合っている姿勢を示しました。
また、国際社会と日本のコミュニケーションの違いの一例を紹介しました。国際社会では「状況・文化・考え方」をお互いに理解するために言葉でのコミュニケーションを重要視する反面、「日本人はみな同じ」と無意識に思い込んでいる私たちは、言葉でストレートに表現するよりも、場の雰囲気を察したり、相手の気持ちを推察したりしながら意思疎通をはかることに慣れている面があります。国際社会では自己主張も必要であり、また時にはストレートな言葉で伝えないと相互理解も難しい。その違いを意識して言葉ではっきり伝える努力が必要、と中村さんは話してくれました。
講座の締めくくりに、中村さんは2つの重要なメッセージを贈りました。「海外での円滑なコミュニケーションには、言葉で伝えることが不可欠」という点と、「この合宿中に異文化コミュニケーションのスキルを意識的に磨いてほしい」という期待です。
この講座を通じて参加者たちは、異文化との出会いが単なる違いの発見にとどまらず、相互理解と適応のプロセスであることを学びました。今後グローバルな視野を広げていくにあたり、貴重な第一歩となったことと思います。
(報告:岡山県JICAデスク 橋本千明)

国際社会と日本のコミュニケーションの違いの一例を紹介




scroll