【研修実施レポート】JICA研修史上初めての水素エネルギー課題別コースを開催!
2022.03.29
世界9ヵ国の研修員、水素エネルギー利用の推進を学ぶ!
課題別研修:水素エネルギー利用の推進 - CO2フリー社会に向けたエネルギー政策
研修期間:2022年1月17日-2022年2月4日
参加国:ナイジェリア、ウクライナ、エジプト(11名)、ウルグアイ(8名)、コロンビア(2名)、ウズベキスタン(3名)、チリ(2名)、マレーシア(2名)、パキスタン
参加人数:31名
世界9か国のエネルギー省関連の政府関係者31名が、1月17日から3週間の期間にて、東京工業大学InfoSyEnergy研究/教育コンソーシアムをはじめとした産官学の多彩な講師による遠隔研修に参加し、日本の最先端の水素エネルギー技術を学びました。
日本では、2017 年に世界で初めて水素基本戦略を策定し、国を挙げて水素社会の実現に向けた各種取組を進めています。一方、世界では、2020 年以降、2050年のカーボンニュートラルの実現を目指す欧州各国を中心に各国が相次いで水素戦略を発表するなど、世界で水素利活用の促進に向けた取組が加速しています。

開発途上国においても、究極のクリーンエネルギーとされる水素の利用促進のために、政策的な枠組み、大学等研究機関や民間セクター等との連携、利用促進のための啓発活動等包括的な取り組みが急務となっています。
カーボンニュートラル実現に向けて、開発途上国の関係者が水素供給、利活用促進に向けた政策立案能力を向上することを目的として、この研修は実施されました。
研修では、初日のオリエンテーション、各国の参加者から水素エネルギー事情を説明するカントリーレポート発表で始まりました。各国とも熱意をもって水素エネルギーの利用促進を進めていることがわかりました。
続けて、東京工業大学InfoSyEnergy研究/教育コンソーシアムによる「エネルギーキャリアを使用した水素利用の促進、燃料アンモニアとサプライチェーン」ついてのオンデマンドでの講義が行われました。オンデマンド講義では、研修員がビデオを視聴し、次の日には質疑応答・議論の時間を設け、活発な意見交換が行われました。
資源エネルギー庁による日本政府の役割と取組、北九州市による自治体の役割と取組、さらに東京工業大学InfoSyEnergy研究/教育コンソーシアムよる大学研究機関の役割であるグローバルコラボレーション-ゼロカーボン社会に向けた水素技術について、最先端の知見の共有が行われました。
日本における民間セクターの役割では、種々の水素キャリアの視点から各企業の方々に講義を行っていただきました。現状の技術では貯蔵・運搬等に課題を有する水素を効率的かつ大規模に貯蔵・運搬するためのアンモニアやメチルシクロヘキサン、液化水素の可能性と課題について講義を行いました。
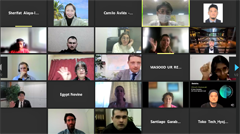
最終日には、研修で獲得した知見を利用して作成されたアクションプラン(今後の目標達成のための行動計画)を研修員が発表しました。ウズベキスタンの研修員からの自国で水素エネルギー開発をスタートさせるための水素利活用促進に係る方針の報告、ナイジェリアより再生可能エネルギー・水素エネルギー普及のための課題の報告、さらにウクライナからは、水素のバリューチェーンにおいて十分な設備が整っており、より広範な欧州のエコシステムにおいて成功する可能性を秘めているなどの発表がありました。
※全研修日程は下記関連ファイルを参照願います。
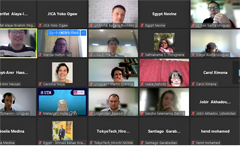
関連ファイル:
3週間にわたり実施した本コースは、研修員にとって、知識はもちろんのこと、各国の再生可能エネルギーや水素エネルギー分野の専門家が集まったことから、オンライン上とは言え、研修員同士、日本側の講師たちとの間で活発な質疑応答・意見交換がなされました。
以下、研修員の感想をいくつかご紹介します。
今年度の研修は修了しましたが、来年度以降も実施予定です。本コースで得た知識・技能や人脈を生かし、水素エネルギーに関するリーダーとして自国の水素利活用の促進に貢献されんことを期待しています
(JICA九州 研修業務課)
scroll