【青年研修】地元資源を活用した産業振興(観光振興)/観光振興における「連携」を強化し観光客増に挑むベトナム
2024.09.27
8つの世界遺産を有するベトナムは、近年、観光地としても注目されています。2023年は、ベトナム政府が定めた年間目標800万人を大幅に上回る1,260万人もの外国人観光客が訪問。コロナ禍前のピークだった2019年の水準(1,800万人)には届かないものの、ベトナム国家観光局は、2024年の目標として、1,700〜1,800万人の訪問客誘致を目指しており、今後はさらなる観光客増を見越した観光振興策が必要とされています。コロナ禍を経て、世界が求めるようになってきている持続性に配慮した観光、地域資源を生かした観光など、これまでのベトナム流とは異なる視点で開発された観光振興を学ぶため、ベトナムから共産党青年同盟を中心とする12名が来日しました。
海外から日本への観光客数は、2019年の3,188万人をピークにコロナ禍の影響で一旦大きく落ち込んだものの、2023年には2,506万人まで回復しており、日本は世界的にも人気の旅行先のひとつに数えられています。日本の観光振興策を学ぼうと、ベトナムの観光開発を担う共産党青年同盟を中心とする12名が来日し、2024年7月16日〜8月2日の日程で青年研修『地元資源を活用した産業振興(観光振興)』が行われました。
年々進化する世界の潮流を踏まえた日本の観光振興策を学ぼうとするベトナムの意欲は相当に高く、2015年に初めて研修員を受け入れたベトナム向けの本研修は、今年で4回目を数えます。本研修で目標としたのは、観光振興における制度や実施体制を中心とした基本的な知識を身につけ、さらに現場視察や関係者との意見交換を経て、日本の経験や背景から観光振興のあり方を学んでいます。研修は東京でスタートし、観光庁や学識者から日本の観光の現状や東日本大震災からの復興の一部を担う観光政策についてレクチャーを受け、まずは日本全体の観光振興の概要を理解してもらいました。その後、拠点を福島県会津地域へ移し、地方の観光資源に触れながらさまざまな体験や視察を行い、具体的な観光運営方針や実践手法、マーケティングについて学びました。

大正大学で観光を学ぶ学生との意見交換会の一コマ
会津若松市に拠点を移して行われた地方研修においては、歴史ある鶴ヶ城や、かつての宿場町の大内宿など、従前から人気の観光スポットに加えて、双葉町にある東日本大震災・原子力災害伝承館を訪問し、語り部の話に耳を傾け、震災と爪痕と復興の現場を見学しました。またスノーリゾートで有名な磐梯町では、日本大手のリゾート運営会社が経営するホテルに宿泊し、温泉や食事、おもてなしサービスを実際に体験するとともに、季節型リゾート経営の方針や人材開発、さらには広報や地方自治体との連携などの運営体制についても詳しくレクチャーを受けました。
本研修の委託先である『会津若松市国際交流協会』の小林真司さんは、本プログラムのねらいをこう語ります。「時代とともに観光をとりまく状況も目まぐるしく変化するため、プログラム構成には頭を悩ませましたが、前回研修の評価を参考に、新たな観光への取り組みとして“連携”の重要性を伝えるため、自治体や企業、ボランティア団体との連携の手法を学び、多様なネットワーク創出のヒントが得られるような構成にしました。また、日本全体の観光プログラムを東京で、また地方の観光プログラムを会津で行うことで、日本の取り組みを全体像から把握し、具体策は地方で体験しながら理解してもらえるよう配慮しています。さらに研修員と年代の近い大学生との意見交換や、実践形式のワークショップは、これまでにはなかった新しいプログラムで、インターアクティブな研修になるように今回から導入したものです」
また、東北地方の観光においては、震災や復興も重要なトピックスです。「世界的にも大きな災害が多発していますので、震災と原子力災害を経た福島の復興がどのように進み、時とともに観光への影響がいかに変化したのかも、理解してもらえるようにしました」と、小林さんは話します。

茅葺屋根の古民家が建ち並ぶ大内宿での視察

ガイド体験を受けながらの鶴ヶ城の視察の様子

双葉町の伝承館を訪れ、語り部の声に熱心に耳を傾けました
研修員からは、「観光庁のレクチャーが印象深かった。復興や、産業と観光を合わせた地域活性化を行っているところが参考になった」という声や、「リゾート見学がよかった。ホテル内の装飾、特産物イベント、夜の共有スペースでの盆踊り開催など、地元の伝統文化を短期の宿泊客でも味わえるようにしているところに感心した」、「実際に福島県を訪れ、震災関連の講義を受けたことで、来日前に持っていた恐怖心がなくなった。被災地域の人々と自治体が、将来に自信を持って生きていることに感銘を受けた」という感想がありました。
初日から最終日まで熱心に研修に取り組んだ12名の研修員に、特に印象深かったプログラムを聞くと、2泊3日のホームステイという声もありました。小林さんは、「ホームステイは研修プログラムの恒例で、一般のご家庭に研修員一名ずつお世話になります。ホストファミリーと休日を一緒に過ごし、寝食を共にすることを通じて、集団プログラムでは触れることができない、会津地域の生活・文化を理解する有効なプログラムとなっています。また、個人でホームステイすることで12の異なる文化に出会え、研修員同士でその体験を共有することで文化の広がりも理解してもらえます」と話します。
研修員からは、「日本の文化や日本人の生活を肌で感じることができる貴重な体験だった。2泊3日だと時間が足りず、期間をもう少し長くしてほしい」という声もあがりました。
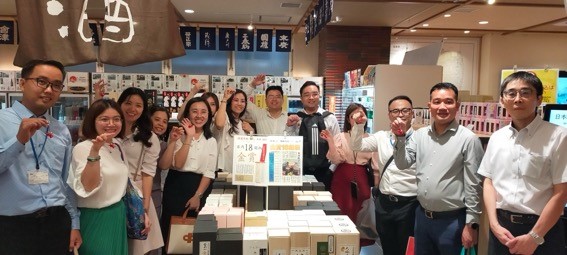
日本橋のふくしま館にて。福島への期待が膨らみます。

伝統文化体験としての茶の湯も好評でした
研修後期のワークショップでは、「観光のキラーコンテンツを作って観光プランを策定する」という実践的な課題に対し、料金体系やプロモーションまでを想定したプラン作りをグループで協力して行いました。「自分が観光客だったら楽しいだろうか」という視点を軸に、ひとりよがりのプランにならないよう、運営側と観光客側の双方向での意見交換がなされ、多様な視点を持つように工夫しました。このワークショップがアクションプラン(帰国後の具体的な活動計画)作成への弾みとなり、研修員一人ひとりが考えを深化させるきっかけになればと考えます。
小林さんは、「帰国後の研修員たちは、それぞれの職場で別々に観光開発に取り組むことになると思いますが、同じ研修を受けた仲間として、折々にコミュニケーションを取れる関係であってほしいですね。困ったときに助け合える関係を維持して、励まし合いながら観光開発に取り組んでもらいたいです」と、12名の研修員の飛躍を期待します。
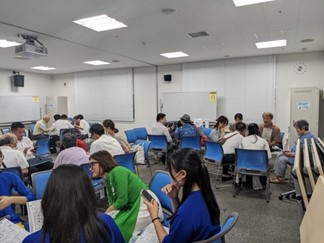
市民交流の様子(ベトナム語・英語・覚えたての日本語を使って)

研修を修了し、充実の笑顔。
scroll