【草の根技術協力】ベトナムと日本、両国の課題にアプローチする日本式介護人材育成事業がまもなくスタート
2025.04.24
現在、我が国では介護人材が不足しており、宮城県でも顕著な課題となっています。一方、ベトナムでも近年急激に高齢化が進んでおり、介護人材の育成と確保を要している状況です。こうした双方の現状を受け、宮城県はベトナム政府と2023年に『日本へのベトナム人技能実習生・特定技能労働者・技術者の送り出し・受け入れ推進に関する協力覚書』を締結し、ベトナムからの積極的な人材の受け入れを目指しています。
2025年度からの開始を予定している草の根技術協力事業『人材環流を内包する日本式介護人材事業』は、ベトナムの大学で日本式の介護技術を教え、指導者育成やカリキュラム・教材作成などその体制を整備することを目的としており、そこで学んだベトナム出身者が、日本やベトナムの介護事業所で働き手として活躍することが期待されています。
受託する『さくら事業協同組合』は、2022〜23年にベトナムでJICAの中小・SDGsビジネス支援事業(案件化調査)の実施実績があり、介護人材の現地での実情やニーズ把握に努めてきました。同組合の理事長である鎌田厚司さんは、「ベトナムでは人口の8.62%が65歳以上と高齢が進んでいる一方で、驚くことに『介護』という言葉がなく、介護学を専門に学べる教育機関が存在しません。現地には高齢者が入居できる高齢者向け療養施設が増えてきましたが、あくまで医療の一環として看護師が高齢者のケアに当たっているのが現状です。まずは、現地で適切な介護サービスを提供できる人材の育成環境を構築しつつ、育成したベトナム人が日本で技能実習生として活動を経てスキルアップした後、ベトナムへ帰国してさらに活躍、といった人材の環流を期待しています。ベトナムの介護人材育成のための本事業ですが、日本とベトナム、両国にとってメリットとなるのが本事業です」と話します。

中小・SDGsビジネス支援事業(案件化調査)でナムディン医療専門学校を訪問
一番左:今野渉さん(専務理事) 中央:鎌田厚司さん(理事長)
2022〜23年に同組合が行った上述の案件化調査は、日本での技能実習を終えてベトナムに帰国した実習生(日本式の介護技術を身につけた者)に対して技術を活用できる就労場所を提供する「介護人材紹介サービス」の新規市場開拓を目的に実施されました。「ニーズがあることが判明した一方で、同時に介護人材の不足や育成が優先課題であり、そのための研修講師を育成して欲しいと、育成プログラムの導入が現地より期待されました。ハイズオン医療短期大学(現在:ハイズオン医療技術大学と合併)を訪問した際には、『ベトナムと日本の文化の違いを汲んだ介護教材を大学へ導入し、組合が授業を行うだけでなく、教員に同教材の教授方法も教えて欲しい』と、強いリクエストを受けました」と、同組合専務理事の今野渉さんが、本事業提案に至る経緯を語ります。
その要望に応えるため、今回の草の根技術協力事業では、次のような複数のステップを設けました。
① ハイズオン医療技術大学に教授方法を移転し、同大学教員が学生に対して介護教育を実施できるようになること
② 有望な教員を「マスタートレーナー」として養成し、彼らが他の大学の教員に対して介護教育を教えると同時に、さらに「マスタートレーナー」を育成すること
③ 介護人材育成を行えるベトナムの教育機関を増やし、ベトナム全土で日本式介護を学んだ介護人材を増やすこと
案件化調査で培ったハイズオン医療技術大学とのネットワークを活用し、同大学を同事業の相棒となるカウンターパートに据えます。ハイズオン医療技術大学があるハイズオン省を起点とし、その後はニーズのあるベトナム北部のソンラ省やナムディン省を中心に展開を予定します。
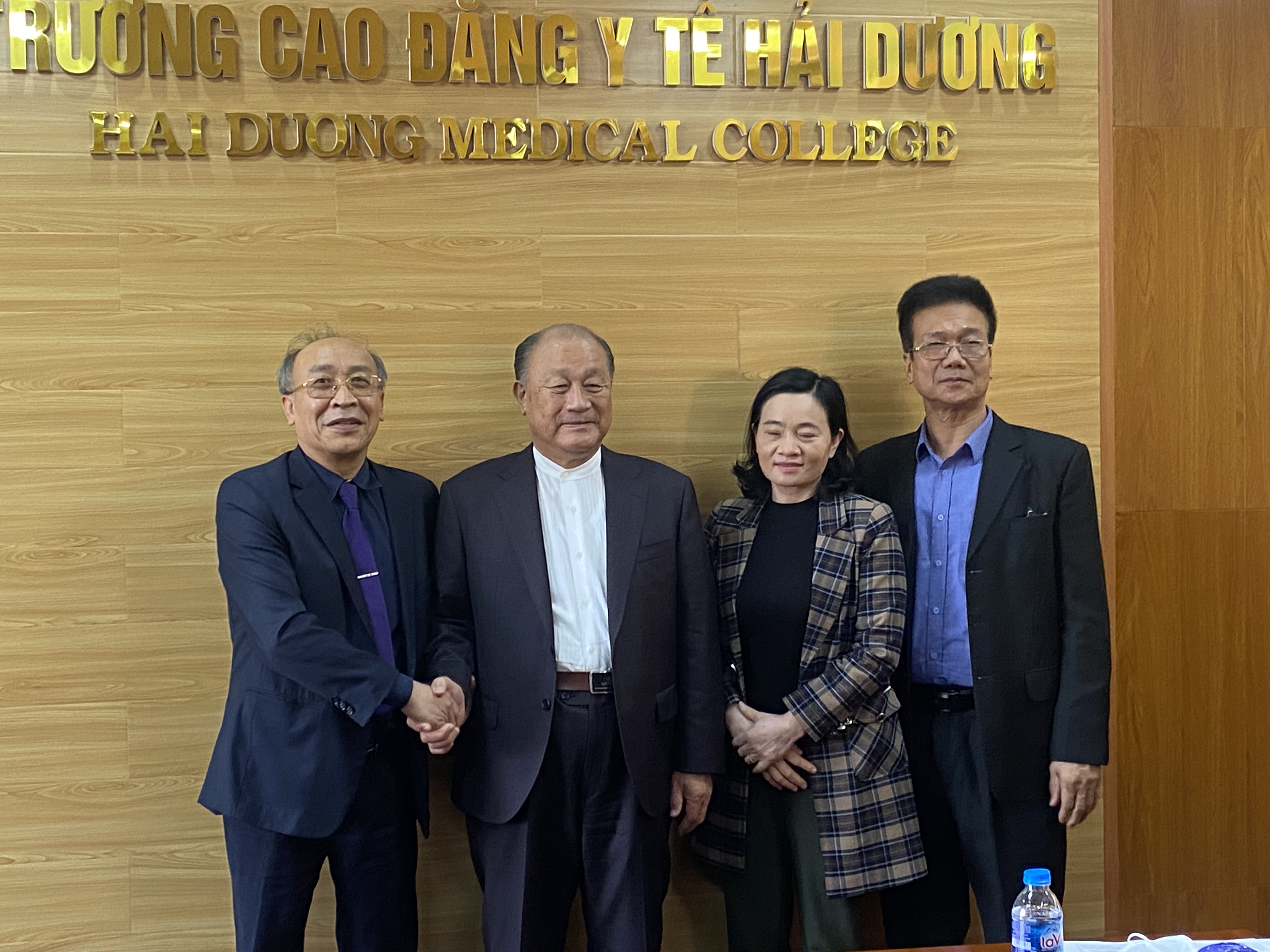
本事業のパートナーとなるハイズオン医療短期大学(現:ハイズオン医療技術大学)訪問の様子
左から2人目:鎌田厚司さん(理事長)
「本来、本事業は2024年秋からスタートの予定でしたので、当組合としてプロジェクトを遂行する準備は充分に整っています」と鎌田さん。ベトナムの国内事情やハイズオン省の教育機関の組織改変などの影響を受け、本事業の進め方についてのカウンターパートの理解を得るのに時間がかかり、本事業のスタートは当初のスケジュールから遅れる見込みです。しかし、遂行に不安はありません。「私たちは、技能実習生の受入開始から21年、宮城県で初めての介護技能実習生受入認可を取得した組合です。これまでに多くの技能実習生の受け入れを行っており、ベトナムにも拠点を持ち運営していますから、彼らの文化や商慣習については熟知しているつもりです。今回、現地の大学で日本式介護技術を教えることになりますので、新たに介護教育分野で専門性の高い人材を組合内部に配置しました。本事業は『介護技術マスタートレーナーの養成の仕組みが構築されること』が大きな目標となります。実施するのはハイズオン省という地域で、都市部ではスムーズに展開や改善が図れることも、郡部では難しい一面も予想しています。しかしながら、私たちはその難しい郊外のエリアでこそ、豊かに暮らすべきで、幸せになって欲しいと思うのです。そこに暮らす地元の方々にまずはこの事業のメリットを届けたいと思っています」と続けます。

ハイズオン医療短期大学(現:ハイズオン医療技術大学)での協議の様子
本事業の波及効果として、現地の送り出し機関が実習生に負担させる過大な準備金制度に一石を投じることも目指します。現地ブローカーの介在によって実習生の経済的負担が増し、実習を断念せざるを得ない状況が散見されています。本事業での中長期的な目標は、これらの要因にも対策を施し、適切な手数料以外の負担をなくすための仕組みづくりも同時に目指しています。こういった多様な視点から、本事業は適正な送り出しやこれら労働者の人権保護、ベトナムと日本双方での活躍の促進に向けて①政策・制度の整備・運用、②人材育成、③組織的・人的ネットワーク構築・強化を重視する草の根技術協力事業の「外国人材受入・活躍支援枠」で採択されており、期待値も大きいものです。
宮城県経済商工観光部国際政策課長の高橋征史さん
提案自治体である宮城県経済商工観光部国際政策課長の高橋征史さんは「宮城県では、さくら事業協同組合の皆様と協働で本事業を活用し、ベトナムの介護人材育成に向けた取組を通じて、将来を担う質の高い介護人材の育成や県内の介護人材不足の解消を目指してまいります。また、現在、県内では外国人労働者としては最大の約5,000人のベトナム人の方々に技能実習や特定技能等として御活躍いただいており、本県の産業基盤を支える重要な人材となっております。本事業を活用した国際協力活動により、本県とベトナムの関係性をより強固にし、国際社会への貢献を図るとともに、ベトナムにおける本県の知名度向上と人材育成を図ってまいりたいと考えております。」と、期待を寄せています。
宮城県とベトナム、双方の高齢化問題に多様な視点からアプローチする本事業。ベトナム国内の大学でトレーナー育成環境を整えるなど、環境整備や協力体制構築には難しさもありますが、現地に精通したさくら事業協同組合の持つ事業推進力に期待しています。
scroll