一人ひとりの「学ぶ力」が湧いてくる!-ウズベキスタンの子どもたちの教育DXに挑む-(株式会社学書/愛知県/2020年度案件化調査)
2023.06.08
ウズベキスタン共和国(以下、ウズベキスタン)で教育DX(デジタル技術を活用した教育モデルの改革)に挑む、株式会社学書。現在、JICAの案件化調査にてウズベキスタンの中学校でデジタル教材の活用可能性を調査しています(実施計画期間:2022年6月~2023年12月)。
日本の大手民間塾でも採用されている学書のテキスト教材は、1000アイテムを超えます。その中から本調査では「デジタルドリル(中学版)」と「基本のキ」をウズベク語に翻訳し、中学1年生の授業で使用し調査しています。ウズベキスタンの子どもたちの学力の底上げと、教員の指導力向上の道しるべとなりえるのでしょうか。現地の教室より届いた心揺さぶられるストーリーをお届けします。

ウズベキスタン「デジタルドリル」を使った授業風景
ウズベキスタンは安定した出生率を背景に、総人口3,440万人(2022年:国連人口基金)のうち18%にあたる約600万人程度(2022年:国民教育省)が義務教育を受ける年齢の人口となります。
義務教育は11年間。2019年に識字率100%を達成していますが、きちんとしたウズベキスタン語を読み・書きできる子はそこまで多くはありません。
旧ソ連系の影響があり、授業では“出来る子”のみが理解でき、“出来ない子”は後ろの席でただ座っているだけ。早いスピードでどんどん授業がすすめられ、エリート教育ともいえる指導法が現在も続いています。

教室でテストを受ける様子
ウズベキスタンの教育での改善の要項は大きく4つ。「教材の不足」「都市と地方の教育格差」「教師の能力不足」「教師数不足」があります。
その中でも一番大きな教材不足は深刻なもので、ドリルのような副教材がほぼありません。数少ない副教材はロシア語と英語の輸入版のみで、印刷書籍は高価で購入もままなりません。
今回のプロジェクトで使用しているのはウズベキスタン語に翻訳した「デジタルドリル 中学版」(数学)と「基本のキ」。デジタルなので何度見ても、何度質問しても先生には怒られません。ウズベキスタン語の解説動画(教員育成にもつながる)をセットで幾度も解説動画を繰り返し観て学ぶことで、理解することができたようです。
回線速度が十分ではない地域でも円滑な起動が可能なことから、ウズベキスタンの地方都市を含め広範囲で提供可能であると推察されます。
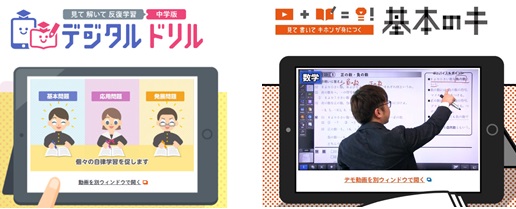
学書のデジタルコンテンツ(左:「デジタルドリル中学版」、右:「基本のキ」)
タシュケント市とブハラ州の学校で、デジタルドリルを使ったプレテスト、特別学習カリキュラム(注1)、ポストテストが終わり、教員・学生・保護者300人以上が集まり実証実験の結果を発表しました。セミナーの終わりにベスト3の学生を発表し、株式会社学書の田村社長がプレゼントをお渡しする時です。ブハラ州の1番学校のNadiraさんが1位と発表された時、Nadiraさんは涙を抑えることができず、その涙は保護者、先生と会場全体に広がり、拍手の中でプレゼントが渡されました。非常にエモーショナルなシーンだったそうです。
今回の表彰は、ポストテストでの最高得点ではなく、プレテストとポストテストの結果、伸びた差が一番大きい子を評価することにしました。
頑張り屋で真面目なNadiraさんですが、あまり数学が得意ではなかったそうです。本案件で実施した特別学習カリキュラムにNadiraさんは3ヶ月間欠かさず参加し、積極的に勉強した結果、“伸びた点差”が一番大きかったのです。(ポストテストではNadiraさんより点数が上の子もいました)

写真左から、学書の田村社長、ブハラ州1番学校の中学生Nadiraさん、Nadiraさんの保護者
セミナー終了後、副校長・担当先生にプロジェクトの成果やお話を伺いました。
担当の先生は「15年以上教員をしていますが、学力ばかりで評価して頑張っている子を評価しなかったことに気づきました。高得点が取れなくても一生懸命頑張っている子を応援する方法を知ることができました。高得点を取らせるだけが学校の役割ではなかった。」と、話してくれました。
株式会社学書 田村社長 / JICAスタッフ=J
J:
今回の実証実験の結果、伸びた点差が大きい子を評価する、という方式は社長のご提案ですか?
田村社長:
そうです。現地に行って初めて知りましたが、ウズベキスタンの教育はエリート教育で、数学の授業では成績の良い子から前に座らせ、理解できていない子は後ろの方でただ座っているだけでした。日本の教育は、基礎学力を定着させるためにスモールステップで学習を進めて行きます。日本の学習塾の方法でデジタル端末を使い、何度でも繰り返して勉強することで、自分の苦手分野を克服していく。これは「個別最適化」の手段の一つであり、自律学習形式で“伸びしろ”を伸ばせたことで、グンと点数があがる子が何人も現れました。

1位と呼ばれ前に出るNadiraさん
J:
Nadiraさん、顔を真っ赤にして泣いていましたね。
田村社長:
普段注目を浴びていなかった子たちが今回表彰されました。「まさか、自分が?」という気持ちだったと思います。周りの生徒や保護者もとても感動していました。
J:
先生方の反応はいかがでしょうか?
田村社長:
渡航したばかりのころ、先生方にお話を伺ったことがあります。「授業を行ううえで何を一番大切にしていますか?」と。そうしたら、「授業を完璧に行うこと」「時間通りに進めること」と答えたんです。
今回の実証実験後に先生たちが、「子供たちの表情を見て、“分かっているか分かっていないか”を感じることの大切さを知ることができた。」「授業中に数学の問題解説をしている時に後ろの席の生徒が『こんな解き方があります!』と手を挙げて発言してくれたんですよ!その瞬間にはとても驚きました。」と言っていました。考え方が大きく変わったようです。
J:
現地で困ったことや苦労などはありましたか?
田村社長:
苦労、というか、ウズベキスタンの生徒たちはテストで分からないことがあると助け合うためにおしゃべりしながらテストを受ける習慣があるようで、テストの時は一人で考えて受けるんだよ、ということを理解してもらい、徹底するまでが大変でした。
あとは、冬が寒く、マイナス20度まで下がり雪が降るため、生徒が学校に辿りつけない、ということもありました。デジタル学習があるおかげで通えない時には自宅でもできるという大きなメリットがありました。学校が停電になるとビデオが使えないのですが、そんな時は何度もビデオを観て覚えたファシリテーター(注2)(指導員)が、ビデオの先生のように教えてくれたこともあります。
J:
学校内でも口コミが広まりそうですね!
田村社長:
実は、すでに小学6年生の学年が立候補してくれ、第2回目の実証実験を3月~5月(2023年)に行ったばかりです。こちらの結果もデータ化しているところです。データ化することでロールモデルとなり、日本の学習塾の方法は海外でも結果が出るんだよ、と一目で分かっていただけると思います。計100名の生徒に実証実験に参加いただきまして、基礎学力の向上と学力格差の是正に貢献できたという結果とその検証データが得られたことは非常に有意義であり、今後に活かせる価値あるプロジェクトとなりました。
J:
世界に広まる教材になる予感がします。本日はありがとうございました。
────────────── インタビュー終 ──────────────
点数だけでなく、ひとり一人の「頑張り」を認めることの大切さを改めて感じると共に、現地の課題が解決される光が見えたプロジェクトの今後が大変楽しみです。
(注1)
パイロット版の特別学習カリキュラムの実証実験検証対象
教科と期間 【数学/週2回/60分/各3ヶ月間】
第1回/2022年10月-2023年2月/3校(7年生)計100名
第2回/2023年3月-5月/3校(6・7年生)計100名
(注2)
ファシリテーターを学書社が現地雇用契約者として派遣。
役割はデジタル利活用の自主学習の管理者のような存在で、授業は行いません。
案件の詳細は下記をご覧ください↓↓
scroll