- トップページ
- 事業について
- JICAグローバル・アジェンダ
- 農業開発/農村開発
- JICA食と農の協働プラットフォーム(JiPFA)
- 第5回年次フォーラム(2024年1月22日開催)報告
概要
第5回年次フォーラムは、「開発途上国の食料ロス削減を通じた食料安全保障への貢献 実例と戦略~グローバルな視点で現地の課題解決策に貢献する~」をテーマとした。
開会挨拶
JICA上級審議役 窪田修
本フォーラムのテーマ選定に至る世界の情勢の説明、同テーマに沿った課題解決の手段や知見をお持ちの登壇者へのお礼を述べた。

第一部 JICAからの報告
(1)JiPFA
の2023
年度活動報告と今後の方針
JICA
経済開発部 計画担当次長 森口加奈子
2023年度のJiPFA活動実績の報告、及び今後の取り組みを発表した。

(2)食料安全保障とJICAの取り組み
JICA経済開発部 部長 下川貴生
食料安全保障に貢献するJICAの取り組みを紹介した。世界は人口増加や経済発展の影響で、2050年までに食料需要が2010年比で1.7倍に増加するという厳しい現実に直面している。この増加する需要の中で、現在約8億人が食料不足に苦しみ、食料生産量の1/3が無駄に廃棄されていることは、国際社会にとって大きな課題である。特に開発途上国では、流通過程でのロスがこの問題をさらに深刻化させている。加えて、コロナ禍による栄養不足人口の増加、特にアフリカでの食料不足の深刻化は、紛争、経済的ショック、気候異変といった複数の要因が絡み合い、食料危機を引き起こしていることを示している。
このような状況に対応するため、国際社会はG7広島サミットの「広島行動声明」やCOP28のUAE宣言といった国際的な取り組みを通じて、食料安全保障の強化に向けた行動を加速している。持続可能な発展のための国際的な協力が必要であり、JICAも農業・農村開発を含む20の地球規模課題に取り組み、特に食料安全保障に対する脆弱性が高いアフリカでの支援に注力しており、飢餓の撲滅と食料安全保障の実現を目指している。
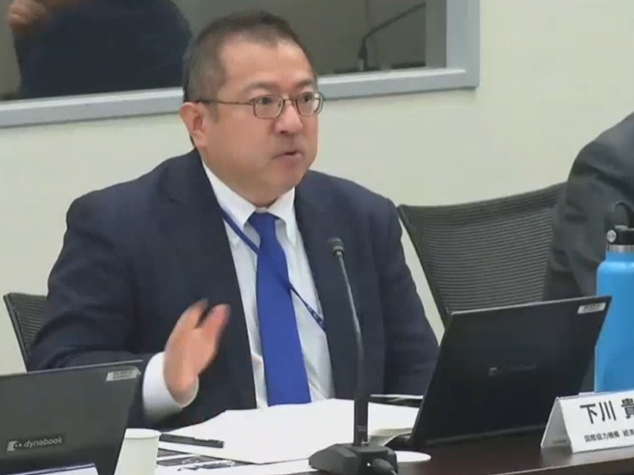
第二部 民間企業からの報告と質疑応答
1. 農道の整備による流通段階、及び灌漑施設の整備による生産段階での食料ロス削減に関する取組の紹介
~土を固めることの価値。食品ロス削減と気候変動対応への貢献~
株式会社SPEC 代表取締役社長 久保 祐一様、営業部長 上林 思瑶様
約50年前に日本で開発された土壌硬化剤は日本国内での使用に加え、開発途上国の農村部の道路や灌漑施設の整備に貢献している。カンボジアでの実証事業に成功し、現在ケニアで特殊土壌の硬化研究を現地大学と共に進めている。この技術が食品ロス削減にも役立つことを紹介する。
STEINは約50年前に日本で開発された土を固める素材であり、粘土質、砂質を問わず、土壌に約10%添加することで大型トラックも通行可能な強度を持たせることが可能である。この素材は、道路、水路、ため池の施工を短期間で可能にし、材料の大部分を現場の土壌から調達できるため、コストを大幅に削減できる。硬化メカニズムは土壌粒子を強固に引き付け、セメントの水和反応により強度を高めることで、施工後は大型トラックの荷重にも耐えうる強度を持つ。施工方法は土質試験に基づき、STEINと水の配合を行い、ロードローラーで転圧し養生することで、3~7日間で実用的な硬さを実現する。
日本の事例として、1975年に美瑛町の農道に使用されて以来、その農道はほぼメンテナンスフリーで利用され続けている。サハラ以南アフリカでは農産物のフードサプライチェーンにおける損失削減に役立つことが期待されている。インフラ整備の予算が限られる中、STEINを用いることで資材・輸送・施工コストを抑え、農業機械化や水資源の有効活用に貢献し、気候変動に強い農業に貢献することが可能である。
カンボジアでは農道の施工実験を行い、フィリピンやスリランカでは農業機械の利用促進のための農道や水路の整備に成功している。ケニアでは、灌漑水路や農道の改善、ため池での魚の養殖など、STEINを用いた多様なプロジェクトが展開されるなど現地の課題解決に貢献している。
STEINの利用は、施工コストの削減、施設の耐用年数の延長、維持管理の容易さ、地域の課題解決への貢献、現地生産による雇用創出など、多岐にわたる価値を提供する。今後のビジネス計画として日本国内外での普及を目指し、品質保証された材料を政府や建設企業、国際機関などに提供することで、その利点を広く伝えることを計画している。
STEINの機能とそれが生み出す価値を広く知ってもらうために積極的に情報を発信し、地域の課題解決に貢献する製品を提供していきたい。
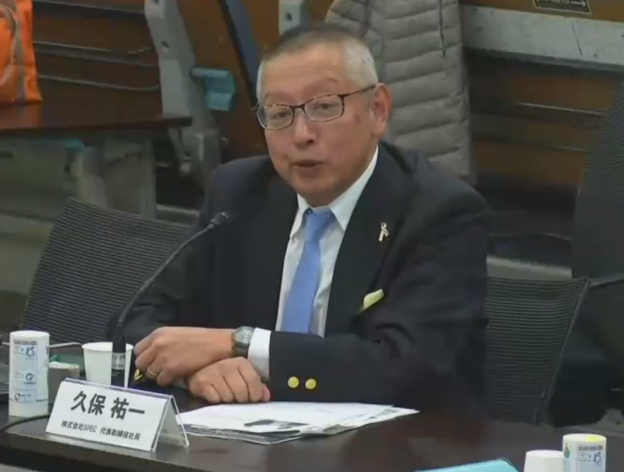
株式会社 SPEC 久保様(上林様はケニアよりオンラインご登壇)
2. 包装材を用いた流通段階~消費段階での食料ロス削減の取組に関する取組の紹介
~青果物の劣化防止に関する技術と人材育成、開発途上国で事業展開をする時の心得~
日産スチール工業株式会社 東京営業所 営業部 国際部長 西本 英世様
流通過程でのエチレンガスやカビの発生は、青果物にとってのヒートショックが原因である。先進国では、収穫後の青果物を冷蔵して運搬するが、荷卸し時の急激な温度変化によりエチレンガスが大量に発生し、品質低下を招く。開発途上国では適切な運搬手段や冷蔵設備の不足により収穫物の大部分が腐敗する。この問題に対応するため、弊社は流通過程に関わる人々の教育と包装材Freshmamaの使用を推進している。
Freshmamaは、エチレンガスを分解し、カビの発芽を阻害するプラスチックフィルムであり、青果物の鮮度保持に効果的である。この技術により、青果物の代謝を抑え、食味の低下を遅らせることが可能である。また、カビの胞子が発芽できない純水を生成し、カビの抑制に寄与する。ハワイ島産パパイヤやカルフォルニアのノンケミカルマンダリンなどの成功事例が、その効果を証明している。
開発途上国での事業展開にあたっては、流通過程の改善だけでなく、マーケティング戦略や留意点も重要である。教育、法律・規制への適応、国際展示会への出展、政府機関とのコネクション構築が効果的であり、そのために複数の本邦企業が協力して農業分野での事業を展開し、農産物の廃棄率減少を目指している。例えば、ラオスでのニーズ調査や政府との協議を通じて、農産物の廃棄問題の解決に向けたビジネスモデルの構築を図っている。
要約すると、青果物の流通過程での品質低下問題に対して、弊社が開発した包装材Freshmamaが有効であり、開発途上国での事業展開には教育、法規制の適応、国際協力が不可欠である。これらの取り組みを通じて、農産物の廃棄率を減少させ、農家の収入向上に貢献していく。

日産スチール工業株式会社 西本様
第三部 国際機関の視点からのフォーラムのテーマに関するコメント・助言
国連食糧農業機関駐日連絡事務所 所長 日比 絵里子様
国連の農業関連機関には、緊急食糧支援を行う国連世界食糧計画(WFP)と食料生産や流通の持続可能性に焦点を当てる国連食糧農業機関(FAO)が存在する。WFPは非常に危機的な状況にある地域に食糧の緊急支援を行う組織である。一方、FAOは食料生産や流通の維持、復興のための支援を中心に行っている。FAOの現事務局長は、イノベーションや技術革新が食料問題解決に貢献すると主張している(注:FAO、WFPの他にローマを本部とする国際食料農業機関として開発途上国の小規模農家に低金利融資や補助金を通じて生計向上を支援する国際農業開発基金(IFAD)もあり、これら3つの機関はRome Based Agencies(RBA)として緊密に連携を取っている)。
食品ロス削減はFAOと国連環境計画(UNEP)がSDGsの一環として取り組んでいる。日本では食料廃棄(消費に適しているが小売、消費の段階で意識的に廃棄すること)にも食品ロスという単語を当てているが、FAOでは食料のロスと食料の廃棄を区別している。食料ロスとは生産段階から小売の手前までに発生する食料損失と定義している。この区別は管轄官庁が異なることによる。日本を事例とすると生産から小売りの段階は農林水産省が、廃棄の段階は環境省が主要な役割を担っている。世界全体で見ると、生産から小売りの手前までの損失率は13%、小売りから消費者の段階での廃棄率は17%である。
食料安全保障の現状は、農業・食料システムという広範な概念で捉えられており、サプライチェーンの各段階だけでなく、それを取り巻く様々な要因も考慮されている。食料の「Availability」、「Access」、「Utilization」、「Stability」の4つの側面が重要であり、特に「Access」、すなわち経済的アクセスが重要である。食料安全保障や世界の飢餓の改善は、根本的な貧困や不平等の改善なしには解消できない。
インフラの改善は、食料ロス・廃棄に限らずコミュニティ全体の改善に貢献するが、特に水資源の利用に関しては利権をめぐる争いや環境への影響も考慮すべきである。FAOは水資源の平和的な調整や紛争予防に取り組んでいる。
食料ロス・廃棄削減や食料安全保障への貢献は、現地の情報収集や国際的な基金との連携、政府や民間セクターとの提携を通じ、公的プログラムに製品や技術を組み込むことで、より大きな規模での認知と利用が可能になる。これには、長期的な視点と各国政府の中長期的なプログラムとの連携が鍵となる。

国連食糧農業機関駐日連絡事務所 日比様
フォーラムの総括及び閉会挨拶
JICA経済開発部部長 下川貴生
開発途上国における日々変化するニーズと、株式会社SPEC様や日産スチール工業株式会社の様ご紹介にあったような製品、技術とのマッチングを重視していく。例えばコールドチェーンへの依存を前提としない食料の品質保持技術は農家の生計向上に貢献する可能性が高く、農家の市場アクセス改善を含む普及活動に取り組んでいるJICAとして活用する機会を模索していく。
食料・農業システムの複雑性を理解し、開発途上国の政策パートナーとの対話を通じ、公的な議論に本フォーラムで紹介された技術等を組み込む提言はJICAの今後の方針の参考にする。











scroll