- トップページ
- 事業について
- JICAグローバル・アジェンダ
- 教育
- 専門家からのメッセージ
- 専門家から国際協力での仕事を目指す方へのメッセージ(西方専門員)
活動中に直面する壁とその克服方法
教育系の隊員が現地の授業を見ると、「授業が下手だな」、「もうちょっと工夫すれば子どもの学びが向上するのに」、などといった問題意識を必ず感じると思います。すると、現地の授業を日本と同じような授業に変えることが必要である、と漠然とイメージするのではないでしょうか。これは仕方ありません。普通人間は自分の経験したことを尺度として物事を見てしまいますので。しかし、現地の教師は隊員と全く異なる経験をしてきています。よって、隊員の思っていることを推測することはできません。ここで隊員は、言葉がうまく話せないこと、自分の思いが相手に伝わらないことでがっかりしがちです。
ではどうすればいいのでしょうか。まず、課題に対する認識と課題解決のための戦略が隊員と現地教師の間で共有されているか、について冷静に考える必要があります。例えば、隊員が「学びの改善」を課題として捉えている場合、現地の教師も同様の問題意識を持っているのかを確認することが重要です。口では子どもの学びの改善は重要だと言っていても、学びを改善するということがどういうことか、なぜそうしなければならないのか、という理解が十分にできていない場合もあります。そうするとこの時点で既に両者の思い描く具体的ゴールが合致していないので、どんな活動をしてもズレが生じてきてしまうのです。例えば、隊員がその手立てとして授業改善をしなければならない、と思っても現地の教師はそうは認識していない、ということも起こりうるのです。
具体的なゴールが共有されていないと分かった場合には、例えば簡単なテストを実施し、結果を一緒に分析することで「この結果を改善しよう」などといった具体的でわかりやすい目標を共有してみるのはどうでしょう。現地の教師は半信半疑かもしれませんが、やってみて具体的な成果が出れば、仕事の充実感につながり、もっとやってみようとなります。あまり大きな目標を設定せずに、達成可能性の高い目標設定(例えば基礎的・基本的な理解・技能の向上等)を行うことが重要です。ちょっと工夫したら結果が出た、という経験の積み重ねで達成感を持ってもらいましょう。スモールステップで、少しずつ実現可能なゴールを目指すことが重要かと思います。
活動を振り返り、改善するために
(注)例えば、以下の4つの観点から自分のやってきた活動を振り返ることもいいかもしれません。
- 「目的」がカウンターパートと共有されていますか?
-「自分」は何を目的として活動してきましたか?それはカウンターパートの考えと同じでしょうか?カウンターパートは子どもに何ができるようになってほしい、と思っていますか?また、カウンターパートの子どもへの願いは具体的なものでしょうか?(漠然としていると評価ができないので、手立てもぼけやすいです)具体化するために簡単なテスト等で子どもの学びの実態を共有して、一緒に考えることも一つの手かもしれません。 - 「課題」がカウンターパートと共有されていますか?
-「一生懸命活動しているのになかなかうまくいかない」と思っていませんか?カウンターパートと何が問題なのか?について共通認識がとれていますか?「こっちが言うことをなんでやらないんだ」と思っていませんか?そんな時は、もしかするとカウンターパートと問題意識のずれがあるかもしれません。生まれも育ちも異なる両者なので簡単に問題意識を共有させることの方が難しい、と考えましょう。現地には現地の事情があります。「自分」が現地の教師であったなら、「自分」が思い描いている活動ができるか?という視点でも振り返ってみましょう。カウンターパートと継続してコミュニケーションをとりながら、具体的に問題意識のすり合わせをしていく必要があります。 - 「戦略」がカウンターパートと共有されていますか?
-自分たちができる範囲内での解決策はなんでしょうか?そしてそれは妥当でしょうか?自分の思っていることが押し通すのではなく、カウンターパートの考えも尊重し、両者にとって納得感のある戦略を考えましょう。思い描いていることを100%実現させることは難しいので、「今よりもちょっとでもよくなるため」の戦略を一緒に考えましょう。 - 「活動」がカウンターパートと共有されていますか?
-例えば戦略が授業準備の充実だとしたら、いつ、誰がやるのでしょうか?その時間は取れますか?できる範囲で活動を組織できますか?カウンターパートは家に帰れば子育てが待っているかもしれません。あまり無理強いすると続きません。もしも難しい場合は、目的が高すぎるか、戦略が妥当ではないのかもしれません。その場合は、もう一度検討してみましょう。
活動を継続的に実施するための工夫
教師に無理をさせない範囲で活動することが重要です。例えば、授業後すぐに帰宅したい教師に、授業準備が重要だからと無理を言って残業してもらっても、その活動は長くは続きません。彼らの生活リズムの中で、無理のない範囲で活動しながら、その良さを分かってもらうように工夫しないといけません。例えば教材であれば、ニーズがあるものや、今使っているものよりも使いやすいものは、教師にもメリットがあるので使ってもらいやすくなります。どんな活動でも無理強いせず、自分が現地の教師だったら、という視点で考えるといいでしょう。
協力隊へのメッセージ
協力隊としてホンジュラスで活動した経験が、人生を大きく変えたと思っています。隊員時代に精一杯色々なことに挑戦したからこそ、今の自分がいます。そのため、現在活動している隊員の皆さんも、これから派遣される皆さんも、楽しく、精一杯活動するのが良いのではないでしょうか。成果うんぬんというよりも、人生の中の2年間という短い期間で、精一杯体当たりしてみてください。手加減しては自分の身になりません。2年間の過ごし方で今後の人生が変わると思います。応援しています!
西方憲広 国際協力専門員
1984年より新潟県で小学校教諭として勤務。1987年より青年海外協力隊(職種:小学校教諭)として中米ホンジュラス共和国で活動。1990年より再び新潟県で小学校教諭として勤務したあと、1996年から大学院で国際学を学ぶ(博士課程後期課程中退)。1998年より在ホンジュラス日本国大使館で専門調査員として政務(特に中米統合)・経済協力などを担当。2001年よりJICA長期専門家(基礎教育強化アドバイザー)として勤務(2005年より算数科指導力向上プロジェクトフェーズ1のチーフアドバイザー兼任)。2006年4月から算数科指導力向上プロジェクトフェーズ2(中米算数教育広域プロジェクト、通称"算数大好き"プロジェクト)チーフアドバイザー。2009年任期終了し帰国後、JICA国際協力専門員(人間開発部課題アドバイザー:教育)として勤務。アフリカ・アジア・中近東・中南米の教育案件策定、運営指導、評価、研修などにかかわる。2016年より再び小中等教育算数・数学指導力向上プロジェクト長期専門家(チーフアドバイザー)としてエルサルバドルに赴任。2019年、任期終了し帰国、現在に至る。
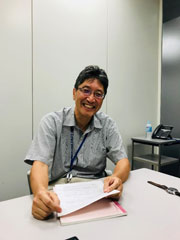











scroll