- トップページ
- 事業について
- 事業ごとの取り組み
- JICA開発大学院連携/JICAチェア
- JICA留学生の声
- 祖国への想い~日本で生きるアフガニスタンの子どもたちの教育支援~(2024年12月)
未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト(通称アフガンPEACE)は、未来のアフガニスタンの国造りを担う人材育成のため、アフガニスタンの行政官と大学教員を研修員として受け入れる技術協力プロジェクトとして2011年に開始されました(現在はフェーズ2を実施中です)。
PEACE生は来日後、本邦大学の修士課程・博士課程に在籍し、アフガニスタンの国造りに必要とされた工学、農学、教育、保健分野などの専門分野の研究に励んでいます。
しかし、2021年8月に発生したアフガニスタンの政変以降、前政権の行政官だった研修員は帰国困難となり、多くのPEACE生が再びアフガニスタンへ戻れるようになるまでの間日本に残ることを希望し、新たな挑戦をすることとなりました。
本シリーズでは、慣れない日本での就職活動を経て外国人材として日本で就労しているPEACE修了生と受け入れ先企業・団体へのインタビューをお届けします。
活躍の様子はもちろん、現在の悩みや今後の展望など、十人十色のJICA研修の「その後」を語ってくれました。
未来への架け橋・中核人材育成プロジェクトフェーズ2 | ODA見える化サイト
祖国への想い~日本で生きるアフガニスタンの子どもたちの教育支援~
インターンシップ実施報告(合同会社アイオライト・コンサルタンツ)
2024年9月2日から13日に渡り、PEACE研修員11バッチ Nayyer Farhad氏(ナイール・ファハド氏、以下、ナイール氏)とHaidari Khodadad氏(ハイダリ・フドーダッド氏、以下、ハイダリ氏)が合同会社アイオライト・コンサルタンツ(以下、アイオライト社)にてインターンシップを行いました。
同社は外国にルーツを持つ子どもたち(両親またはそのどちらか一方が、外国出身者である子ども)のための多言語数学動画教材の翻訳の協力者を求めていました。今年3月に実施されたJICAネットワーキングフェアをきっかけに、当該研修員との出会いに繋がり、今回のインターンシップ実施に至りました。
背景―外国にルーツを持つ子どもたちの学習のために

修了証書授与:ナイール氏、倉田氏
同社COO・シニアコンサルタント倉田聡子氏(以下、倉田氏)は、日本において外国にルーツを持つ子どもたちが、言語の壁や文化差により学業に困難を抱えながら、公立の夜間中学校1や、高校夜間部(以下、まとめて「夜間学校」)に在籍し学んでいるニュースを耳にし、彼らが直面している課題についての支援を検討されました。その結果、京都教育大学の黒田恭史教授(以下、黒田教授)の研究室が開発された、多言語数学動画教材を活用し、子どもたちが母語で数学を学べるような支援方法の検討を開始されました。
外国にルーツを持つ子どもたちは年々増加しており、日本の公立学校に多く在籍しています 2 。しかし、言葉の壁により授業内容が理解できないことから、徐々に学校から足が遠のいてしまう子どもたちが少なくなく、その中には在日アフガニスタン人の子どもたちも含まれていました。今回インターンシップに参加した研修員2名はJICAネットワーキングフェアでこのような現実を知り、日本で困難に直面している自国出身の子どもたちのために支援できることを考えました。

修了証書授与:ハイダリ氏、倉田氏
本インターンシップは、研修員自身が日本国内での就職に向け、日本企業での実務経験や知見を深めることも目的としました。この取り組みが将来的にアフガニスタンに住む子どもたちにとって有意義な学習機会提供の第一歩となり、ひいてはアフガニスタンの発展への貢献となることを期待し、多言語数学動画教材の翻訳業務と日本に在住するアフガニスタンを含めた外国にルーツを持つ子どもたちの現状分析を主としたインターンシップに参加する運びとなりました。
12023年の学齢相当の外国人の子どもの人数は前年度と比較して10.1%増加(文部科学省、報道発表
)。
2義務教育を修了しないまま学齢期を経過した人や、不登校など様々な事情により十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した人、外国籍の人などのために義務教育を保障する場(文部科学省、夜間中学設置応援資料
)。
インターンシップ実施にあたり
上記の多言語数学動画には、アフガニスタンの言語版は含まれていなかったため、インターンシップでは同国公用語の一つであるダリ語で動画の翻訳を試みました。インターンシップを行うにあたり、ナイール氏とハイダリ氏にインタビューしたところ、インターンシップに対する期待や参加の動機を以下のように語ってくれました。
ナイール氏:「今、住んでいる広島にも多くのアフガニスタン人が住んでいますが、中学生くらいの子どもにとっては日本語の習得が難しいと聞いています。今回、日本に住むアフガニスタン人の子どもたちの学校内での課題を知り、生徒たちの支援の良い機会になるなら、自分の時間を提供できることをとても嬉しく思い、参加することとしました。このインターンシップを通して、日本で生活をするアフガニスタンの子どもたちの課題を理解したいです。」
ハイダリ氏:「アフガニスタンで教育者としての経験があり、教育分野の業務に興味を持っています。言語は小学生くらいであれば習得が早いですが、中高生になると難しくなると推察します。日本に住むアフガニスタンの子どもたちとの交流を通して、課題を見出し、彼らの将来のために解決策を検討したいと考えています。また、関心のある分野の企業での経験は自分自身の成長にもつながると考え、このインターンシップに参加したいと思いました。」
活動内容と課題の発見
インターンシップは2部に分かれて行われました。前半1週間は在宅勤務で、本テーマの文献調査や、在日アフガン難民の教育支援を行う社会福祉法人にオンラインでの聞き取りを行うとともに、黒田教授から提供された中学1年生の数学の動画教材の一部をダリ語に翻訳し、説明の音声録音を行いました。また、アイオライト社グローバル人材推進マネージャーの岡田一葉氏の指導の下、日々、業務開始時と終了時に行われたオンラインミーティングで進捗報告や疑問点の確認を行ました。
翌週は生徒たちの受入先となっているフリースクールや夜間学校、数学動画教材への活用可能性のあるITツールを提供している教育IT企業を訪問しました。訪問先ではナイール氏、ハイダリ氏が滞日の背景等を含めた自己紹介を行い、交流を図りました。また、フリースクールや夜間学校での授業見学の後に行ったインタビューでは、生徒側、先生側のそれぞれの課題をヒアリングすることができました。
特に、生徒たちは日本語での授業内容を理解することに大きな課題を感じていると言います。これは、言語面の問題だけでなく、出身国での学習内容や個々の学習歴の違いにより生徒の学力が多様であることも理由にあると先生は話されていました。訪問した学校では、副担当教員による個別の支援も行っていますが、生徒たちはアプリの翻訳機能などを用いて授業内容の理解に努めるため、翻訳の精度によって個々の理解度に差が生じていることも分かりました。そこで、訪問時にダリ語に翻訳した数学動画教材のサンプルを紹介すると、生徒たちはぜひ使いたいと、大いに興味を示しました。インタビューを通して得た、教育現場の期待を踏まえて今後の支援策の検討を進めていくこととなりました。

作業を進めるナイール氏とハイダリ氏
最終日にはJICA東京で成果発表会が開催されました。同社CEOである大庭祐樹氏のオンラインでのご挨拶に始まり、本インターンシップに協力頂いた関係者も視聴する中、PEACE研修員による外国にルーツを持つ子どもたちの教育にかかる現状分析、教育課題に対する解決策の提案について発表がありました。
倉田氏から総評として「限られた期間に多くのタスクをこなす困難もあったかと思います。翻訳に関して想定していたよりも課題点が多くありましたが、よくがんばってくれました。日本でのアフガニスタンの子どもたちの現実を目の当たりにした経験を今後の糧にしてほしいです。」とナイール氏、ハイダリ氏への感謝とともにエールを送られ、2週間のインターンシップを終えました。
インターンシップを終えて
1) PEACE研修員からのコメント
ナイール氏:
「日本語の会話は滞日年数経過とともに慣れてはいくものの、読み書きの難しさや、異文化適応力の有無が課題につながることが多いことが明確になりました。母語での学習支援は不可欠であり、今回の我々の協力が子どもたちにとって有意義な支援であると実感しています。」
ハイダリ氏:
「この経験を通して、日本の学校に通うアフガニスタンの生徒たちが母語での勉強を熱望していることがわかりました。将来的にはアフガニスタンに住んでいる子どもたち、とりわけ女子学生たちの教育支援のために、ダリ語に翻訳された学習動画教材のオンライン教育プラットフォームの展開を期待したいです。」
2)関係者の反応
普段の学校生活では見せることのない、ナイール氏、ハイダリ氏とダリ語で生き生きと話すアフガニスタンの生徒たちの姿に、視察先の学校の先生方も驚かれていました。日本で就職し活躍を目指している両研修員の存在は、同生徒たちにとってよきロールモデルとなったのではないかと、倉田氏は語っています。
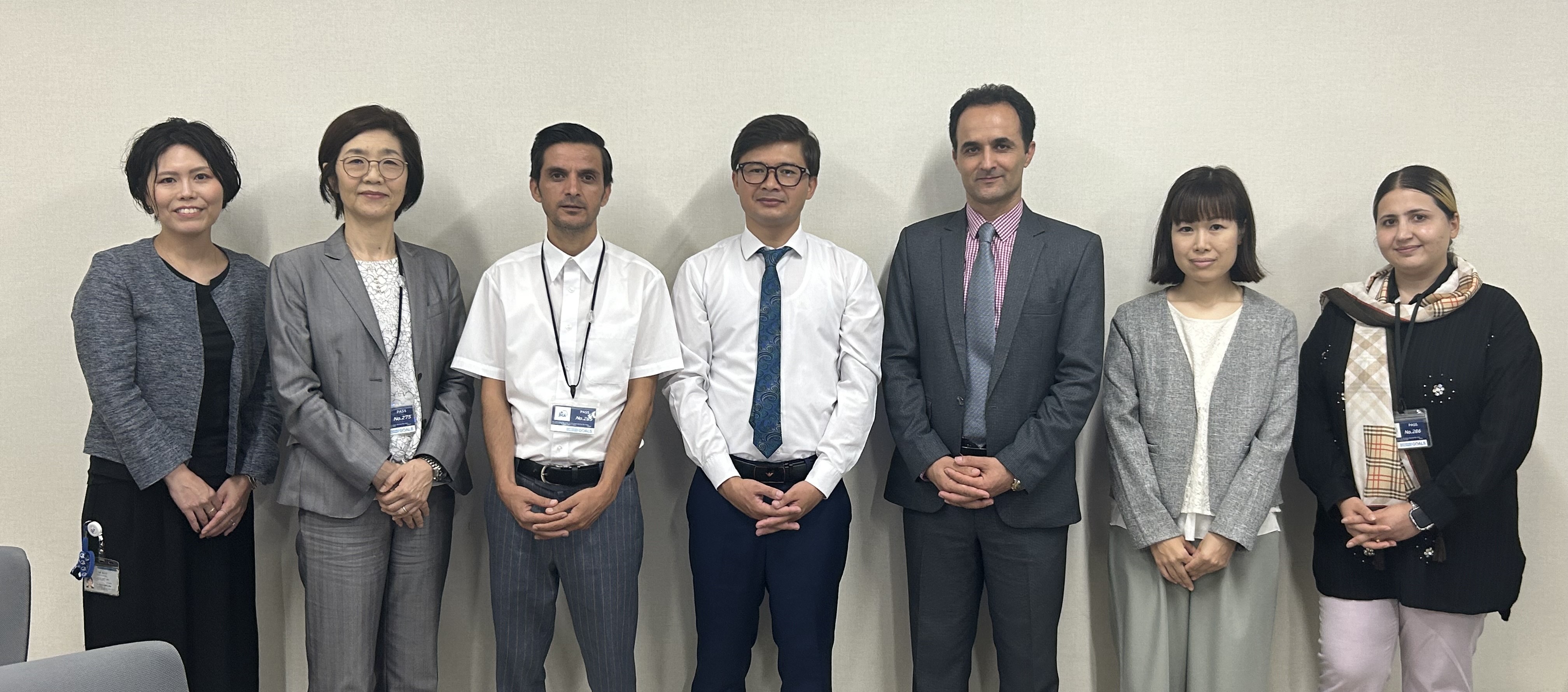
成果発表会後にハイダリ氏、ナイール氏を囲んで集合写真
最後に
このように、今回のインターンシップを通じ、PEACE研修員の活動が日本在住のアフガニスタンの子どもたちの学習の理解促進への一助になる可能性を見出すことができました。本来、PEACE事業は、母国に帰って日本で得た知見を国の発展に活用することを目的に実施していましたが、2021年の政変によりそれが叶わなくなってしまいました。祖国の状況がなかなか好転しない中、自身の無力さに悔しさを感じるPEACE研修員が多かったことは事実です。
しかし、日本国内に在住するアフガニスタンの子どもたちの懸命な姿を目の当たりにし、祖国の発展への想いを再確認することとなりました。今回のインターンは、PEACE研修員がアフガニスタンのために日本国内からもできることを真摯に考え、行動に移していくことの重要性を再認識する機会となりました。
【取材協力】
合同会社アイオライト・コンサルタンツ様
Nayyer Farhad氏 (PEACE修了生)
Haidari Khodadad氏(PEACE修了生)











scroll