【事例紹介】マダガスカルのカカオ農家と紡ぐ、持続可能な未来 - 株式会社明治(東京都)



2025.02.14
本記事では、カカオの調達・製品化のみならず、カカオ農家との関係構築、メイジ・カカオ・サポート(MCS)、さらにはその他の取り組みを通じて、ビジネスとコミュニティの持続性を高めたビジネスづくりのストーリーをお届けします。
2020年における、日本国内のチョコレート製品の年間消費量は、263,942トンにもなります(日本チョコレート・ココア協会調べ)。沢山の人に愛されているチョコレートの原料となるカカオ豆の多くは、アフリカや中南米、アジアの開発途上国で生産されていますが、農園の貧困、児童労働、森林伐採といった、深刻な社会問題を抱えている地域もあります。
株式会社明治は、2006年から中南米を中心に8か国でMCSの取り組みを通じて、カカオ農家を支援し、持続可能なチョコレート作りを推進しています。
メイジ・カカオ・サポート(MCS)(以下「MCS」)は、2006年に始まった、同社が行うカカオ農家支援活動です。この取り組みは、持続可能なカカオの生産を促進し、カカオ農家の生活向上と環境保護や児童労働防止など、社会課題の解決を目指しています。具体的には、カカオ農家の生活環境の改善、教育支援、カカオ技術向上のサポートを行っています。
同社は、2019年7月から2025年1月にかけて、9か国目となるマダガスカル共和国(以下「マダガスカル」)で、カカオを取り巻く社会課題の解決と高品質なカカオのバリューチェーンを構築すべく、JICAの「中小企業・SDGsビジネス支援事業(以下、JICA Biz)」を活用して、ビジネス化に取り組み、カカオ農家への技術指導や物資の支援により、MCSの輪を広げています。
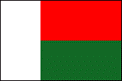


メイジ・カカオ・サポートのマークは、カカオ豆生産者・お客さま・明治の3者のつながりや未来に向かってよい循環を続けていくことを3つの手で表現し、カカオの実や花を支える様子を表現しています。
「カカオでつながる、すべてのひとを笑顔にしたい」という熱い想いでMCSを牽引される、株式会社明治のグローバルカカオ事業本部 副本部長 宇都宮さんと、研究本部 馬場さんに、JICAインターン生の井戸がお話をお伺いしました。
JICA: なぜ、MCSの9か国目にマダガスカルを選択されたのでしょうか?
宇都宮さん: チョコレート業界において、マダガスカルは「クリオロ種」という、世界全体の生産量のうち僅かであり、希少で高品質なカカオの生産地域として認識されています。マダガスカル産カカオ豆は、その優れた品質が評価されている一方で、日本への輸出はごく僅かであり、さらには、マダガスカル産カカオを使用したチョコレートも、日本ではあまり出回っていませんでした。このように、マダガスカルとの接点が少ないことから、企業が直接アプローチするのが難しい状況でした。そのため、ベース作りのために、JICAの力をお借りしました。
JICA: 接点が少ないマダガスカルでの事業展開において、どのような点にご苦労されましたか?
宇都宮さん: マダガスカルでは、カカオ栽培に好条件なサンビラノ川の下流地域のほとんどが大手プランテーション等に占有されており、新規参入が難しい状況でした。そこで、道路が未舗装といった、アクセスが悪い上流域での挑戦となり、往復10時間を超える移動といった困難にも直面しましたが、現地のコミュニティとの繋がりを活用することで、3つのエリアコミュニティとパートナーシップを結び、カカオ生産を進めることができました。
馬場さん: 一方で、マダガスカルではコミュニティ間での情報交換が少なく、カカオの作り方がバラバラで品質が安定しないといった課題がありました。今回、JICAのご支援で現地に直接赴き、明治独自の技術指導を行えたことで、品質の向上と安定を実現できています。
JICA: マダガスカルでの現地調査を通じてどのようなことを感じられましたか?
馬場さん: カカオ豆の契約時期と収穫時期にはタイムラグが存在するため、カカオ農家は価格の変動により大きな影響を受けてしまいます。例えば、農家と輸出業者は電話で口頭契約を結ぶことが多く、書面で契約内容が明記されないことで、輸出業者に有利な条件で買い取りが行われる可能性があります。カカオ産業のサステナビリティの観点から、一部だけが利潤を得るのではなく、カカオに関わる全ての人が公正にメリットを得られるようにとの想いから、弊社ではカカオ農家と技術指導等を通じて信頼関係を構築した上で、輸出業者や商社とも協力して高品質なカカオ豆を適正な価格で買い取る取り組みを行っています。
宇都宮さん: また、マダガスカルの住民のほとんどが1日1ドル以下で生活しているという現実を目の当たりにし、チョコレート事業を通じた支援だけでは、現地の環境改善には全く十分ではないと危機感を覚えました。カカオをチョコレートにする企業は世界中にあることから、チョコレート事業以外での取り組みにも注力し、マダガスカルの貧困改善に繋がるよう支援を加速しています。例えば、カカオの未使用部位を有効活用し、1つのカカオから複数の製品を生み出し、この取り組みによって得た収益をカカオ産地に還元しています。具体的には、カカオ由来の美容保湿成分「カカオセラミド」を世界で初めて素材化し、化粧品への使用や商品化 を行う「meiji CACAO BEauty Project」や、チョコレート製造の途中で取り除かれるカカオハスク(カカオ豆の種皮 )から、「生分解性カカオバイオプラスチック」を開発するバイオプラスチック事業などを進めており、これらの技術をマダガスカルにも導入できる可能性を検討しています。
JICA: 御社が開発途上国へ進出される際にどのような点を意識されていますか?
宇都宮さん: 弊社がビジネスを継続できているのは、連携させていただいている国々の農家の皆様のおかげであり、彼らがいなければ、私たちの存在意義自体が危ぶまれてしまうというのが、社内での共通認識です。サステナビリティが声高に叫ばれる前から、弊社では農家との連携を強化し、共にものづくりを行い、その成果を適正価格で購入するなどの支援を通じて、持続可能なカカオ作りを推進してきました。この取り組みは、単なるビジネスの枠を超えて、農家と共に歩む未来を築くための重要な基盤となっています。

協力農家と調査メンバー

JICA: JICA Bizを活用されたことで、御社の事業展開にどのような効果がありましたか?
宇都宮さん: 接点を持つのが難しかったマダガスカルで、JICAの力をお借りして関係性のベースを築くことができました。明治のカカオの歴史は100年以上にわたり、アフリカのガーナと南米との関係もほぼ100年に及びます。そのため、これまでのMCSにおいては、現地に直接赴き指導できる基盤が整っていました。ですから、未踏の地であったマダガスカルにおいて、農家一軒一軒との顔が見える取引が実現し始めたことは、JICAのネットワークを活用できたからこその大きな成果だと感じています。生産者との密接な関係構築が可能になったことで、既に生産されたカカオを購入するのとは一線を画し、大手プランテーションでの明治独自豆生産が実現しました。
新規ビジネスや市場開拓の第一歩を踏み出すために、JICAのご支援を得ながら、我々民間企業は進出国にとって有益な活動を全力で考え続けていく所存です。
JICA: JICA事業が、御社の調査のお役に立つことができ、有難く存じます。
宇都宮さん: ありがとうございます。現地での高い知名度のJICAの事業ということで、相手との打ち合わせや会話がスムーズに進み、良い反応を得ることができました。また、JICAマダガスカル事務所からのアプローチにより、役所や行政機関への訪問や、やり取りがしやすくなるなど多大なサポートをいただきました。品質評価のために大量のカカオサンプルを日本に輸出する必要があった際、JICAマダガスカル事務所所長や商社の協力を得て、産業省大臣との面談を実施しました。この面談を通じて、サンプルが商業目的ではなく、将来的にマダガスカル産カカオの品質向上を目指す試験サンプルであることをご理解いただいた結果、大臣の協力もあり、スムーズに輸出をすることができました。
また、現地で雇用していた傭人についても、JICAの別のプロジェクトパートナーであったため、安心して調査を委託できました。コロナ禍で現地渡航が制限されていた際も、彼との連携により、リモートでプロジェクトを順調に進めることができました。

乾燥中のカカオ豆品質確認中の宇都宮さんと馬場さん
JICA: マダガスカル産カカオを使用したチョコレートの商品化に関しまして、今後のご計画を伺えますでしょうか?
宇都宮さん: 現在2026年の商品化を目標に取り組んでいます。本事業を通して、マダガスカルは、これまで関係を築いてきた国々と比較しても、最貧国に近しい状況であることを実感しました。だからこそ、まずは2026年にマダガスカル産カカオを使用したチョコレートを商品化し、日本のお客様に確実にお届けするという目標のもと、弊社と共にカカオづくりを進めることで、農家の方々にとっても生活の向上に繋がるよう、カカオの品質向上や多角化に貢献できればと考えています。
JICA: 先ほどお話にございました、MCSに留まらない、「meiji CACAO BEauty Project」や「生分解性カカオバイオプラスチック」に代表されるサステナブルな取り組みなども通して、どのような社会の実現を目指していらっしゃるのでしょうか?
宇都宮さん: 我々はこれまで、カカオを通じて世界中との繋がりを築いてきた企業として、今後もカカオを活用しながらSDGsに取り組んで参りたいと考えています。現在、カカオに含まれる「セラミド」という美容成分を活用したプロジェクトを進めていますが、この成分はマダガスカルで消費が多いお米のイネにも含まれている可能性があります。イネはカカオと比較して、セラミドが含まれる葉や根などの廃棄部分が多いため、そのセラミドを上手に活用することで、回収量の向上と資源の有効活用が期待できます。カカオだけでなく、イネ等のマダガスカルに関わる植物全体を見渡し、持続可能な形で効果的に活用していきたいと考えています。
JICA: では最後に、JICA Bizの利用を検討されている企業様へ、メッセージをお願いします。
宇都宮さん: マダガスカルのように、非常に魅力的でありながらもこれまで接点が少なかった国にアプローチする際、JICAと共に現地の環境改善をはじめとする支援を行いながら、着実かつ迅速に新たなビジネスを創出できたことは、私たちにとって大きな成果だと感じています。

インタビューに応じる宇都宮さんと馬場さん
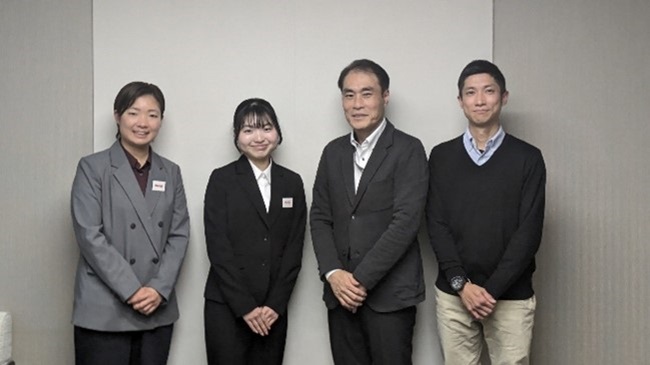
左からJICA信岡(JICA Biz本案件担当)、井戸(今回取材担当)、(株)明治宇都宮さん、馬場さん
株式会社明治のMCSの取り組みを通じて、日本企業が、SDGsに貢献しながら開発途上国の社会課題解決への糸口となるダイナミズムを感じることができました。これは、民間連携事業ならではの強みであると実感しています。さらに、同社は2020年に設立されJICAが事務局を務める「サステナブル・カカオ・プラットフォーム」の運営委員会に参画され、同プラットフォームを通じて、開発途上国における社会的・経済的・環境的に持続可能なカカオ産業の実現を目指し、多様な関係者と協働しながらカカオ産業の課題解決に貢献されています。カカオに限らず、私たちが日々食べているものや使用している製品のトレーサビリティが確立されることによって、豊かで持続可能な未来に一歩ずつ近づいていけるということを、改めて学ばせていただきました。
インタビューにご協力いただいた株式会社明治の皆さま、貴重なお話を誠にありがとうございました。今後の益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
(民間連携事業部インターン 井戸綾星)
scroll