- トップページ
- 事業について
- 事業ごとの取り組み
- 技術協力
- JICA-Netマルチメディア教材 利活用事例
- JICA関西 廃棄物、水資源分野の課題別研修で活用-各場面、各人のニーズに合った学習-
課題別研修で10年以上活用
JICA関西では、JICA課題別研修「都市固形廃棄物管理の実務(A), (B)」「都市上水道維持管理(浄水・水質)(B)」で、廃棄物及び水資源分野のJICA-Netマルチメディア教材を多数活用しています。廃棄物コースについては、前身にあたる案件を含めると10年以上使用しているため、具体的な人数は不明ですが、視聴を推奨した対象の研修員の人数は100名以上と思われます。
JICA-Netマルチメディア教材を知ったきっかけは、JICA-Netライブラリーが行っている活用セミナーでした。それまでは、既存(公的機関や企業が公開する動画等)資料を利用していたのですが、ビジュアル教材が限られている、最新のものが少ない、英語版が無い、著作権上のハードルが高いなど、研修の公式教材として指定するには難しいものが多いと感じていました。その点、JICA-Netマルチメディア教材は質が比較的高くメッセージ性があり、よくまとまっていると感じ、採用しました。
活用教材の一部をご紹介

マレーシアでは「全国リサイクル情報システム」の構築、3R活動・環境教育の導入が行われました。
課題別研修で使用している廃棄物及び水資源分野の教材の一部をご紹介します。
「日本の経験・技術が途上国で活用された事例」では、スーダン、パレスチナ、エルサルバドル、バングラデシュ、マレーシア、ベトナム等で、廃棄物分野での日本の経験や技術を取り入れた海外の事例を紹介しています。
こちらの教材は、「日本の自治体の取組み」「日本の廃棄物管理の経験の概要-戦後・高度成長期からの発展の歴史-」と合わせ、日本の廃棄物管理の経験を現在の途上国での課題解決に役立てていただくことを目的としたシリーズとして、2023年に作成されたばかりの教材です。
「How has Japan Achieved Universal Access to Safe Drinking Water? — Japan’s Infrastructure Development: the Case in Urban Water Supply Systems」では、東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授及び同大学付属水環境工学研究センター長の滝沢智氏をお迎えし、日本において安全で広範囲な給水を実現した歴史を前半で振り返り、後半では、特に近代化の過程においてどのように日本人技術者を育成したかについて、講義形式で解説しています。
他にも、「緩速ろ過法 ~安全でおいしい水を求めて~」「生ごみコンポスト化の推進によるごみ減量のすすめ」「高倉式コンポストの技術」「衛生埋立への道-福岡方式-(準好気性埋立技術)」等、定番として長く使用している教材もあります。
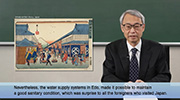
講義形式で日本の給水の経験と知見について解説します。
講義でカバーしきれなかった部分を教材で補完
コロナ禍前には、対面の研修で教材のDVDを研修員に配布していました。現在は、遠隔研修やハイブリッド研修でYouTubeのリンクやJICA-VANからの視聴方法を研修員に案内しています。
研修員の専門や経験などが多様であることから、集団での講義や視察でカバーしきれなかった部分を各人のニーズに基づき自習してもらう、質疑や補足説明の際、講師が動画の一部を見せて理解を促進するといった形で教材を活用しています。
教材のメリットとしては、画像、動画が豊富に使われており分かりやすい、JICAの当該分野に対する認識や協力方針に基づいて作成されているため、外部の専門家が作成した既存教材に対して必要になるような補足説明が不要で、省力化ができる等を実感しています。
また、研修員の都合、背景等に合わせていつでも視聴可能で、特に公開の教材については、帰国後の普及に活用できる等、状況に合わせたさまざまな使い方が可能です。
このようなメリットを考慮すると、将来的には、JICAチェアなどを通じて、長期研修員やそのスーパーバイザーにもご紹介できるのではないかと思います。
JICA-Netマルチメディア教材は、様々な人、いろいろな場面で柔軟に使うことができますので、今後も広く活用していきたいと思います。
JICA関西 研修業務課 環境コース担当
このページで紹介している教材
日本の経験・技術が途上国で活用された事例
この動画では、JICAが行ってきたプロジェクトであるスーダンでの定時定点収集の取り組み、パレスチナでの広域処理の導入、エルサルバドルでの衛生埋立処分場の導入・維持管理、バングラデシュでの住民参加型廃棄物管理体制の構築、マレーシアでのデータ管理システムの構築、3R活動・環境教育の導入、ベトナムでの多くの関係者を巻き込んだ3R活動推進の取り組みについて紹介します。
How has Japan Achieved Universal Access to Safe Drinking Water? — Japan’s Infrastructure Development: the Case in Urban Water Supply Systems
In this video, we will present Japanese development experience in the water supply sector.
This lecture answers two questions.
The first question is, why was it possible to extend the water supply coverage to 98% of the total population in Japan, and why was it possible to supply safe drinking water 24 hours a day, every day?
The second question is, what are the reasons that the capabilities of Japanese engineers developed successfully through learning foreign technologies during the process of modernization?
This video series provides a comprehensive summary, by development issue, according to the lineup of JICA’s cooperation strategy called the “JICA Global Agenda.”
These video lecture shall be widely disseminated to JICA chair participants, trainees, JICA staff, and other interested parties. To have them learn about the process by which Japan has solved development issues.











scroll