- トップページ
- アフリカひろば
- アフリカビジネス
- アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ
- ABEイニシアティブの「いまとこれから」について官・学・民で意見交換しました
2024年7月31日にアフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ(ABEイニシアティブ、以下ABEイニ)の進捗報告会を開催しました。外務省をはじめとする省庁や横浜市、日本経済団体連合会(経団連)、ABEイニ生受入大学関係者、インターンシップ受入企業など、官・学・民から約100名にオンラインと対面で参加していただきました。
「6年間で3000人の育成」を達成!
2019年のTICAD7で打ち出された「ABE3.0」は人選の戦略性強化、プログラム内容の拡充・強化、ABEイニシアティブ研修員以外の一部プログラムへ の参加拡大を主な柱とするものです。本報告会の目的は、「ABE3.0」の成果報告と関係者からの意見聴取に加えて、関係者間の意見交換とネットワーキングでした。
報告会のなかで、JICA側と海外産業人材育成協会(AOTS)側からそれぞれ達成状況が報告されました。経済界からのニーズに基づいて、AOTSには経済分野における研修プログラムの一部をご協力いただいております。また、ABE生を多く受け入れている大学代表として国際大学、ABE生をインターンとして受け入れている企業代表としてアセンティアホールディングスからそれぞれ活動報告がありました。

JICA側から人材の育成状況やABEイニ修了生の活躍、経済界からの評価などが紹介され、ABE3.0における協力パートナーの拡大があったことも報告されました。また、ABE3.0からABEイニへの活動を強化したAOTSより、実績例3つを紹介していただきました。実績例の一つであるABEイニ生のネットワークを生かしたオンラインセミナーはABEイニ生からの要望に応えたものでした。
それぞれの報告のなかで、「6年間で3000名を育成する」コミットメント達成されたことが発表され、JICA側1200名とAOTS2549名を合わせた計3749名が育成されたことが報告されました。
多様な学園環境の創生に一役を買う
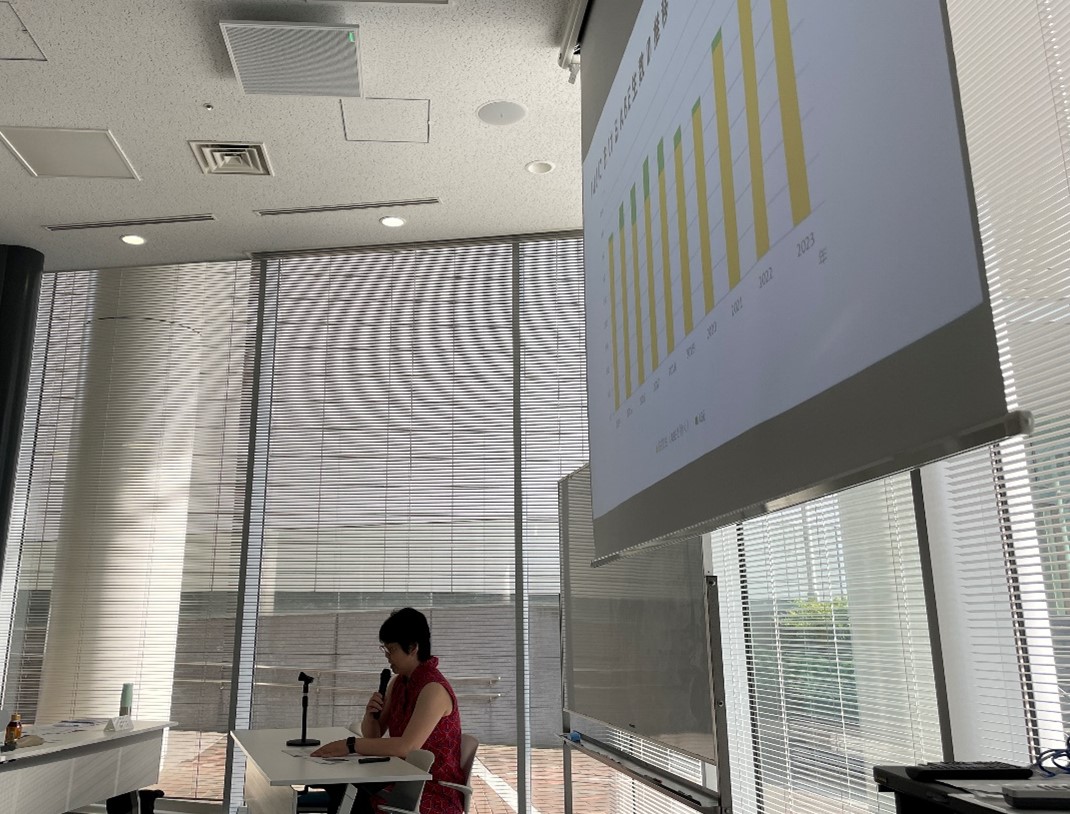
これまで42か国390人のABEイニ生を受け入れてきた国際大学の報告では、ABEイニ生の受入で学内が多様になり、学内・外での活動に活気が出るようになったと湯田ミノリ室長より発表していただきました。他方、学力や日本語運用能力、修了後のキャリアパスなどの改善が求められる部分もありました。
多様な学園環境の形成に一役を買うABEイニ生を受け入れいきたい旨が共有され、今後も積極的な受け入れていくことに加えて、アフリカ行政官を対象とする研修の開発や地域コミュニティとの共存を目指していくことが紹介されました。
ABE生との共創で日本の中小企業に新たなチャンス

これまで多くのインターン生を受け入れ、またABEイニ修了生とのビジネス連携も実施しているアセンティアホールディングスからは、松本信彦取締役より、モザンビーク修了生の事例を用いて、ABEイニ生との連携やインターン受入のメリットを紹介していただきました。ABEイニ生の受入によって、日本の中小企業にも新たなビジネスチャンスが生まれるという、松本氏の力強い言葉に、会場からは大きな拍手が送られました。
これからのABEイニシアティブ
最後に、JICA側からTICAD9に向けた新たな取り組みを紹介しました。そのなかで、「日アフリカ間の人材交流を活性化」を目的とした日本語研修の強化とインターンの強化を2大柱とする方針が示され、JICA海外協力隊との連携も含めた案も紹介しました。
その後の質疑応答では、多くの参加者からABEイニが持つ良い点が多く挙げられ、ABEイニ生の就職と起業に対する強い意欲があることも評価されました。他方でそれぞれの現場担当者が抱える課題感も会場で共有され、日本語に対する学習意欲や他機関との連携についてなど、今後の更なる展開に向けて多くの質問・意見が活発に交わされました。
今回の進捗報告会を通じて、ABEイニシアティブが官・学・民の3者から高い評価を得ていることを確認できたことに加えて、ABEイニ生一人一人が多方面で日本とアフリカに大きなインパクトを与えていることも見ることができました。一方で、官・学・民の3者から高い期待が寄せられていることもあり、よりよいプログラムとするために多くの課題があることも確認することができました。JICAは来年のTICAD9に向けて、更なるアップデートで魅力あるABEイニシアティブへとするために引き続き尽力していきます。












scroll