【3/8は国際女性デー】自分らしく輝くJICA職員のアナザーストーリー ~世界1位に輝いた秘訣とは!?~
2025.03.07

毎年3月8日は、「国際女性デー」(International Women's Day)です。
1975年の国連総会で正式に制定されて以来、女性の平等な社会参加や尊厳を考え、行動をする大切な日とされています。国や地域によって意味や祝い方は異なりますが、世界各地で様々な催しが行われ、日本でも、チャリティランや音楽祭、フォーラムなどの啓発イベントが各地で開催されています。
女性が自分らしく輝くこの日に合わせて、今回はJICA東京で勤務する職員、市民参加協力グループの湯浅あゆ美さんのストーリーを紹介します。
JICAに入構後、ハーバードケネディ行政大学院への留学、内閣府男女共同参画局での勤務、OECD(経済協力開発機構)局次長としての国際的な経験を経て、現在はJICAの管理職として勤務する湯浅さん。仕事では管理職、家庭では中学生の子どもを持つ母として日々過ごされています。
そんな湯浅さんは、実は、あるスポーツで世界ランク一位というもう一つの顔を持っています!
以下は、湯浅さんがJICA社内報に寄稿した記事です。ある地域での講演をきっかけに、関係者の方から『この記事をぜひ県内、市内で共有したい』という声が寄せられました。そこで、国際女性デーに合わせ、広くメッセージを届けるため公開することにしました。
(記事の後には、湯浅さんからのメッセージがありますので、是非最後までお読みください!)
私は子どもの頃から運動が大好きで社会人になってからもスポーツを続けてきました。そんな私が40代で出会ったのが 「クロスミントン」 。バドミントン、テニス、スカッシュを融合させた新しいラケットスポーツで、2002年にドイツで誕生し、現在は20か国以上で楽しまれています。

これまで獲得してきたメダルたち(一部)大人になってこんなにメダルをもらえるとは思っていませんでした。
クロスミントンを始めた翌年、私はポーランドで開催された世界選手権に遠征しました。日本中のクロスミントン愛好者が集まり、「日本にメダルを持ち帰ろう!」と励まし合いながら挑んだ大会は、多世代が共に過ごす修学旅行のようでした。
これまでに世界選手権に4度、アジア選手権に2度出場し、国内外の仲間たちは私にとっての「サードプレイス」になりました。仕事や家庭とは異なる場所で、純粋にスポーツに打ち込む時間と仲間の存在が、公私ともに大きな刺激となっていたのです。
皆でユニフォームを揃えました
一つでも多くメダルを多く! と全員で応援
2022年、初めて日本人が世界選手権で金メダル!皆で歓喜
クロスミントンを始めたのは、仕事と家庭の狭間で忙殺されていたいわゆる「中年の危機」の頃。サードプレイスでマインドフルにスポーツに熱中することで、「今ここ」に意識が集中し、心がスッキリしていく感覚があり、気づけば、仕事の意欲や生産性も向上していました。
国際機関OECD局次長の公募ポストを受験し、武者修行することになったパリでの3年間は、「なんで私がこんなハイランクなポストに?!」と多大なプレッシャーを感じながらも、自信満々なふりを演じて各国と交渉をこなす日々。限界を感じたときにはクロスミントンを求め、スイス、スロバキア、チェコ、スロベニア、ドイツと単身遠征しました。
移動中は孤独でしたが、大会会場には仲間がいますし、選手の自宅に泊めてもらうこともありました。そんな交流を通じてすべての大会で入賞し、アスリートとしての成果を出すことで自己効力感を維持し、仕事に臨むことができ、OECDでの任務もやり遂げました。
3位入賞!頑張りました
スイスオープン優勝で地元紙に名前入りで取り上げられました
スロベニア大会で仲良しドイツ人選手と再会
そんな中、「一度くらい世界一を目指してもいいのでは?」と思い立ちました。どうせなら世界一を狙おう。
そこからは戦略的にクロスミントンと向き合い、世界一のチャンスがある「シニア(40代)女子ダブルス」に挑戦。アジア選手権優勝、世界選手権銀メダルなどの実績を積み重ねた結果、2023年3月30日(奇しくも母の誕生日)、ついに世界ランキング1位を達成!
現行システムで記録が残る185週のうち、現時点で最長の82週(44%)を世界1位として過ごしました。
まさに、サードプレイスでマインドフルに自己効力感を高め続けていたら、世界一になりました。
決勝戦はファイナルセット僅差で負けて銀メダル
世界選手権表彰式が地元紙に
国際大会の表彰式では国旗を持って臨みます
一方で、自分の競技に時間を費やすことへの罪悪感も。娘と過ごせる時間を削ってまでスポーツを続けるべきかーー。でも、「元気も自信もない状態の私より、スポーツを通じてエネルギッシュで自己効力感の高い状態の私といる方が、娘にとっても良いのでは?」と思うように。
そして、大会を家族イベントにすることにしました。海外選手が日本に遠征に来る際には、娘も一緒に彼らと都内観光や登山を楽しみ、知床半島まで足を延ばしたこともあります。娘(現在中学3年生)は、私の試合応援も海外選手との交流も良い経験だったと振り返ってくれています。

当時世界最強男子のパトリック選手(独)とは知床半島にも!

来日したハンガリー選手団と

ハンガリー選手団とスロベニアで再会!
直近の目標は、世界選手権での悲願の金メダル。長期的には、70代カテゴリー(現時点で最年長カテゴリー)でも動ける身体を維持すること。また、ライフワークとしてスポーツを通じた多文化・多世代交流や地域活性化にも取り組んでいきたいと考えています。
最近、クロスミントンの縁でつながった仲間と一緒に「ピックルボール」を通じた多文化・多世代交流・地域活性化の取り組みを(小さいながら)スタートさせました。
ワクワクする挑戦は、まだまだ続きます。
「サードプレイス」で自分の思いや仲間との関係を大切にされたことで、自己効力感を高め、仕事や家庭にも好循環が生まれたという、湯浅さんのストーリーでした。今でこそ、率直にご自身の経験や考えを発信されていますが、湯浅さん自身「女性とは」「母とは」の「あるべき像」に縛られ、自己批判を繰り返していた時期があったそうです。
最後に、それらを振り切ることができたきっかけや、皆さんへのメッセージを聞いてみました。
「子どもの頃、母の言葉や態度から、多くのことを我慢しながら私を育ててくれていると感じていました。感謝する一方で、『私のせいで母はやりたいことが出来ないのでは』と悩むこともありました。
母のことが大好きだからこそ、ストレスで辛そうな姿を見て、その一端が自分のせいなのだと感じ、子ども心にも悲しかったのを覚えています。
子どもは親にハッピーで居て欲しいと思うものですよね。なので、自分の子どもには、そう感じさせないよう、自分は『ハッピーマザー』でいる姿を見せたいと思うようになりました。
もちろん、親になるとそれまで通りの生活は難しくなりますが、少しずつでも自分のやりたいことを続けようと決め、周囲にもその考えを伝えました。そのようななかで、徐々にスポーツの再チャレンジも始めました。
でも、一般的な母親像と異なることへの罪悪感や『これでいいのかな?』という迷いや不安もたくさんありましたし、自分自身が抱えている『あるべき母親像』と比べてしまい、自己批判することも多くありました。
しかしながら、海外に住んだり、事例を調べるなかで、海外の子育てはもう少し『リラックス』していることを知って考えが変わり始めました。小さい子どもがいても預けて夜に定期的に出かける夫婦や、ヨガやスポーツなど趣味も続けている母親たちの実例を目の当たりにするなか、自分の『母親像』は固定観念だったのだと気づきました。
ただ、自分の経験は役に立たないのでは、と経験共有を避けていました。私は実家すぐ近くに住み、一番忙しかった頃は保育園のお迎え、夕飯、お風呂もお願いするなど実家に頼りっぱなしなので、「両立」には当たらないんじゃないか、私の経験は役に立たないのでは、と引きこもっていました。でも、女性職員との雑談で自分の状況を共有したら、『そんなに頼ってもいいんだ!』と目からウロコの様子をみて、もしかしたら私の経験も役に立つのかもと思い、『こんな例もある』と伝えていこうと思うようになりました。それ以降、勇気を出して、企業や大学で経験談を話しています。
たとえば、15年前に経験した子連れ海外単身赴任(一時期は子どもを日本に残しての単身赴任)については、当時、周囲に似た例がなく孤独でした。でも実は、私自身、その決断ができたのは、大学院留学時代に小さなお子さんを日本において単身留学していた女性の存在があったらだと思い出し、JICAのリクルートパンフレットで特集してもらった際には、「こういう例もあるんだよー」と私の例を率直に共有しました。
私の経験がすべての人に当てはまるわけではありませんし、特殊な例かもしれません。でも、多様な例があるのだと共有していくことで、『女性とは』『母とは』『〇〇とは』といった固定観念から解放される一助になればと思います。
一人ひとりが『〇〇とはこうあるべき』という固定観念から解放されることで、『誰もが自分らしく生きられる社会』につながるのではないでしょうか。」
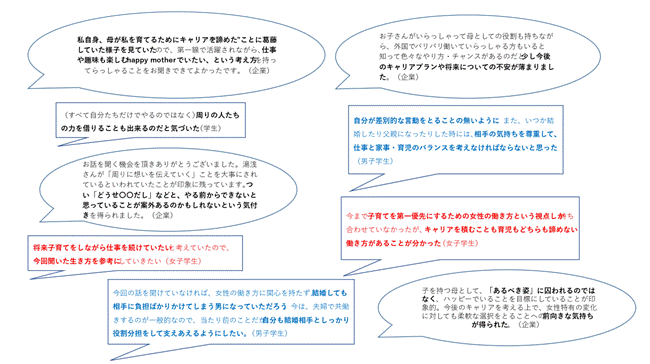
企業や大学で自分の体験や想いを共有した際に、参加者からもらった言葉たちは、湯浅さんにとって宝物だそうです。

2010~2013年、育休明けに子連れ単身赴任をした体験を、学生向けJICAリクルート雑誌にて共有
湯浅さんの経験を悩みも含めて共有してもらったことで、皆さんも「こんな例もあるんだ!」と参考になったのではないでしょうか。
3月8日、国際女性デーをきっかけに、それぞれが自分らしく輝く生き方について考え、行動してみませんか?
scroll