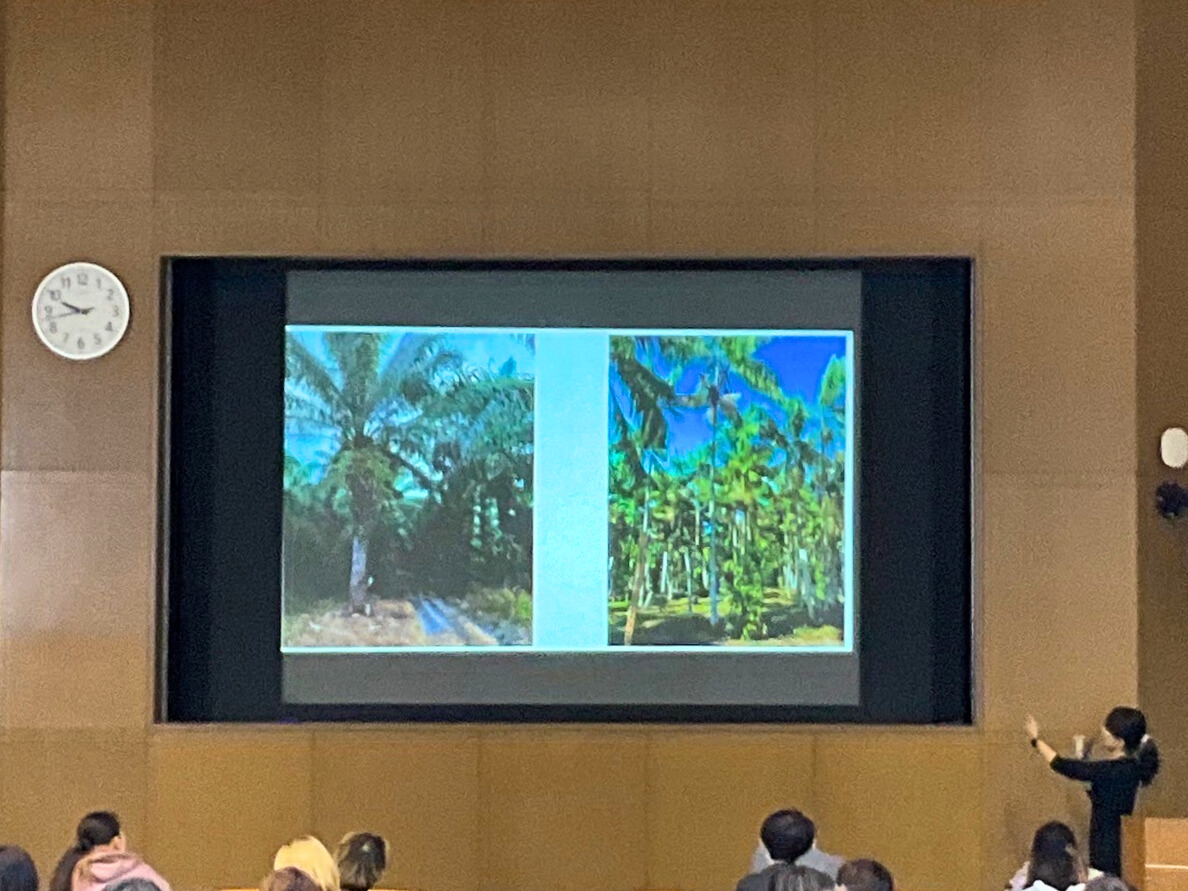- トップページ
- 日本国内での取り組み
- JICA横浜
- 事業の紹介
- 世界を身近に感じよう! 開発教育支援事業
- 教師海外研修
- 【教師海外研修】実践授業レポート from 公文国際学園 (菊池史織教諭)
実践授業とは…
実践授業とは、JICA教師海外研修に参加した先生方に、研修で得た経験を活用した授業プログラムを作っていただき、学校現場で実践いただくものです。
菊池先生のレポート
私は、生徒たちが将来、多様な他者とともに平和な世界をつくっていくことができるように、種まきをしたいと考えています。そのために、自分と相手を大切にできる生徒を育てたいです。英語の授業においては、相手に伝えるためにはどうすればいいのか、相手は何を伝えようとしているのか、といった相手意識を大切にした授業展開を目指します。
(1)本時の目標
10月10日、高2生徒約160人を対象に一斉講義スタイルで授業を行いました。
テーマは「diversity 多文化共生」。教師海外研修に参加したメンバーで考えたワークを取り入れ、ペアやグループで考え話し合うスタイルで1時間、正解のない問と向き合いました。
(2)揺さぶりたい価値観
自分が無意識に持つ固定概念について、自覚をする。社会における経済格差に向き合い、自分たちがすべきことについて考える。一人一人、個々に異なり、「ひとくくりにしない」ことの重要性について理解する。
(3)展開
◎、⚪︎、●、◻︎などのイラスト
研修の中で提示されたものです。特定のイメージや言葉があるわけではないのですが、シンプルにダイレクトに「分ける、混ざる・混ぜること」について考えることができます。
問いを設定せずに感じることについて意見を伝えあうことで、様々な価値観を共有することにつながったと思います。
平等、公平、公正についてのイラスト
公共の授業にて既に目にしていたため、それぞれのイラストについてどのように考えるかを言語化することがスムーズにできました。「理想と現実」が国により、状況によりことなることは理解できているものの、自分たちはどこに向かうべきなのか明確な意見を述べることができない状況をもどかしく思っていることが伝わりました。
日本だけではなく世界の未来を担う一員であることを自覚し、アクションを起こさなければいけないという自覚を促しました。
ブラジルで撮影した写真
「多文化共生」があたりまえの日常として生活や教室にあることを話しました。写真と共に話を聞くことでよりリアリティーが増したという声を聞きました。特に渋滞の中ものを売る親子や、街の中に溢れているテント、警備にあたる警察官の写真には衝撃を受けている様子でした。
(4)生徒の様子
「異質の他者を認める」という建学の精神を生徒自身も大切にしているため、多文化共生について関心がもともと高いです。自分以外の国籍・文化に対しての理解だけではなく、ジェンダーや身体的・精神的困難、はたまた人間と自然との共生という新たな視点を示すことで、視野を広げ視座を高め、共生社会のためにすべきことを考えるきっかけとなったように思えます。
移民・難民など自分にとって日常ではないことに対して、個々の状況を知り、ジブンゴトとして捉えることができるようになるために、今後合教科(社会・英語等)での学びを計画したいと思います。