大阪万博を通じてフィリピンの未来を形作る!(第1回)「万博研修」参加行政官へインタビュー
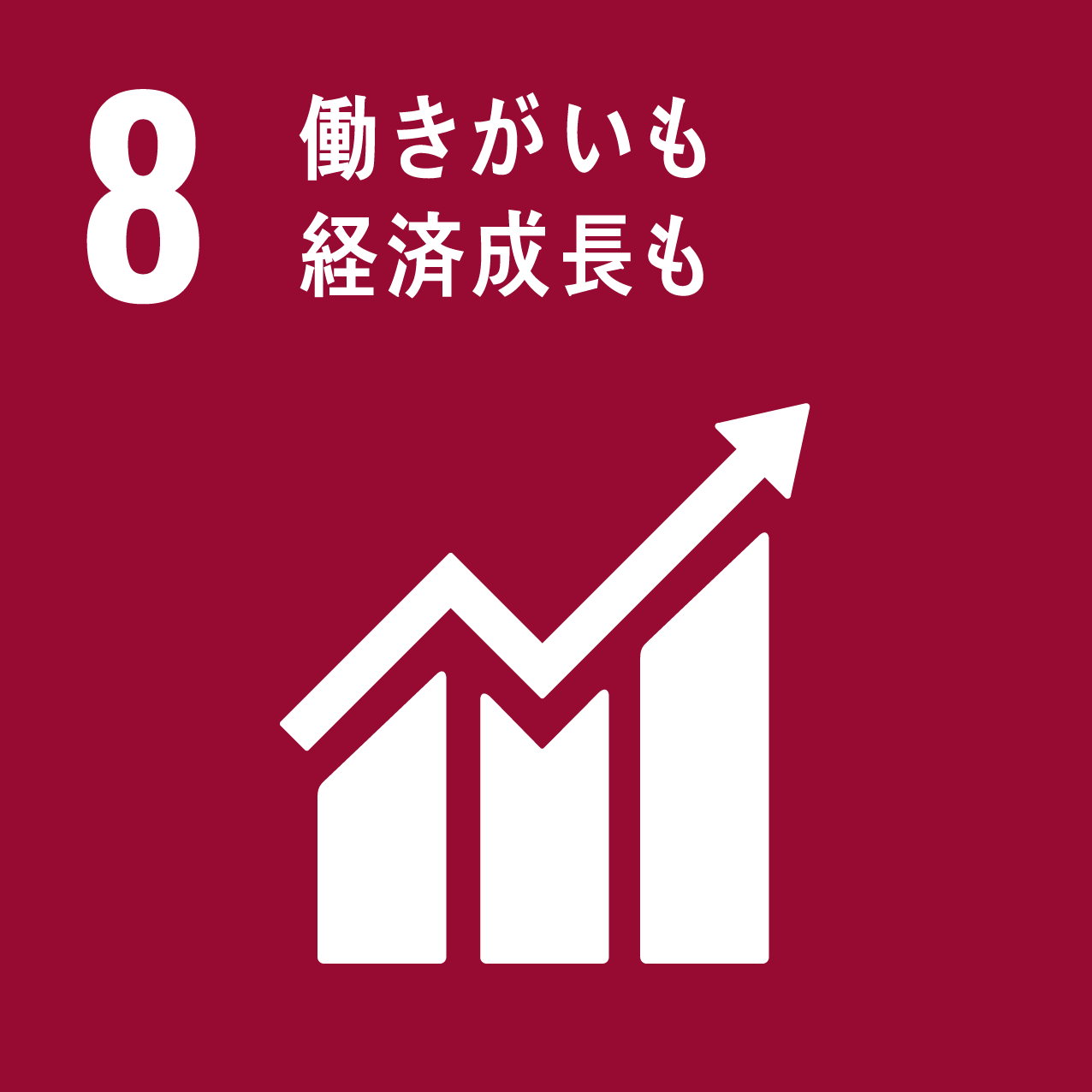


2025.07.03

今回インタビューしたフィリピン政府観光省観光促進委員会所属のMilo Oropezaさん
世界中の国々が集まり、自国の文化や技術、魅力を紹介し合う国際博覧会、万博。
2025年日本国際博覧会(以下、「2025大阪・関西万博」)の開催に際し、JICAは地球規模課題について対話・交流する「テーマウィーク」を開催しているほか、現在途上国へ赴任中のJICA海外協力隊とSDGsや環境問題について考える「ジュニアSDGsキャンプ」や、出展を希望する新興国に対してパビリオン出展支援等の取り組みを実施しています。※1
※1 2025大阪・関西万博におけるJICAの詳しい取り組みはこちら
また、万博は他国から知見を学び合い、自国の更なる発展に活用する文化交流の場でもあります。2025大阪・関西万博には自国の産業振興を志す途上国からも、世界各国のモデルケースを学びに多くの行政官が来日しています。フィリピンからも6月7日の「フィリピンナショナルデー※2」に合わせて、フィリピン政府の行政官や、バンサモロ暫定自治政府(BTA)の貿易産業観光省(MTIT)の行政官及び中小企業の経営者ら(MSMEs)が研修の一環で万博を訪れました。
※2 2025大阪・関西万博に公式参加している各国・各地域の文化に対する理解を深め、国際親善の増進に寄与することを目的とした日。当日は、公式参加者が国内外の賓客や一般の来場者を招いて行う式典と文化イベントが行われます。
本記事では、2回に分けて万博を訪問したフィリピンからの研修員たちの声をお届けします。第1回では、「2025年大阪・関西万博を通じた博覧会及び国際会議開催能力向上」(以下、「万博研修」)に参加したフィリピン政府観光省(Department of Tourism)観光促進委員会職員のMilo Oropezaさんにお話を伺いました。
JICAは、国際会議やイベント等を開催する際の準備や企画運営に関するノウハウを習得し、将来各国が国際会議等を開催する際に中心的な役割を担う人材の育成・能力向上を目的とした「2025年大阪・関西万博を通じた博覧会及び国際会議開催能力向上」研修を実施しています。
7か国の途上国※3から行政官研修員(以降、「研修員」)が集まり、要人接遇のノウハウや広報活動等の企画運営の実務のほか、観光庁と独立行政法人国際観光振興機構(JNTO)が共同で作成した万博関連モデルコースを視察しながら各地の観光振興の様子を学んだり、大阪大学が主催する「いのち会議」事業に参画し、SDGs達成に向けた方策を学んでいます。
※3 研修員の派遣元:カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、モンゴル、フィリピン、タイの7か国

「万博研修」参加研修員が博覧会協会櫟副事務総長を表敬訪問

研修の様子
万博研修に参加し、実際に2025大阪・関西万博を訪問したことを通じて、国際会議やイベントの運営方法のみではなく、その場を有効活用した文化交流のあり方や観客に対するメッセージの発信方法など様々な学びを得ることができました。
魅力的なパビリオンデザイン
2025大阪・関西万博では、各パビリオンが強い物語性を持っていました。例えば、日本、スペイン、UAEのパビリオンは、観客が参加型で展示を体験できる最新技術や建築デザイン、文化的シンボルの展示をうまく組み合わせて、観客の感情に訴えかける体験を作り出し、各国の素晴らしさを伝えていました。情報を提供するだけでなく、感情に訴える体験を作ることの重要性を学びました。
万博内での「サステナビリティ」の実践
2025大阪・関西万博ではサステナビリティ(持続可能性)が重要なテーマとして掲げられていましたが、単なるテーマではなく多くのパビリオンに実際に組み込まれていました。再生可能エネルギーの利用や持続可能な素材を活用したパビリオン建設などの実例を見て、「サステナビリティ」がイベント計画のすべての段階で重要であることを再確認しました。
文化交流が持つ力の大きさ
万博は様々な国々のパビリオンを巡り、観客が各国の文化や歴史を知る中で自然と好印象を持つきっかけになっています。商業的な取引に頼らずとも、文化交流によって相互理解を促進できる可能性の大きさを知りました。
人々の共感を呼ぶ国際イベントの可能性
万博は革新的な考え方を多くの人々に伝える可能性を持っています。国際イベントが世界の様々な問題について、人々が対話し、共にアクションを起こすきっかけに繋がると学びました。
スムーズな運営のための調整の重要性
これだけ大規模なイベントであるのにも関わらず、2025大阪・関西万博がスムーズな運営であったことに大変驚きました。今回の万博は今後国際的な大規模イベントを運営することになった場合の基準となりましたし、様々な関係者と詳細な計画を練った上でイベントを準備・運営することの重要性を学びました。

フィリピンパビリオンは、「サステナビリティ」を体現しているパビリオンです。
伝統的な素材やフィリピン現地の材料を使用した環境に優しいデザインとなっており、万博終了後にはフィリピンで再利用する計画となっています。展示ではフィリピンの職人技が鮮やかに紹介されており、フィリピンの魅力を存分に味わうことができます。
フィリピンパビリオンを訪れることは、観客はフィリピンの文化や歴史をさらに理解し、フィリピン、日本、そして世界との文化交流を深めるきっかけとなると思います。

フィリピンパビリオン内の様子

パビリオン内にはフィリピン式マッサージを受けられる場所も。
万博研修で得た知識を活かし、フィリピンの観光セクターの未来に貢献したいと考えています。特に、先端技術を使った没入型の体験は、観客との対話を促進し、メッセージを効果的に伝えるための重要なツールだと感じました。これを活用して、フィリピンでのイベントや展示のクオリティを向上させたいです。
また、万博では「サステナビリティ」が常に重要なテーマとして掲げられていました。フィリピンの観光業でも、環境に配慮したイベント運営を行い、人々が世界の課題に対してアクションを起こす場を作っていきたいと思います。
さらに、国際イベント開催に向けたトレーニングをフィリピン国内で充実させることで、今後の万博や国際サミットなどのイベントにおいて、国際社会とのパートナーシップを強化していきたいです。これらの取り組みを通じて、フィリピンの観光業がより持続可能で魅力的なものになることを目指していきたいです。
実際にフィリピンパビリオンへ訪れた方々に取材したところ、以下のような声が聞かれました。フィリピンパビリオンを通じて、フィリピンの魅力が伝わっているようです。
Miloさんをはじめとした「万博研修」に参加した研修員は、帰国後、研修での学びを活用して、母国での国際イベント開催や観光セクター全体の発展に取り組んでいきます。JICAはこれからも「万博研修」をはじめとした、途上国出身の行政官に対する研修事業、「人づくり」を通じて、「国創り」に協力することで、これからの国際社会を共に助け合う途上国との信頼を築いていきます。
第2回では半世紀に渡って続いた「ミンダナオ紛争」後、平和の実現に向けて産業振興に取り組むバンサモロ・ムスリム・ミンダナオ自治地域(BARMM)から来日した職員の万博訪問インタビューをお届けします。万博で得た学びが、どのようにフィリピンの持続的な平和に繋がるのか、ご紹介します。
scroll