- トップページ
- 事業について
- 事業ごとの取り組み
- 民間連携事業
- 途上国の課題/ビジネスニーズを知る
- 分野別
- 課題情報の発信(栄養)
(最終更新:2024年8月)
1. 途上国の課題
健康を維持するために必要な栄養を十分に摂取できていない「低栄養」や、エネルギーの取り過ぎ等の「過栄養」が世界的な課題になっています。子どもの低栄養は、身体的・知的な発達遅滞を引き起こし、過栄養は非感染性疾患の原因となります。特に開発途上国では、低栄養と過栄養の「二重負荷」 ※ が深刻な課題です。これら途上国の栄養不良という課題の背景には、貧困や養育者の教育レベル、女性と子どもに食事が優先されない社会文化的側面があります。その背景を踏まえて、課題の要因を、適切な食事習慣や成長のモニタリングが実践されない「食習慣とケア」と、食糧不足や摂食の偏りの因子などの「食料の調達」の視点で整理しました。
※低栄養と過栄養が個人や集団内で同時に見られたり、一生涯の中で低栄養と過栄養の時期が存在したりする状態
開発途上国の栄養に関する課題の概要
課題01:食習慣とケア(低栄養)
低栄養…発育阻害、やせ、微量栄養素欠乏 ※1
● 妊産婦・養育者・家族などの個人の要因 ● 行政・学校・企業の要因
- 出生前ケア
- ●妊婦の慢性的な低栄養
●低栄養状態の母から子に連鎖する低栄養サイクル - 母乳・離乳食
- ●離乳食が適切に与えられない(適時・適量・安全)
●完全母乳育児が実施されない - 食習慣
- ●家庭で健康的な食事(の選択肢)がない
●栄養・バランス食などに関する知識・意識が不十分 - 高齢者ケア
- ●高齢者向けの栄養摂取に関する知識・対策・製品がない
- 成長モニタリング/保健サービスとの連携
- ●産前産後、乳幼児、学童の各ステージでの検診による成長モニタリング※2や、労働者健診が実施されない
※1ビタミン、ミネラルなど、微量ながらも人の発達や代謝機能を適切に維持するために必要な栄養素
※2定期的に体重や身長などを計測し、発達の評価をすることで、健康、成長発達、栄養状態を把握して、健康教育を提供することで小児の健全な成長を見守ること
課題02:食習慣とケア(過栄養)
過栄養…過体重、肥満
● 養育者・家族などの個人の要因 ● 行政・学校・企業の要因
- 食習慣
- ●家庭で健康的な食事(の選択肢)がない
●空腹を低コストで満たしやすい炭水化物や甘味料、油脂多用食が好まれる
●栄養・バランス食などに対する知識・意識が不十分 - 高齢者ケア
- ●高齢者向けの栄養摂取に関する知識・対策・製品がない
- 成長モニタリング/保健サービスとの連携
- ●産前産後、乳幼児、学童の各ステージでの検診による成長モニタリングや、労働者健診が実施されない
課題03:食料の調達
- 質と量
- ●食物の栄養価および生産量が不十分
- アクセス
- ●インフラを含めたサプライチェーンが未発達で、生鮮食品の保管・運搬が難しい
結果、食物の価格が上昇し、必要な食物が購入できない
2. JICAの事業戦略(グローバルアジェンダ)
JICAは、「栄養の改善」をグローバルアジェンダの目的とし、日本の強みや経験が活かせる分野として2つのクラスター(協力方針)を設定しています。(1)ライフコースを通じた栄養改善、(2)食と栄養のアフリカイニシアティブです。
グローバルアジェンダの目的
開発途上国の子どもを中心とする脆弱な人々の慢性的な低栄養状態の改善に向けた取組により、「栄養不良」の課題解決を目指す。「過栄養」に対する取組も、同課題が深刻化している国において推進し、栄養不良の二重負荷(低栄養、過栄養)の低減を目指す。
日本の製品・サービスが求められるサブセクター
- ・食料の調達
- 03 食料の質・量・アクセスを通じた栄養不良(低・過栄養)の改善
【参考】JICAグローバルアジェンダ 「栄養の改善」
https://www.jica.go.jp/activities/issues/nutrition/index.html
3. サブセクター説明
上記の課題をもとに、栄養分野におけるビジネスニーズや事業展開国を検討する際のポイント、企業の展開事例などを、「食習慣とケアを通した低栄養の改善」「食習慣とケアを通した過栄養の改善」「食料の調達を通した栄養不良の改善」の3つのサブセクターに分類して説明します。
日本の製品・サービスが求められるサブセクター
食習慣とケアを通した低栄養の改善
- 現状と課題
- 5歳未満児の年間死亡の45%が低栄養に関係
- 低栄養人口は減少していたが、2015年から再び増加
- 低栄養・低出生体重は、成人後NCDs(非感染性疾患)発症リスクが高い
- 「最初の1000日」(胎児期280日+生後2年間)や高齢者に重点を置いた現地ニーズ
- 妊娠期の栄養指導・貧血予防
- 妊婦・乳幼児への微量栄養素およびその製造技術
- 完全母乳育児・適切な離乳食の推進、成長モニタリング
- 栄養士、保健師など保健栄養人材の育成と、それら人材が活躍できる職場の創出
対象国選定のポイント
統計を活用し、低栄養が深刻な地域を選択する。
特に低栄養は、官民での連携が重要であるため、政府機関のニーズや政府機関との連携の可能性を事前に確認する。
JICAは低栄養の課題が大きいアフリカおよび一部南アジアで多く事業を実施している。これらの地域に展開する場合はJICAの既存事業と連携できる可能性がある。
想定される民間技術(例)
- 栄養(補助)食品や微量栄養素(低価格で供給・流通できるもの、主食を補完するもの、不衛生な環境でも安全に提供できるもの、離乳食、高齢者向け流動食など)
- 妊婦や子どもの栄養・健康データを収集・モニタリングし、必要な支援を提供するデジタル/ICT技術
- 給食サービス
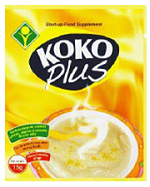
離乳食用サプリメント
1日1袋食事に加えるだけで、幼児の必要な栄養素を供給できる栄養サプリメントを公益財団法人味の素ファンデーションが開発し、ガーナで販売。
日本の製品・サービスが求められるサブセクター
食習慣とケアを通した過栄養の改善
- 現状と課題
- 途上国を含む世界各国で過栄養が増加傾向
- 過栄養は非感染性疾患(NCDs)の一因
- 従来の食習慣への固執や「健康食」への低いモチベーション
- 生活習慣病対策を念頭においた現地ニーズ
- 健康的な食事への行動変更、食習慣改善を促す取組み
- 栄養士・保健師など食育指導を行う保健栄養人材の育成と、それら人材が活躍できる職場の創出
- 食事制限を伴いつつ、食事満足度を高める/満足度減少を補う取組み
対象国選定のポイント
食習慣、食の多様性などをもとに、提案製品・サービスの受容度を事前に検討すること。
JICAは二重の負荷が課題として大きい東アジア、東南アジア、南アジア、大洋州で多く事業を実施している。これらの地域に展開する場合はJICAの既存事業と連携できる可能性がある。
想定される民間技術(例)
- 健康食フードサービス(レストラン、宅配)
- 学校・病院給食、社員食堂事業
- 栄養管理や栄養アドバイスを提供するデジタル/ICT技術
- 栄養教育に寄与する商品・サービス

乳幼児用の離乳食・妊産婦用の食育プログラム
アサヒグループ食品株式会社が開発した離乳食と、日本国内で長年実施してきた食育プログラムを活用し、ベトナムの保健医療従事者・養育者に対して適切な食事・栄養の知識を普及させ、乳幼児の健全な発達を目指す。
日本の製品・サービスが求められるサブセクター
食料の調達を通した栄養不良の改善
- 現状と課題
- 食料の栄養価および生産量が不十分(質と量)
- 流通・貯蔵を含めたインフラ整備が未発達。結果、価格が値上がりし、必要な食物摂取が減少する(アクセス)
- 現地ニーズ
- 高栄養価作物の栽培技術(大豆などの豆類、葉菜・果実類等)
- 小規模な動物性蛋白質生産技術(養鶏等の畜産等の技術)
- 魚食普及に係る技術
- 品質・衛生管理・鮮度維持に関連する技術・製品
対象国選定のポイント
農業分野の指標の中でも、栄養に関連する農業指標と、栄養状態をみる指標に着目をして、対象国を検討する。
想定される民間技術(例)
- 高栄養価作物の栽培技術
- 栄養補給食品の開発
- 簡易的な所定栄養素の分析、栄養価計算技術
- 簡易な流通ノウハウ・地方部でも導入可能な保存・保管や梱包に係る製品・技術

小型低温倉庫の建設・運営
川崎陸送株式会社が、野菜廃棄削減を目的に、インドで小型低温倉庫の建設・運営をしている。
4. ビジネス展開上のTIPS
他の社会課題を踏まえた多様な関係者との取組み
関連する他の社会課題を考慮すること、多くの関係者を巻き込むことが、より効果的です。
一つの製品やサービスだけのビジネス展開では、栄養不良は解消できません。保健、農業や水・衛生など様々な社会課題を考慮して取り組むこと、また政府やNGOなど様々な関係者と一緒に取り組むことで、栄養不良の課題解決に貢献できます。
行動変容を促す取り組み
行動変容を促す取り組みを想定したビジネス展開が求められます。
健康的な食事の定着にあたっては、食生活の改善などの行動変容を促す取り組みも大事となります。しかしながら、製品・サービスを受け入れてもらうためにも、できるたけ伝統的食習慣を変更しない、という視点も大事です。
現地の食習慣・入手可能な作物の把握
現地の食習慣、入手可能な作物を把握しましょう。
一つの国の中でも、地方や農村部、都市部では、食習慣や入手可能な食物が異なります。季節によっても手に入らない食材もあります。食習慣や入手可能な食物を基本とした製品・アプローチが重要です。
ジェンダーの視点
低栄養に対する介入では、ジェンダーの視点が大事です。
途上国では、特に女性と子どもが栄養不良に直面しており、貧困や文化的・社会的な慣習によって十分な食事を確保できていないことがあります。こういった状況を踏まえて、ビジネス展開を行う必要があります。
5. 統計情報等
1)主な統計の使い方
世界保健機関(WHO) 各国の栄養に関連する統計を検索できるデータベースが提供されています。
2)その他の統計
既存の国別の栄養に関する報告書や統計情報から、進出したい国の栄養の状況、政策を確認しましょう。
-
JICA: 栄養プロファイル
アフリカ、大洋州、アジア、中東各国の栄養に関するニーズや既存の政策・取り組み、優先課題、民間連携先行事例を掲載
https://www.jica.go.jp/activities/issues/nutrition/more.html -
UNICEF: 世界子供白書の巻末統計
国別の母子保健に関する主要統計、2019年の栄養特集の情報が豊富
https://www.unicef.or.jp/sowc/2019/ -
Global Nutrition Report
世界の栄養指標や栄養改善の実施状況のモニタリングを担っているグループが作成
栄養データのダッシュボードを参照可能
https://globalnutritionreport.org/ -
Demographic Health Survey
アメリカ合衆国国際開発庁(USAID)が技術的支援する国別の保健状況分析レポート
https://dhsprogram.com/ -
UNICEF: MICS
UNICEFが支援する母子保健統計
https://mics.unicef.org/ -
世界銀行: Nutrition Country Profile
世界銀行が提供する栄養の国別情報
https://www.worldbank.org/en/topic/health/publication/nutrition-country-profiles -
世界銀行: Open Data
世界銀行が提供するデータベース、栄養関連の指標も確認可能
https://data.worldbank.org/ -
GAFS: Global Food and Nutrition Security Dashboard
世界銀行が提供する食料と栄養に関する国別情報
https://www.gafs.info/country-profiles/?state=Advice&country=GHA&indicator=IPCC











scroll