震災の記憶を未来へ、世界へ。
2025.04.28
JICAは開発途上国の将来を担う意欲と能力を持った行政官・技官らをJICA留学生(以下、留学生)として日本の大学院に受け入れています。日本の発展や開発の歴史を学び母国の発展の参考にしてもらおうと、JICAは留学生に向けて様々なプログラムを実施しています。関西センターでも、2府4県のそれぞれの発展の歴史を学ぶ機会を提供しており、2月18日から20日(3日間)にかけて兵庫県のプログラムを開催しました。阪神・淡路大震災から30年という節目の年に、30名の留学生が「防災」を学び、プログラムをとおして得た学びを記事としてまとめました。これらの記事は今後、防災啓発のために母国で発信する予定です。プログラムの内容と、記事をご紹介します。
【読売新聞社による取材講習会】
阪神・淡路大震災当時、読売新聞の記者として震災の取材に関わった水野広宣さんの話を伺いました。第一部では被災者の声を伝える意義を伝えてくださり、留学生は、災害報道の難しさ、防災意識の向上、新聞の役割などについて多くの質問をしていました。講演の第二部では、デジタル時代における取材の重要性とアナログな対面取材の価値についてお話いただきました。
留学生からは、「市民の防災意識を維持するために、新聞はどういった役割を果たすことができるのか模索し続ける姿が印象的だった」というコメントや、「日本は地震大国で住民の防災意識は高いにもかかわらず、ショッピングモールなどで割れやすい商品が棚の上などに展示されているのはなぜなのだろうか」といった疑問も出ていました。


【北淡震災記念公園への訪問】
午後には、北淡震災記念公園を訪れました。はじめに、阪神・淡路大震災の経験をもとに、震災の教訓を伝える語り部の森康成さんからお話を伺い、野島活断層を震源とする地震の特徴や、地域の結束によって多くの命が救われた事例が紹介されました。自身の家も山の斜面崩壊の影響を受けた森さんが震災時の恐怖を振り返る中で、「避難する際に正解はない」という現実を語られていたのが印象的でした。留学生からは、震災後の対応や安全対策と建物の耐震性、心理的影響とメンタルケアに焦点を当てた質問が出ていました。お話を聞いた後は実際の野島断層を含む施設内を見て回り、改めて地震の脅威を肌で感じました。


【齋藤先生とのディスカッション】
兵庫県で初代防災監を務められ、その後兵庫県副知事として兵庫県の復興を牽引された関西国際大学の齋藤富雄名誉教授を講師に迎え、防災の“我がごと化”や“災害に強いまちづくり”、“防災教育”を推進する取り組みについて講演をしていただきました。神戸大学博士課程で防災研究をされているレアンドロさんが留学生の代表として登壇し、行政主導の災害対策や市民の危機意識の醸成について齋藤教授と意見交換を行いました。「備え不足が実際の被害拡大にどのような影響を与えるのか」「地域住民の相互扶助はどのように生まれるのか」など活発に質問が飛び交い、防災・減災に対する理解を深める機会となりました。

【人と防災未来センターへの訪問】
人と防災未来センターでは、震災発生の瞬間を再現したシアターや倒壊した家屋のリアルなジオラマ模型の見学をとおして、震災の記憶を追体験しながら防災・減災の重要性を学びました。家族の死を嘆き悲しむ人々の動画を見た留学生からは、「人々の感情は世界共通だと実感した」「生身の人間の痛みが伝わるシーンだった」という声が挙がっていました。今回の訪問をとおして、“防災は命を守るための事前投資”という意識を社会全体で共有し、災害の経験と教訓を次世代に継承していく必要性を再認識することができました。

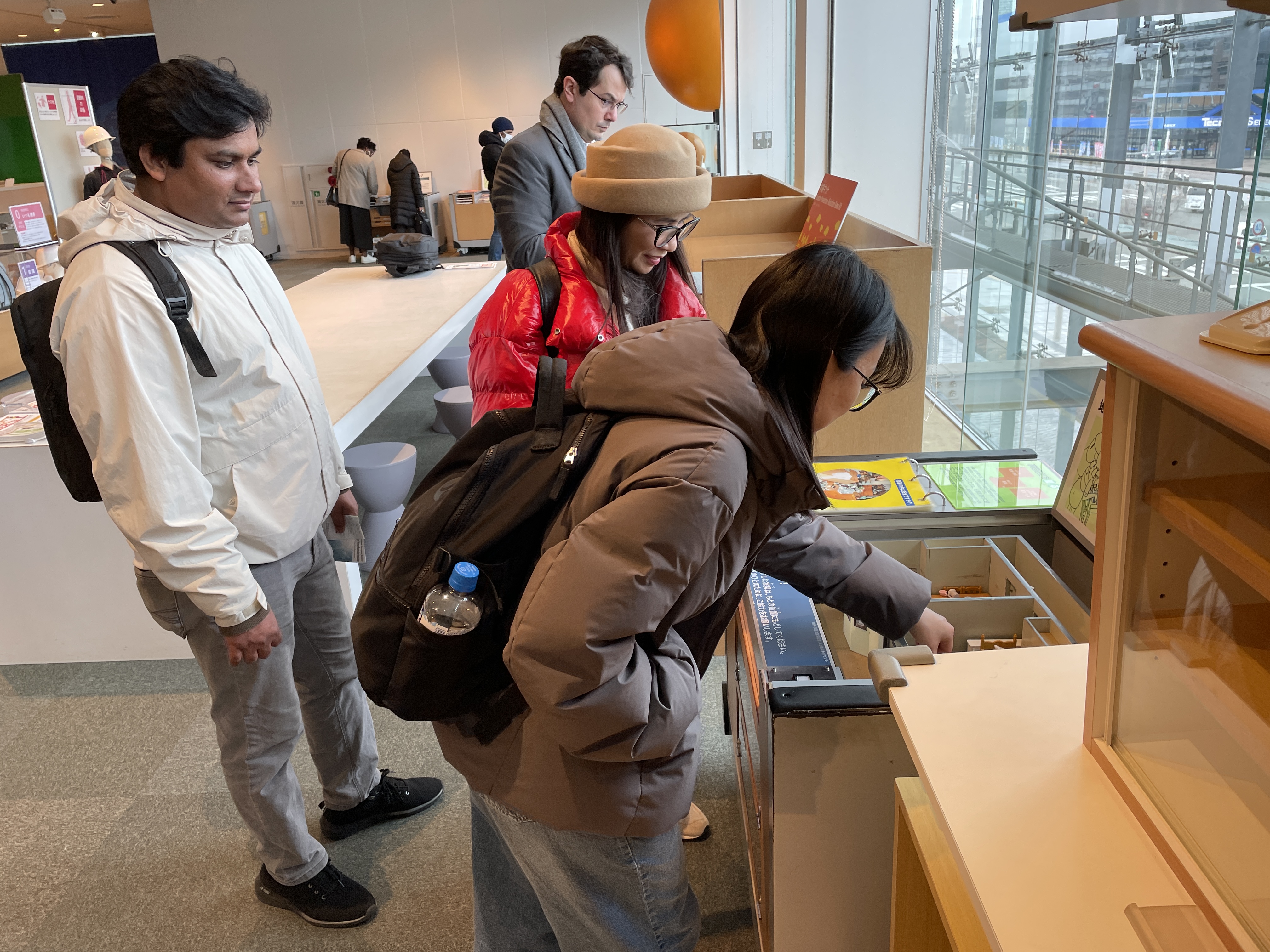
【記事執筆にかかるワークショップ】
読売新聞社よりお越しいただいた坂根薫さんによるレクチャーが行われました。留学生は2日目のプログラム終了後に作成した、母国に発信する記事のドラフトを元に、より多くの人に読んでもらえるよう、レクチャーをとおして学んだことを記事に反映しました。その後、坂根さんから伝授された「5W1Hを盛り込む」「情報の優先順位を決め、可能な限りシンプルに」といったコツを意識し、記事本文から見出しを考えるワークショップが実施されました。留学生は自身が書いた記事の見出しを作成して、積極的に質問もしながら最終的に記事を完成させました。


午後からは作成した記事を全員が発表しました。特に印象に残っているのが「災害が少ない国」で生活している留学生の意見です。彼らは阪神・淡路大震災で大きな被害をもたらした「準備不足」が自国にも当てはまるのではと危機感を抱いていました。中には「漫画を用いて国民の防災意識を向上させることができるのは」というアイデアを出す留学生もいました。
いつどこで発生してもおかしくない災害に対して、どう防災意識を高め、準備を促すか。阪神・淡路大震災の事例をもとに印象深い見出しも数多く発表されました。
イベント後、参加した留学生からは以下のような様々な声が寄せられました。
【3日間かけて学んだこと】
「『災害』を特定の場所でしか起こらない出来事と信じ込まないことが重要。」
「『防災意識』が被害の大きさを左右することを学んだ。」
【自身の学問分野と結びつけてわかったこと】
「災害に関わる法整備が災害の前後で重要な役割を果たすはずだ。」
「現在、世界では資源やエネルギー供給などを国の繋がりで賄っている。一部の地域への災害でもその他の国への二次的な被害もあり得るため、防災は世界的な問題である。各国のコミュニケーションを通じて総合的な戦略、財務面の戦略を立てるべきだ。」
【この経験をどう活かしていきたいか】
「記事を広めて、災害の少ない自国でも起こりうる災害について考えを深めるきっかけにしたい。」
「『準備』の大切さを知ったため、阪神・淡路大震災から得た教訓を発信していきたい。」

本プログラムをきっかけに、留学生がそれぞれの国で防災意識の向上に貢献することを期待しています。
【留学生作成の記事】
アジア・大洋州
アフリカ・中東
中南米
scroll