教育関心者300名以上が注目!グローバルシチズンシップ・国際教育の国際調査シンポジウム報告


2024.07.03
去る5月31日、文部科学省 国立教育政策研究所と国際協力機構(JICA)は、2023 年から実施してきた共同調査「グローバル化時代の国際教育の国際比較調査フェーズⅡ」の知見を共有するべく、「グローバルシチズンシップ・国際教育の国際調査シンポジウム 答えの見えない世界を生き抜く子どもたちへ―学校・教育行政・社会にできること―」を開催しました。
気候変動、感染症、紛争など国境を超えた、地球規模の課題が山積する中、子どもたちが目の前の課題について知り、考え、行動するために、そして「持続可能な社会の創り手」として生き抜くことができるために、学校には何ができるのか。教育行政・社会はどのように貢献できうるのか。2部構成で議論を深めていきました。
本会については様々な学会や教育関心者ML等でも呼びかけていただき、台風接近の中、会場には100名もの関心を持たれる方々が来訪。また250名以上の方々よりオンライン視聴を事前申込みいただきました。ご関心をよせてくださった皆様にも、広報をご協力くださった皆様にも厚く御礼申し上げます。
※シンポジウムの様子は次のJICA YouTubeから視聴いただけます
※報告書は次のJICA HPからご覧いただけます
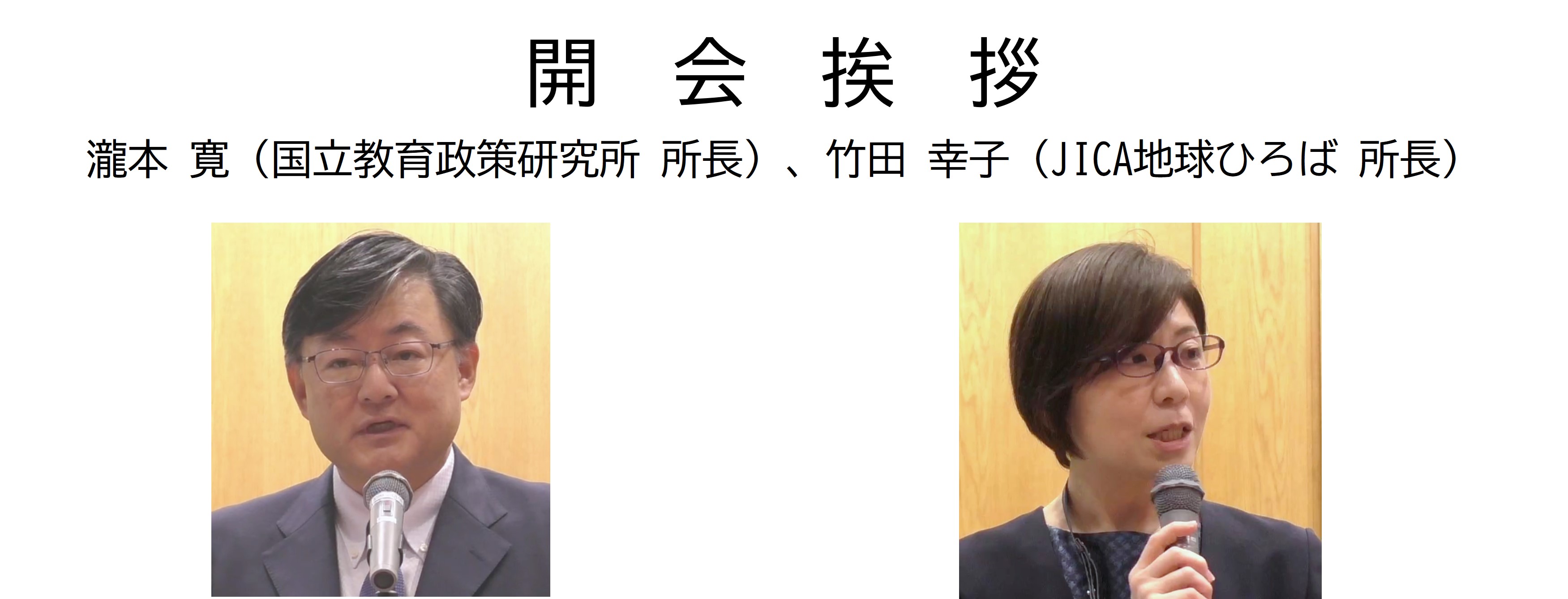
冒頭、開会のご挨拶として、国立教育政策研究所(以下「国研」)の瀧本所長より、国研とJICAの国際教育のシンポジウム開催は2013年以来11年ぶりであることを言及。2013年当時より、世界的に「資質・能力(コンピテンシー)」の育成が目指され、その資質・能力の構造として「知り、考え、行動する」力が共通に求められている点を国研として整理し、そして今回は「子どもたちが知り、考え、行動するにはどのような支援が必要か」を、国際教育を軸として調査を実施したことをご説明いただきました。
JICA地球ひろば所長の竹田からは、日本において外国人労働者増加や「教室の中の国際化」が進み、また世界的には地球温暖化や感染症など地球規模の課題が山積など、グローバルな視点を持ちつつ地域レベルでの対応の必要性が増していることを言及。教員の負荷も増大している中で、国際教育を推進するためにできることは何か、議論を深めたいと挨拶しました。

最初に、株式会社国際開発センター 田中 義隆主任研究員より、海外調査を実施した4か国(英国、カナダ、オーストラリア、韓国)の調査結果概要について報告。各国の社会状況、学校・先生をとりまく状況の変化に触れた上で、本調査におけるマクロ(政府・教育省)、ミクロ(学校現場)とその間にあるメゾ(政府関係機関、大学、企業、民間団体等)という構造的なとらえかたについても説明の後、各国で調査したメゾにあたる組織の位置づけや支援の内容を簡単に説明しました。
調査した4か国のうち、具体的事例として、日本と距離的・文化的にも近い韓国の状況について、文部科学省 国立教育政策研究所フェローである田中光晴氏からより詳細にご報告いただきました。韓国では、現実の問題として外国につながりがある子どもが増加しており、先生方が多文化教育の必要性を切実に感じていること、「支援が必要だから与えるのではなく、外国につながる生徒とそうでない生徒たちの間にある違いを資源としてとらえるような視点への切り替え」が起きていることなどが説明されました。またユネスコの一機関であるAPCEIUが実施する「世界市民教育先導教師事業」など、具体的な支援事例についても紹介がありました。
カナダ・英国・オーストラリア調査については、調査にご参加いただいた先生方から、印象深かった点をご紹介いただきました。各国調査結果詳細については、今後発行される報告書を是非ご覧ください。
最後に、「グローバル化時代に国際教育をデザインする―JICA・国立教育政策研究所による国際調査の総合考察―」と題し、法政大学キャリアデザイン学部 松尾教授より、あらためて研究の背景と問い、分析の枠組み、マクロ・メゾ・ミクロそれぞれのレベルの特徴等をご説明いただきました。
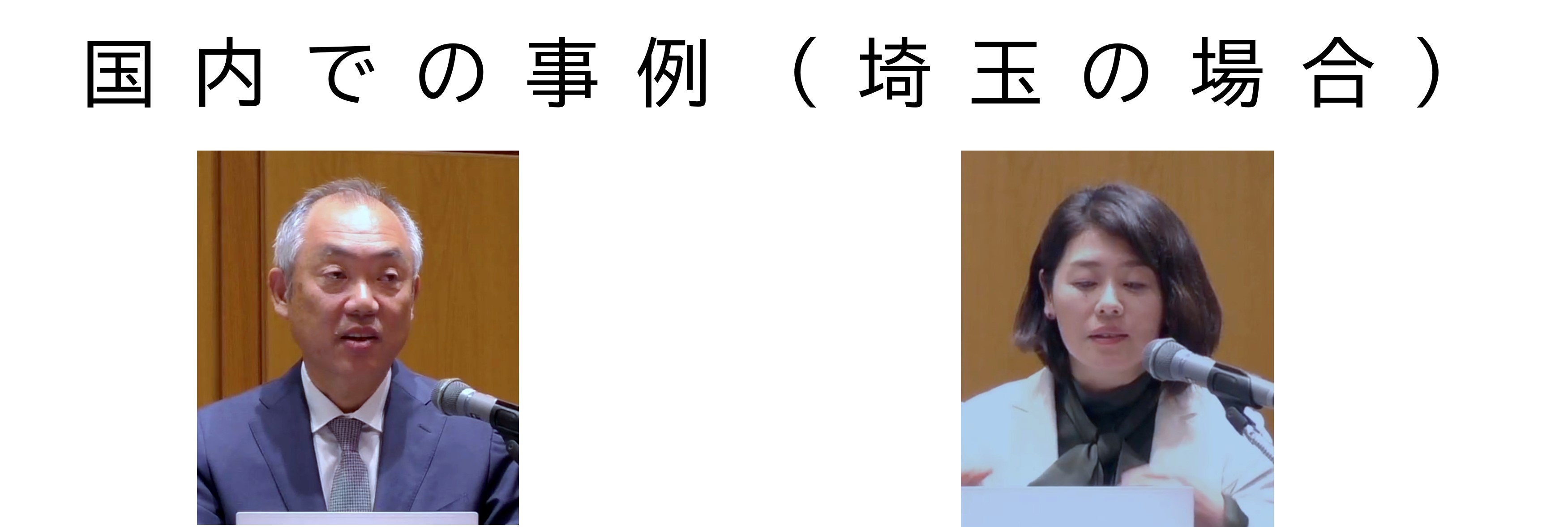
第二部の前半は、日本での取組について考えていくため、国内での事例を共有いただきました。最初に、埼玉県立総合教育センター 田中 邦典所長より、埼玉県の外部との連携状況や、その連携の学校支援への活用事例として「学・SAITAMAプロジェクト」や、センターが実施されている支援をご紹介いただきました。
続けて、学校レベルでの取組として、埼玉県立春日部女子高等学校の事例を「わたしたちが社会を動かす!SDGsで社会とつながる「春女総探プロジェクト」」と題して、今春まで同校の教頭としてプロジェクトを推進された横張亜希子先生(現・埼玉県立吉川美南高等学校 副校長)よりご発表いただきました。総合的な探究の時間に、JICA、動物園、コンビニ、研究機関等の多様な外部機関と1年を通して関わり学びを深め、「自分の力で社会は変えられる」のモットーの下に、生徒は企業に対し自信を持って新事業の提案を行うなど、アウトプットの活動にまで取り組むことも報告されました。
事例発表に続き、有識者の先生方によるパネルディスカッションを行いました。
パネルディスカッションの最初に、国研の白水総括研究官より、これまでの報告で印象に残った点のご紹介がありました。国際教育は、教室の中で多様な文化に触れることでも可能であること、できないことをベースとした教育から、「強み、できること」をベースとした教育に転換がはかられていること(deficit-based approachからasset-based approachへ)、学校、地方教育現場が使えるリソースを探し、最大限活用しようとしていること、の3点です。
JICAからも現在の開発教育支援事業と最近10年での取組の変化等をご紹介し、パネルの皆さんから示唆に富んださまざまなご意見をいただきました。ほんの一部となりますが、以下にご紹介します。
○従来の「答えのある教育」を「答えの無い教育」へ変えていくことは、教員にとって精神的に不安要素。教育を変えるためには、マクロ・メゾ・ミクロの各レベルでの合意が不可欠。
○今後ますます課題が複雑化していく中で、一つの外部機関で出来ることには限界があり、メゾ同士の連携も必要。
○海外に比し日本では主体的なカリキュラム・マネジメントの余地が少ないが、春日部高校は総合的な探究の時間を活用し学校の裁量権を活かした事例。学校現場では、外部連携推進が必要でそのためには管理職の理解度向上が大切。
○日本の大学の教員養成課程では国際教育の科目が限られている。学生が国際教育に触れないまま教員になることが無いよう、教員養成課程の再考が必要。
○NGOとJICAとの開発教育に関する対話の場を復活させることを提案。学校教育(子ども)だけでなく、社会教育や生涯教育(大人)も重要。
各国のメゾ同士が連携し、国境を越えて生徒同士が問題解決型の学びに取り組む「国際協働学習」を提案。未来世代が答えを見出す場を、メゾ組織も含めた大人が作ることが大切。
最後に、国研の白水総括研究官から、これから、教室の中を支えるために実践の知見共有の機会が望まれるとの点に続き、ミクロ・メゾ・マクロの構造を、学校を主体としてとらえたエコシステムとして改めてとらえる視点について発言がありました。子どもの視点からカリキュラムを見ること、学校からみた条件やリソースを考えること、学校が知らない世界を知っているメゾを広げること、それらをあくまでも学校が主体であるというマインドセットをもってトータルにデザインしていけるとよいのではといった大きな絵姿が提示され、シンポジウムは幕を閉じました。
本シンポジウムでの議論もふまえ、JICA全体として、今後の開発教育支援事業について検討していきたいと考えます。
==シンポジウム登壇者一覧==
【開会挨拶】
瀧本 寛(国立教育政策研究所 所長)
竹田 幸子(JICA地球ひろば 所長)
【今回の共同調査で得たナレッジ・提言の共有】
ー英国・カナダ・オーストラリア・韓国における調査の概要と国際教育の現状
田中 義隆(株式会社国際開発センター 主任研究員)
ー多文化化とGlobal Citizenship Educationの推進―韓国調査報告―
田中 光晴(文部科学省 総合教育政策局 調査企画課 外国調査係)
ー調査参加者からひと言
カナダ調査/松原 憲治(国立教育政策研究所 教育課程研究センター基礎教育部 総括研究官)
英国調査/植田 みどり(国立教育政策研究所 教育政策・評価研究部 総括研究官)
オーストラリア調査/青木 麻衣子(北海道大学 高等教育推進機構 教授)
ーグローバル化時代に国際教育をデザインする―JICA・国立教育政策研究所による国際調査の総合考察―
松尾 知明(法政大学キャリアデザイン学部 教授)
【「これから」を考える】
ー埼玉県におけるメゾの活用~教育委員会の立場から外部の力を得る事例~
田中 邦典(埼玉県立総合教育センター 所長)
ーわたしたちが社会を動かす!SDGsで社会とつながる「春女総探プロジェクト」
横張 亜希子(埼玉県立吉川美南高等学校 副校長)
【パネルディスカッション】
『答えの見えない世界を生き抜く子どもたちへ ―学校・教育行政・社会にできること―』
パネラー:
田中 邦典(埼玉県立総合教育センター 所長)
白水 始(国立教育政策研究所 初等中等教育研究部 副部長 総括研究官
・教育データサイエンスセンター 副センター長)
永田 佳之(聖心女子大学現代教養学部 教授・国際理解教育学会 会長)
湯本 浩之(元 宇都宮大学留学生・国際交流センター 教授、開発教育協会(DEAR)代表理事)
畔上 智洋(JICA広報部地球ひろば推進課 課長)
モデレーター:
折田 朋美(JICA緒方貞子平和開発研究所 上席研究員)
総合司会:
湯浅 あゆ美(JICA東京 次長(市民参加協力担当))
報告:石沢祐子(JICA中部 市民参加協力課 専任参事)
scroll