未来の国際協力の種をまく Part2 課題別研修「健康危機に対応する結核対策-革新的技術を用いた保健システム構築-」
2024.07.25
日本の看護師養成学校の生徒は、結核についてどんなことを知っているのでしょうか?結核の状況は日本と世界とで違うのでしょうか?
COVID-19など世界的な健康危機への対応も視野に入れた結核対策の研修で来日した研修員5名が埼玉県立常盤高等学校を訪問し、ヘルスプロモーション講座の生徒と交流をしました。
JICA研修員達が到着すると、まず実習の様子について見学をさせてもらいました。
実習室では生徒が2人1組になり、患者の食事介助をする練習をしています。
研修員からは「患者が食事を拒否した時にどう対応するのか?」、「患者が退院する際、家族に食事介助の方法を学んでもらうのか?」といった質問が出ていました。これらの質問を通じ、JICA研修員の国では入院中の患者の身の回りの世話を家族がすることが多い一方で、日本では看護師が患者の世話をすることが多いという違いを知りました。

実習担当の教諭へ熱心に質問をするJICA研修員
次に、講義室へ移動し、同校の牛坂教諭よりJICA研修員へ学校の紹介がありました。
埼玉県立常盤高等学校は埼玉県で看護師養成のための5年一貫教育をしている学校で、学校卒業後に進学するため早く看護師になれること、学費が安価なことが魅力の学校です。国家試験の高い合格率も特徴の一つです。

常盤高等学校を紹介するクイズを出題
JICA担当からは、参加国の紹介として、国旗と地図から国名や、各国の死因トップ10などをクイズ形式で出題し、各国の挨拶の紹介も行いました。東ティモールの死因トップが結核であることを知った学生たちからは驚きの声があがりました。
続いてJICA研修員から、自国でどのような仕事をしているのか、結核対策について地域での公衆衛生的な対応と病院での臨床対応をそれぞれ紹介してもらいました。
エリトリアの研修員からは、公衆衛生的対応として、住民ボランティア(DOTs[1]プロモーターと現地では呼ばれている)が患者の継続的な服薬を支援している様子や、咳の続いている住民に受診を勧めることで患者発見に繋がっていることについて発表がありました。
パプアニューギニアの研修員からは、国内に島が多いこと、700言語あることが結核対策推進をするうえで難しい点について発表がありました。また、HIV患者の結核罹患が深刻な問題となっているため、政府が結核とHIV対策の現場を視察している様子の写真を見せてくれました。
[1]DOTs(ドッツ)とは、Directly Observed Treatment Short Courseの略で、直接服薬確認療法を指す。結核患者の服薬を保健所等の第三者が確認し、確実な治癒を目指す方法。

パプアニューギニアの研修員が自国の結核対策について発表している様子
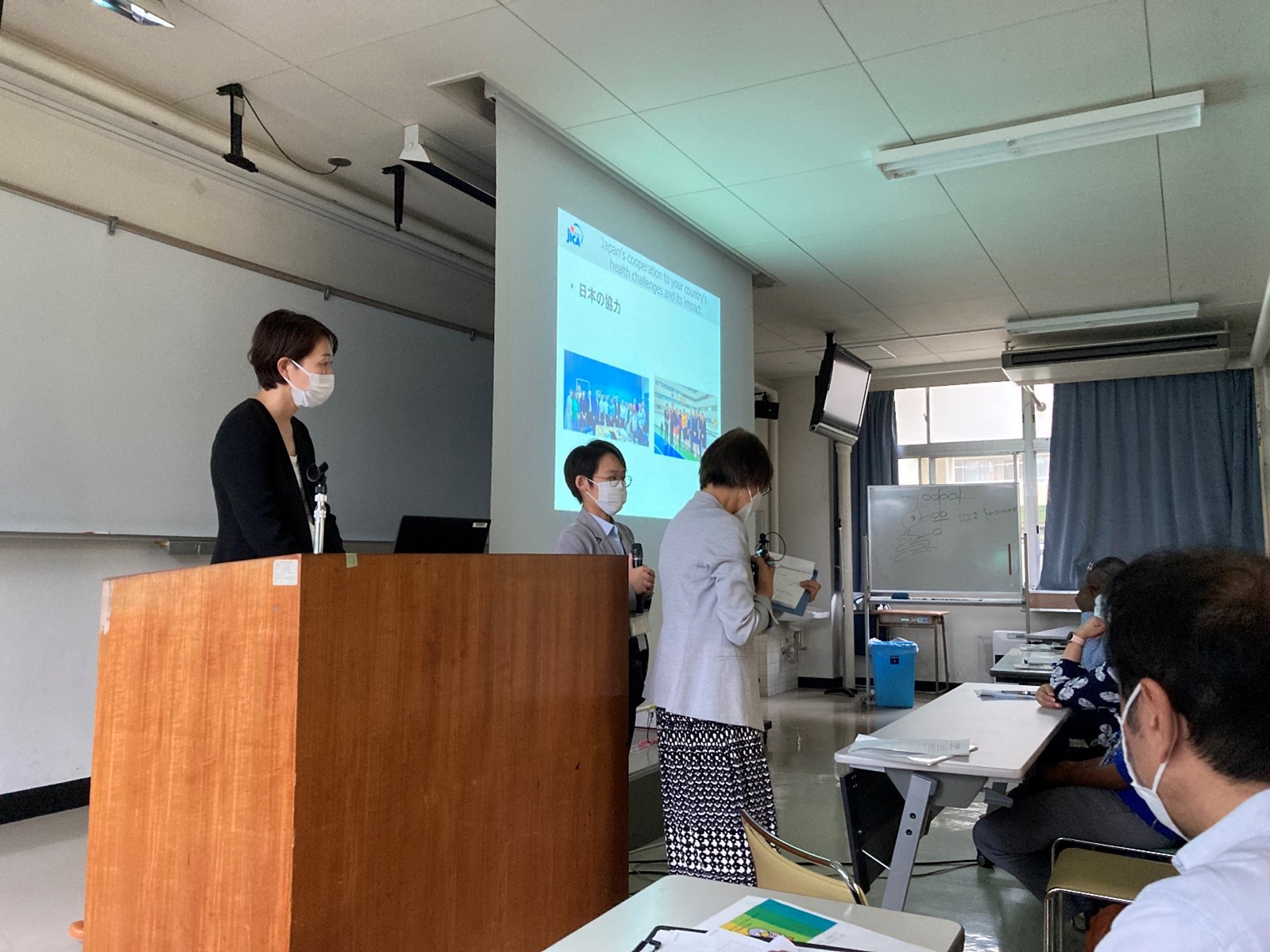
タイの研修員が勤務先の病院での臨床対応について発表している様子
研修員の発表の後、生徒からは「結核の低蔓延と高蔓延の違いは何ですか?」といった質問があり、同行していた公益財団法人結核予防会結核研究所(研修実施機関)平尾晋医師よりWHOの定義をもとに「高蔓延は人口10万人あたり100人より多く、低蔓延は人口10万人当たり10人より少ないこと」と補足の解説をしていただきました。
生徒からは後日嬉しい反応を頂きました。
「東ティモールで死因第一位が結核であるという事実に驚きを隠しきれませんでした。一人一人がしっかりと意識をつけて、必要な場面でマスクをつけることが予防になるのではと考えさせられました。一生に一度あるかないかの素敵な時間をありがとうございました。」
「JICA研修員の話を直接聞き、調べるだけでは分からないことが沢山あることが分かった。土地によって死因も大きく異なり、死と生活には深い関りがあることを実感しました。病院で働くことだけが全てではなく、進路の選択肢も増えて貴重な体験でした。」
「私は今まで海外の国にあまり興味が無かったけれど、JICA研修員の話を聞いて興味を持ちました。エリトリアと東ティモールという国を初めて知りました。」
今回のJICA研修員の常盤高等学校訪問が、生徒のみなさんにとって日本が実施している保健医療協力への理解を深める機会になったようです。
日本は結核低蔓延国となりましたが、在日外国人の結核罹患率が高い状況が続いています。彼ら/彼女らは将来看護師として、在日外国人の結核患者の治療に従事する可能性があります。その際に世界各国の結核の状況や各国で結核対策に奮闘する研修員の姿を思い出してもらえたら嬉しいです。
JICA研修員と常盤高等学校の生徒達
◆関連ファイル
・短期研修員の学校訪問ご希望の場合はこちらまで!
・WHO consolidated guidelines on tuberculosis: Module 1: Prevention - infection prevention and control
報告者:JICA東京センター 人間開発計画調整課 平野志穂
scroll