コロナの影響で始まったオンライン研修で途上国とのつながりを再認識
2021.03.09
2020年度課題別研修「循環型社会構築のための固形廃棄物管理B」コースは、当初、同年8月に研修員がブラジルと日本に渡航して実施する予定でした。関西地域、特に京都で培われた資源循環・低炭素社会の構築を目標としたごみ処理を、京都市環境保全活動推進協会(KEAA)の協力のもと学び、各国の環境衛生改善につなげるのが目的です。参加国はブラジルとモザンビークで、特に日本に渡航する直前に研修員全員がブラジリアとサンパウロを訪問し、同地の固形廃棄物管理を学ぶ事前研修プログラムが特色です。
しかし、新型コロナウィルス感染拡大のため渡航が困難となり、日本との時差が8~12時間の国に住み、ポルトガル語でのコミュニケーションが求められる研修員達に、研修コンテンツを遠隔で提供する必要が生じました。
そこで、当初日本で受講する予定であった講義は、KEAAがオンデマンド動画教材を作成、インターネット上の学習支援ツール上にポルトガル語吹替でアップ、研修員が自国から視聴出来るようにしました。しかし、一方、サンパウロ等で予定していた講義や見学については、世界的にも比較的甚大なコロナ被害が報じられるブラジルの協力機関(ブラジリア連邦区清掃公社(SLU)、サンパウロ市都市清掃機構(AMLURB))が、見学受入という当初の形態から遠隔教材の提供という大幅な変更に対応できるかどうか非常に不透明でした。

動画教材のツカミは最初の数秒、楽器も弾きます(KEAA)

環境漫画家ハイ・ムーン先生による講義(KEAA)
JICAはブラジルの固形廃棄物管理分野でも「E-Wasteリバースロジスティクス改善プロジェクト」を実施するなど長年協力してきており、JICAブラジル事務所はそのような国際協力活動の最前線としてブラジル側関係機関と信頼関係を構築してきました。
このたびの遠隔教材の作成についても、同事務所がブラジル側協力機関と率直に協議し、それらの機関から快諾を得ることが出来ました。
そして約5か月の準備期間を経て、ブラジル、日本それぞれの知見の詰まった遠隔教材が結集、2021年3月1日オンライン開講に漕ぎつけました。
ブラジル側協力機関からの教材は20テーマ以上にわたり、動画再生時間だけでも6時間を超える充実した内容です。現在の日本では提供が難しい知見、例えばウェストピッカー(ごみ捨て場から回収した有価物を売り生計を立てている人々。多くが非正規の個人や家族単位で、道具や装備も乏しく、感染症や怪我のリスクが伴う労働に従事している。)の組織化等は、アフリカからの参加者のみならず、日本側受入関係者にも参考になります。時差や言語のバリアはありますが、インターネット学習支援ツールを活用したモニタリングやバーチャルな意見交換など、JICA本邦研修の英語プログラム名「Knowledge Co-creation Program」が示すような「知見共創」の場として可能な限り効果の高いものにしていく予定です。

動きのある講義動画で理解度アップ(KEAA)
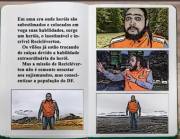
ブラジリア版「ごみ清掃員芸人?」がツカミを担当(SLU)
ブラジル側の遠隔教材には、過去に日本で研修を受けた多くの帰国研修員が講師として登壇している点も、これまでの国際協力の成果の一つと見なせると思います。
また、この教材作成の過程で折につけ、帰国研修員から日本の人々へのお見舞いと励ましのメッセージをもらいました。これまでの両国関係者が築いてきたパートナーシップに基づく、困難な状況下でもお互い励ましあい何かを達成しようとする連帯感が無ければ、この遠隔研修もスムーズには実現しなかったかもしれず、国際協力を通じた人と人とのつながりを再認識させられた機会でした。

帰国研修員の講義(SLU)

帰国研修員の講義(AMLURB)
scroll