実施中プロジェクト
近年、外国人労働者の受け入れをめぐる議論が日本社会のさまざまな分野の中で活発になってきている。その際、外国人労働者の受け入れは、人口減少、少子高齢化や人手不足を背景とした社会と経済の諸課題への対処の文脈で議論されることが一般的である。そこでは、近代以降の日本において国境を越えて移動した人々の歴史が想起されることは極めて少ない。ところが実際には、近代日本において、旧植民地・勢力圏と内地との間で人々の移動や移住が盛んだったことに加え、ハワイや南北アメリカなどにも多くの日本人移民が渡っていった。その中でも、たとえば明治期のハワイ移民や昭和初期のブラジル移民、そして戦後の中南米諸国への海外移住のように、国策として行われた移民送出事業もあった。しかし、日本の中で、ほぼ一世紀にわたって海外へ移民を送り出した側であったことは、果たしてどれほど認識されているだろうか。本研究では、外国人労働者の受け入れをめぐる議論が進む中で、国境を越えて移動する人々と日本の国家や社会との関係の在り方とその歴史的文脈について思考を深めることを試みる。
本研究では日本から中南米諸国への移民送出事業と日本人移民や日系人による活動を対象として、これらが日本と南米諸国の近代国民国家の形成とその変容にどのような役割を果たし、どのような意味を持ったかを問う。その際、ブラジル移民が日本の国策となった1920年代から、就労を目的とした人々の移動の流れが中南米から日本へと変わる兆しが見え始めた1980年代にかけての時期にとりわけ注目する。これを通して、人々の越境移動の観点から、日本と中南米諸国をつなぐ移民を軸とした近現代史の構築を目指す。その際、送出国と受入国の状況がどのように交差して、相互にどのような影響を及ぼしたかを検討して、両方の国家建設の関連性を解明することを目指す。
日本から南米諸国への移民の渡航は1900年代を通してペルーとブラジルにおける労働契約移民として本格化し、1910年代からは移民による入植地の建設がブラジルで始まり、1924年からはブラジルを中心として移民奨励政策と送出事業が国策となった。第二次世界大戦中の中断を挟んで1952年からはブラジル、ボリビア、パラグアイ、アルゼンチン、ドミニカ共和国を対象として行われた。このように日本から中南米諸国への移民は、日本が近代的な国民国家や植民地帝国として再編されつつあった19世紀末に始まり、植民地帝国の膨張と時代的に並行して、帝国の崩壊と占領や国際社会への復帰をきっかけに再開した。そして戦後日本の海外移住事業は、旧植民地・勢力圏からの引き揚げや国内開拓政策、地域社会の再編成、高度経済成長や国際協力事業の展開とともに変化していった。日本の境界や国家の在り方が絶えず変わっていく中で、政府と民間による移民事業は、日本における国家と国民共同体の変容過程の中でどのような役割を果たし、どのような意義を持ったのか。本研究では、このような問題意識から出発しながら、国境を越えた人々の観点から日本の近代を描く。
他方で、移民は中南米諸国の歴史とも深く結びついている。そもそも中南米では、19世紀を通して独立を得た新しい国々にとって、移民の導入と定着が社会的・経済的な近代化の要として重視されていた。そこで、日本人移民はコーヒーやサトウキビなどのプランテーションでの労働力や未開墾地域の開拓の担い手として期待された。一方、ヨーロッパ諸国からの移民を優先しつつ、多様な人々と文化の融合によって新しい国民の創出を理念として掲げていた中で、政治的エリートや知識人の一部から日本人移民への反対論が挙がり、移民制限や阻止の政策がとられることもあった。その間、1920年代から寡頭政治体制から民衆参加型政治体制への移行や一次産品輸出型経済から工業化への転換が試みられ、ナショナリズムの勃興も見られ、1950年代半ばごろから軍事政権が頻発していく中で、日本の移民事業はどのように位置付けられるのか。さらには、移民や日系人による言論や文化的活動は、このような過程をどのように捉えて、どのように意味づけたか。国民共同体のアイデンティティーや国際関係の構築において、中南米への移民の送り出しはどのような意義を持ち、どのような役割を果たしたのか。本研究では日本人移民や日系人の移動と活動を軸にして、南米諸国の近現代の歴史を再考することになる。
以上のように、移民の歴史に着目することで、日本と中南米諸国における国民国家建設過程の連動性を解明することが期待される。このように、移民を軸とした越境的な近現代史が浮かび上がってくる。
- 研究領域
- 開発協力戦略
- 研究期間
- 2021年08月24日 から 2026年03月31日
- 主査
- ガラシーノ・ファクンド
- JICA緒方研究所所属の研究者
- 長村 裕佳子、 近江 加奈子、 長谷川 将士
- 関連地域
-
- 開発課題
-
研究成果(出版物)
-
ファクンド・ガラシーノ・根川幸男「松宮家所蔵南米移民関係資料(その 1)」横浜センター海外移住資料館『研究紀要』第17号、2023年3月、pp. 53-63
-
スタンフォード大学フーバー・インスティチュート(米国)・日本移民学会 共催:Second International Workshop on Japanese Diaspora (2022年11月4日)The Japanese Diaspora as transnational history: migration, development, and nation-building in the Brazilian Amazon (英語)
-
La migración Japonesa y los procesos de modernización (南米における日本人移民と近代化の過程)(スペイン語、JICAチェアの一環としての講義、2021年10月5日)


















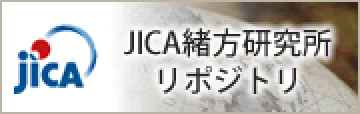

scroll