JICA-世銀連携セミナー:世界開発報告2009「変わりつつある世界経済地理」開催
2009.03.23
11月26日にJICAと世界銀行の共催セミナーにて、2009年版の世界開発報告(WDR)が紹介されました。このWDRは、東アジアの高度経済成長が、沿岸部の産業集積地と開発の遅れた内陸部が空間的に結合されることによって成長を共有しつつ推進されたことに着想を得たものです。JICA研究所はこのWDRの企画段階から深く参画すると共に、論文も寄稿しています。
セミナーではまず恒川惠市・JICA研究所所長が開幕あいさつにおいて、世銀との研究交流を継続する意向を表明しました。小寺清世銀・IMF合同開発委員会事務局長は、30年以上に亘るWDRの歴史を紹介するとともに、JICA研究所に対する期待を述べました。
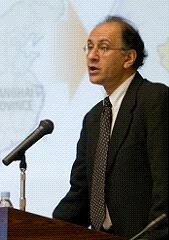
続いて、WDRの執筆責任者であるインダーミット・ジル氏(世銀ヨーロッパ・中央アジア担当チーフエコノミスト)から内容の紹介がなされました。

第3部では、WDRの別冊に掲載された論文の各執筆者によるプレゼンテーションが行われました。
まず、別冊の概要説明を行った世銀のユーコン・ファン氏は、WDRの分析枠組みが東アジアにおける経済成長と格差の発生を極めて整合的に説明し得ることを強調し、国土の均一な発展戦略から沿岸部重点開発戦略へと方針転換して成功した中国を典型事例として挙げました。次いで浜口伸明神戸大教授は、東アジアの経済成長を説明してきた雁行発展論などの既存のパラダイムに代わって、集積経済による経済成長と地域統合という新しいシナリオが出現しており、それに伴って政府の役割も変化しつつあると主張しました。武藤めぐみJICA研究員は、インドネシア地方部においては地方道路改善に伴う都市との連結性の向上が家計収入増加に結び付くことを実証し、地方と都市部を連結する道路インフラ整備の重要性を強調しました。大塚啓二郎GRIPS教授は、アジア・アフリカの産業発展における産業集積の形成促進や技術革新を奨励する政策の有用性に言及しました。大野昭彦青山学院大学教授は、ラオス地方部の織物業において、都市部と地方部双方の商慣習や情報に通じたトレーダーが取引コストの低下を通じてクラスター形成に貢献していることの実証分析を紹介しました。パネル・ディスカッションでは、藤田昌久経済産業研究所所長が空間経済学によって経済理論にロケーションの概念が持ち込まれたことの重要性を強調しました。また荒川博人JICA上級審議役はWDRの提言内容を実際のODA業務に反映させる具体的方策について言及しました。荒川審議役は、先進・後進地域を結合するインフラや貧困層が参加可能な開発の重要性を強調し、新JICAが円借款・無償・技術協力のすべての手段を活用して「空間的統合」の課題に取り組んでいく意向を表明しました。セミナーには各国大使、国際機関、政府等の参加者や研究者が多数参加し、議論に熱心に耳を傾けていました。
開催日時:2008年11月26日(水)
開催場所:JICA研究所

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.
scroll