アジアの平和と発展を考えるシンポジウム開催
2009.09.08
アジアの平和と発展のための制度構築をテーマとする国際シンポジウムとワークショップが、JICA研究所と経済産業研究所(RIETI)及びAPSN(Asian Peace Science Network)の共催により、8月28、29日にJICA研究所国際会議場において開催されました。会合には同会合の提唱者であるウォルター・アイザード名誉教授(米国コーネル大学)をはじめ、恒川惠市JICA研究所所長、藤田昌久RIETI所長、そのほか著名な研究者やJICA関係者などが参加し、アジア地域の制度構築について政治経済の観点から報告があり、実践的な経験を基に活発な議論が交わされました。
今回の会合の目的は、現在の世界的経済危機という状況に対し、通貨・貿易・安全保障等における地域的な制度や枠組みが、アジア全体の一層の平和と繁栄の促進のために、今後どのように発展すべきかについて議論することでした。
1日目(8月28日)に国際シンポジウム、2日目(8月29日)にワークショップが開催され、初日の「平和と発展に向けたアジアの制度構築:グローバル危機を乗り越えて」と題したシンポジウムには、政府関係者や在京大使館関係者、研究者のほか、民間企業関係者、報道関係者、NGOおよびNPO関係者、そして、援助機関関係者ら100人以上が参加しました。アイザード名誉教授、藤田RIETI所長に続き開会挨拶に立ったJICA研究所の恒川所長は、人間の安全保障とアジア地域統合に関してコメントし、地域統合について以下の3つの課題を指摘しました。

写真:谷本美加/JICA
(1) アジアの経済発展のための広域インフラ整備と、国際分業の変化に対応するための人材育成
(2) グローバル化により国境を越えて増大する犯罪や疾病・環境問題
(3) アジア地域に残る暴力的紛争のリスク
そして恒川所長は、これらの課題について、一国レベルで対応することは不可能であり、アジア地域全体としてのアプローチが必要であることを強調しました。
開会挨拶に引き続き、ハディ・ソエサストロ氏(インドネシア戦略国際問題研究所上席研究員)、河合 正弘氏(アジア開発銀行研究所所長)、ユャン・ツァン氏(中国社会科学院アジア太平洋研究所所長)、T.J ペンペル氏(米国カルフォルニア大学バークレー校教授)の4名が基調講演を行いました。講演では、APEC(Asia-Pacific Economic Cooperation:アジア太平洋経済協力)の役割、アジアの影響力が増大する中での地域的な枠組みの一層の必要性、自由貿易協定(FTA)についての賛否、ASEAN(Association of South-East Asian Nations:東南アジア諸国連合)中心の統合モデル、アジア統一通貨の必要性、世界の3極通貨体制、また、アジアの経済統合がいかに地域安全保障の統合より先行しているのか、そして、「組織進化論(Institutional Darwinism)」という新たな概念を用いたアジアの地域制度の将来予測などのトピックスも取り上げられました。
基調講演の後には、地域共同体のガバナンスと国家のガバナンスの両立、中国人民元の通貨交換性とアジア地域でアジア以外の外国通貨を使用する必要性、また、中国の輸出市場と産業が人民元の国際化の衝撃に耐え得るかといった具体的問題について、質疑応答が行われました。
続いて行われたパネルディスカッションでは、恒川所長がモデレーターを務めました。パネリストとして参加した梅宮直樹JICA人間開発部基礎教育第1課調査役は、JICAプロジェクトのAUN/SEED-Net(Southeast Asia Engineering Education Development Network:アセアン工学系高等教育開発ネットワーク)について説明しました。同プロジェクトは、人材開発のための幅広いプログラムや共同研究の実施、また学生や研究者の交流により、ASEANの社会経済発展に貢献することを目指したものです。このプログラムにより、アジア地域における大学教育プログラムの標準化および卒業生の雇用の促進、さらに学生と研究者の交流を促すことで、アジア地域が独自に人材を育てる土壌をつくることが期待されています。
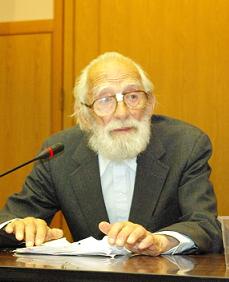
ウォルター・アイザード名誉教授(米国コーネル大学)
2日目に開かれた研究会では、恒川所長、藤田RIETI所長、アイザード名誉教授のあいさつに続き、以下の6つのテーマに分かれて、分科会が行われました。
◆貿易と投資のための制度構築
◆金融・通貨・マクロ経済政策のための制度構築
◆キャパシティ・ディベロップメントのための開発協力
◆環境および資源ガバナンスのための制度構築
◆安全保障問題(非伝統的安全保障を含む)
◆今後のAPSNの活動
「キャパシティ・ディベロップメントのための開発協力」の分科会では、JICA研究所の澤田康幸客員研究員と、佐藤直史JICA国際協力専門員が発表を行いました。澤田客員研究員は、「国際技術移転における技術協力の役割」について述べ、技術協力やその他の援助が途上国での技術移転とキャッチアップに与える影響を、調査した85カ国のデータを基に定量分析するモデルを示しました。その分析結果は、技術協力が技術移転を促進し、キャッチアップのための時間を短縮するということを示唆しており、このため澤田客員研究員は、技術協力が効果的な政策手段となり得ると結論づけました。
同じ分科会で、佐藤専門員は「"法の支配"促進のためのJICA支援におけるキャパシティ・ディベロップメント」というテーマで発表しました。キャパシティ・ディベロップメントのためのJICAの取り組みとしては、一国の法規制の整備の支援と、公的機関の能力開発への支援を挙げ、これを短期および長期で達成するためのJICAの取り組みについて、ベトナムとカンボジアを事例とした研究などを紹介しました。
また、「環境および資源ガバナンスのための制度構築」をテーマとした分科会では、JICA研究所の佐藤仁客員研究員が、「自然のガバナンス:歴史的起源および現代の課題」について、発表を行いました。佐藤客員研究員は、行政組織と環境保護政策の成果との関連性について説明を行い、タイの森林保全のパフォーマンスが良くならない原因として、歴史的に形成された官僚機構の組織的特徴などを挙げました。
こうした経済・政治に関する議論のほか、国境を越えた病気のまん延や犯罪が発生しやすい国境地帯の問題など非伝統的安全保障の問題についての発表がありました。2日間にわたって行われた会合では、政策立案者や研究者、実務家からのさまざまな意見が提示され、実りの多い会合となりました。そして、異なる研究領域を持つ参加者たちは、「アジア地域は、より効率的な地域制度を必要としている」との認識で一致し、そのための具体的な方策などについて、今後、さらに検討していくことになりました。

アジアの平和と発展について議論した国際シンポジウム
■ Agenda&Paper
※ 青字をクリックすると発表内容が確認できます。
August 28
13:00 -13:05 Opening Introduction: Masahisa Fujita (RIETI)
13:05 -13:10 Welcome Speech:Keiichi Tsunekawa (JICA-RI)
13:10 -13:25 Welcome Speech:Walter Isard (Cornel Univ.)
13:25-15:50
Part 1: Keynote Lectures
Chair:
Masahisa Fujita (RIETI)
Keynote lecturers
Hadi Soesastro (CSIS).pdf
Masahiro Kawai (ADBI)
Yuyan Zhang(CASS)
T.J. Pempel (U.C. Berkeley)
Q & A
16:05-18:20
Part 2 Panel Discussion:
"Institutional Cooperation in Asia beyond the Global Economic Crisis"
Moderator:
Keiichi Tsunekawa (JICA-RI)
Panelists (in alphabetical order)
Min Gyo Koo (Yonsei Univ.)ppt .pdf
V. N. Rajasekharan Pillai (Indira Gandhi National Open Univ.)
John Ravenhill (Australian National Univ.).pdf
Naoki Umemiya (JICA).pdf
Susumu Yamakage (Univ. of Tokyo)
Discussion
Q &A
18:20-18:30 Closing Speech: Walter Isard
August 29
8:30 - 9:00 Reception
9:00 - 9:05 Opening Introduction: Keiichi Tsunekawa (JICA-RI)
9:05 - 9:10 Welcome Speech: Masahisa Fujita (RIETI)
9:10 - 9:40 Opening Presentation: Walter Isard (Cornell Univ.)
9:40-11:05
Panel 1: Institution Building for Trade and Investment
Chair:
Risaburo Nezu (RIETI)
Speaker 1 Shujiro Urata (RIETI / Waseda Univ.)
Speaker 2 Biswa N. Bhattacharyay (ADBI)
Discussant Yuyan Zhang (CASS)
Discussion
11:05-12:30
Panel 2: Institution Building for Finance, Currency and Macro-economic Policy
Chair:
Hadi Soesastro (CSIS)
Speaker 1 Eiji Ogawa (RIETI / Hitotsubashi Univ.)
Speaker 2 Chalongphob Sussangkarn (TDRI, ex-Minister of Finance)
Discussant Iwan Azis (Cornell Univ.)
Discussion
13:30-14:55
Panel 3: Development Cooperation for Institutional Capacity Development
Chair:
V.N.Rajasekharan Pillai (Indira Gandhi National Open Univ.)
Speaker 1 Naoshi Sato (JICA)
Speaker 2 Yasuyuki Sawada (Univ. of Tokyo, JICA-RI and RIETI)
Discussant Tatsuhiko Kawashima (Gakushuin Univ.)
Discussion
15:10-16:35
Panel 4: Institution Building for Environment and Resource Governance
Chair:
Glenn Palmer (Pennsylvania State Univ.)
Speaker 1 Jin Sato (Univ. of Tokyo and JICA-RI)
Speaker 2 Huijiong Wang (DRC of the State Council)
Discussant Jurgen Brauer (Augusta State Univ.)
Discussion
16:35-18:00
Panel 5: Security Issues (including non-traditional Security)
Chair:
Hiroshi Kato (JICA-RI)
Speaker 1 Patricio-Nunez Abinales (Center for Southeast Asian Studies, Kyoto Univ.)
Speaker 2 Takeshi Onimaru (National Graduate Institute for Policy Studies)
Discussant Manas Chatterji (Binghamton Univ. USA)
Discussion
18:05-18:50
Panel 6: Future Peace Science and APSN
Chair:
Iwan Azis (Cornell Univ.)
Speaker 1 Glenn Palmer (Pennsylvania State Univ.)
Speaker 2 Raul Caruso (University Cattolica del Sacro Cuore di Milano)
Speaker 3 Ling Xue(Peking Univ.)
18:50-19:00
Closing Session
Walter Isard (Cornell Univ.)
開催日時:2009年8月28日(金)~2009年8月29日(土)
開催場所:JICA研究所

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.
scroll