ミャンマーの社会経済を掘り下げた研究成果を出版
2012.10.22
2008年のJICA研究所設立とともにスタートし、2011年3月に終了した研究プロジェクト「ミャンマー経済の現実と課題」の最終成果をまとめた本『ミャンマー経済の新しい光』が勁草書房社から出版されました。
この本では、現在の成長著しいミャンマー経済の基礎となる、政策転換前の主要分野(為替政策を含むマクロ経済、コメ政策を含む農業開発、工業化政策、自然資源管理、社会基盤など)に焦点をあて、独自に収集したデータを利用して定量的・定性的分析を行い、経済を包括的に展望しています。
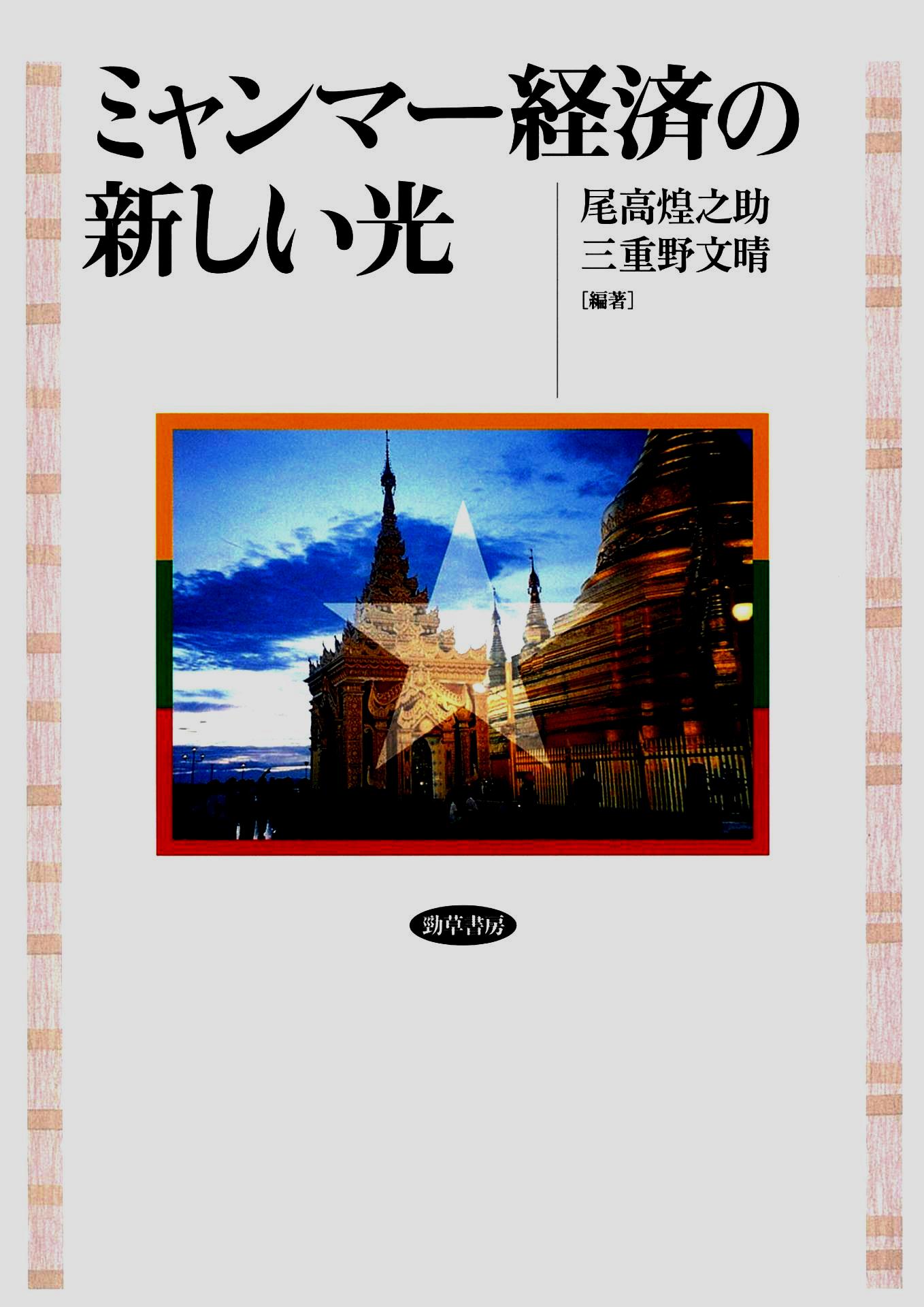
以前のミャンマーは豊富な天然ガス資源と6,000万人を超える人的資源に恵まれているにもかかわらず、独自の政治状況によって経済社会開発は停滞を続けていました。その高い潜在能力を引き上げ、人々の生活水準をより豊かで安定的なものとするような開発戦略の研究が必要とされる一方、その政治状況から情報へのアクセスは限定的になり、小規模の個別的研究・分析にならざるを得ないことが多く、全体像を把握した上での包括的な開発戦略の研究には至らない状況がありました。そこで、JICAが過去数十年間にわたり取り組み得てきた知見の蓄積を有効活用し、ミャンマーの現状と歴史をより正確に踏まえた包括的な開発戦略の研究を推進するために、JICA研究所は研究プロジェクトを開始しました。
この研究には、尾高煌之助一橋大学名誉教授をはじめ、2000年から2004年にかけて実施したJICAプロジェクト「ミャンマー経済構造調整支援プロジェクト」のメンバーが数多く参加しています。当時、プロジェクトチームがミャンマー軍政に対して、研究結果をまとめた経済社会発展のための政策提言を行いました。今回は、そのプロジェクトの調査・分析で得られた経済政策転換の歴史的背景やコメ輸出政策、農村制度改革、民間企業参入が自由化されたことによる工業発展、社会インフラ、運輸交通、電力といった社会資本整備などに関するデータと知見、人的ネットワークは、その後のミャンマー研究そして支援にとって貴重な財産となり、この成果物を構成する重要な要因にもなっています。
この本の目的について、著者の一人である嶋田晴行JICA南アジア部企画役は「開発実務や政策立案に携わる関係者に、ミャンマー支援実務の遂行や援助政策立案に活用してもらうほか、ミャンマー経済に興味のある様々な立場の人たちに、現状と課題を歴史的な文脈も踏まえてわかりやすく解説することを目指しています。そのため、各執筆者が継続的に現地での調査を行い、また国内における研究会、そして最終的な成果発表会などを通じて、日本国内の研究者、外務省をはじめとする中央省庁、JICAをはじめとする援助関係者、そして民間企業からの示唆も参考とすることに努めてきました」と言います。
他方、ミャンマーを巡る情勢は目まぐるしく変化しています。嶋田企画役は「この本の基となった研究会や執筆が行われたのは2008年から2010年であることから、直近の変化を十分に議論、消化できているとは言えません。しかし、ミャンマー経済および社会の構造ともいうべき部分が数年で根本的に変化することは考えられません。現在と将来を見通すためには、歴史的な経緯も含めてミャンマーを長期の視点から捉えることが必要です。このような観点から、急激な変化を見せる情勢にあっても、その本質を理解するという本書の意義及び価値が失われることはないと考えます」と述べています。

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.
scroll