ウェビナー「揺らぐ開発協力—地図なき時代に描く日本のODA」開催
2025.08.20
2025年7月23日、JICA緒方貞子平和開発研究所(JICA緒方研究所)と地経学研究所 は、ウェビナー「揺らぐ開発協力—地図なき時代に描く日本のODA 」を共催しました。米国と欧州の最新情報を共有した上で、世界の連帯が揺らぐ中、日本の政府開発援助(Official Development Assistance: ODA)は何を目指していくべきか議論しました。
まずJICAアメリカ合衆国事務所(以下、米国事務所)の田中賢子所長は、対外援助を担ってきた連邦政府機関であるUSAIDの解体・縮小や予算の見通しについて概説しました。
「USAIDは、連邦政府全体を敵視するトランプ政権により、正当な理由もないまま連邦政府に斬り込む試金石になってしまった。その背景には、抵抗勢力の少なさと世論の支持が盤石ではなかったことがある」と述べました。一方、日本において開発協力が世論の支持を得る上で、官民連携による事業の実施に加え、15ヵ所あるJICAの国内拠点を通したさまざまな交流の存在も大きいのではないかとの考えを示しました。
また、日米の今後の協調については、「マルコ・ルビオ国務長官が『アメリカの開発援助は持続的成長への投資や民間資金の導入を考えるべき』といった日本の国際協力の理念にも通じる考えを述べていることから、日本とのパートナーシップをぜひ活用してほしい」と語りました。
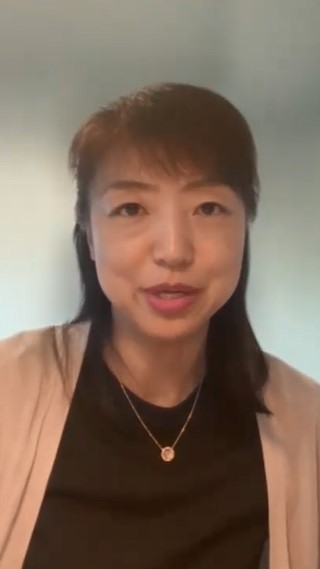
JICAアメリカ合衆国事務所の田中賢子所長
次に、JICAフランス事務所の原田徹也
所長(JICA緒方研究所主席研究員)は、欧州でもODA予算の削減や世論の支持低下が見られることを報告しました。
また、近年、ウクライナへの支援、気候変動対策、自国内での難民受け入れ費用など、ODA予算の使途が多様化する中で、最貧国向けや社会セクター向けの「中核的なODA(コアODA)」の費用を確保すべきという議論があることを紹介しました。一方、中国の一帯一路を意識した戦略的な国際協力を追求する動きもあり、「原点回帰と国益志向の二重構造が欧州のODA議論の現在地」と述べました。
また、2025年7月初旬にスペインで開催された「第4回開発資金のための国際会議(4th International Conference on Financing for Development: FfD4)」の現場で、開発途上国同士の連携や知見の交換が活発化していることにも言及。「日本はODAを“与える”という上からの姿勢ではなく、対等な関係の中でリーダーシップをとっていくことが必要」と提言しました。

JICAフランス事務所の原田徹也所長(JICA緒方研究所主席研究員)
ウェビナー後半には、田中所長、原田所長に3人のパネリストが加わり、JICA緒方研究所の亀井温子 副所長がモデレーターを務めたディスカッションが行われました。開発協力の大きな転換点にある中で日本が果たすべき役割や、日本国内でのODAへの理解向上に向けた取り組みなどをテーマに議論しました。
政策研究大学院大学の大野泉 名誉教授(JICA緒方研究所シニア・リサーチ・アドバイザー)は、「開発協力のアプローチのパラダイムシフトが起きており、今こそ、日本がどう動くかが極めて重要」と指摘しました。日本は米欧の援助縮小に追随せず、「安定役(スタビライザー)として、欧州や新興パートナーを含め、既存の枠組みを超えた新たな国際協力の秩序やアライアンスづくりの『結節点』となり能動的に関与すべき」と提唱。また、今回の事態は過度な援助依存リスクへの警鐘でもあり、「自立的な発展」のために貿易・投資・ODAを組み合わせ、産業・雇用創出につながる協力など、日本が自らの開発経験をもとに培ってきた開発協力のアプローチを再評価・体系化し、国際社会に発信していく必要性を強調しました。世論への影響についても触れ、国内では持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals: SDGs)への関心の高まりに比べ、国際協力への関心が低下しているデータと共に、そのギャップを埋めていく必要性を喚起しました。

モデレーターを務めたJICA緒方研究所の亀井温子副所長
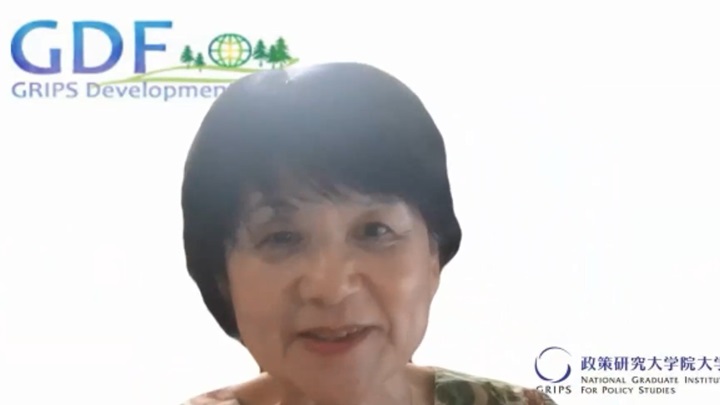
政策研究大学院大学の大野泉名誉教授(JICA緒方研究所シニア・リサーチ・アドバイザー)
地経学研究所の相良祥之 主任研究員は、戦後80年の世界のODAを取り巻く状況を振り返り、SDGs が採択された2015年頃は“高揚感”があったのに比べ、現在は構造的な変化が起きて足元が揺らいでいると指摘。今後の日本のODAの方向性として、人間の尊厳、Security(安全保障)、そして“Development”という概念に代わる概念“Prosperity(繁栄)”の3点の重要性を挙げ、「2030年以降のポストSDGsのキーワードとして、繁栄のために世界で連携していく『Sustainable Prosperity Goals (SPGs)』といった打ち出しも可能ではないか」と提唱しました。また、「自国第一主義が広がっているが、新型コロナウイルス感染症によってグローバル・ヘルス・セキュリティとナショナル・ヘルス・セキュリティが一気に結びついたように、国際協力は『国際益』にも『国益』にもなることを発信していくことが重要」と強調しました。
JICAの原昌平 理事は、日本のODAの状況も変化を続け、2023年には開発協力大綱が改定され人間の安全保障の重要性が再確認されたことや、2025年4月にはJICA法の改正により民間資金の動員や新たなパートナーの活用が可能になったことなどを説明。「開発途上国の人々と同じ目線で、相手を大切にする日本の国際協力を守りながらも、在り方は変えていかなければならない。ODAへの関心が下がっているという危機感もある。ODAもしくはJICAだけで世の中を変えられることは実はそれほど多くないからこそ、もっと幅広い人たちにまずは関心を、そして理解をいただくように働きかけ、さらに賛同していただき、世界中でさまざまな取り組みを進めている方々との連携・連帯を進めていくことが欠かせない」と述べ、セミナーを締めくくりました。
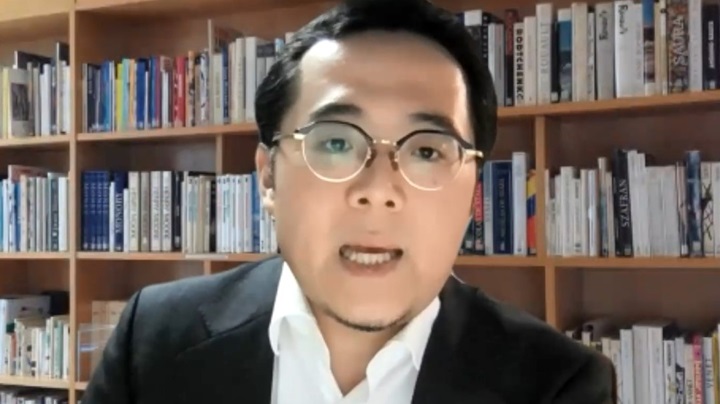
地経学研究所の相良祥之主任研究員
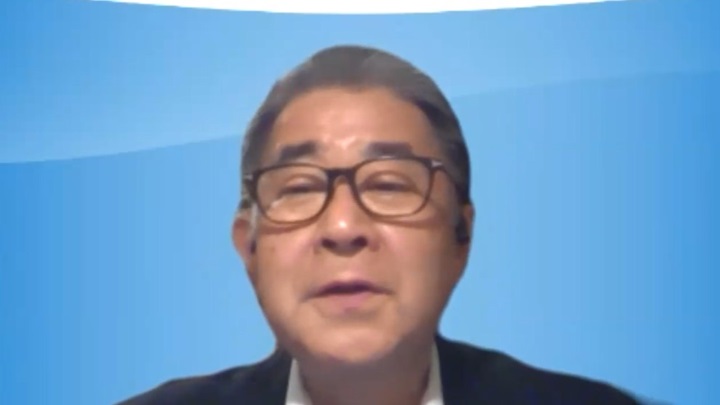
JICAの原昌平理事
本ウェビナーのプログラムや登壇者情報は以下からご覧になれます。
また、本ウェビナーの動画は以下からご覧になれます。

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.
scroll