実施中プロジェクト
ガーナ共和国(以下、「ガーナ」)では、過去30年の間に国家健康保険制度の導入、医師や看護師数の増員や地域保健の拡充、インフラ整備などの医療サービスへのアクセス改善に取り組んだ結果、妊産婦死亡率は、1985年から2023年にかけて出生10万人あたり943から234に、5歳児未満死亡率は、1990年から2022年にかけて、出生1千人あたり128から40に減少しました。しかし、母子保健指標の一定の改善が見られたものの、持続可能な開発目標(SDGs)の達成には至っておらず、特に貧困率の高い農村部では、医療者の介助を受ける出産機会が限定的であるため、都市部に比べ妊婦・子どもの死亡率は依然として高く推移しています。
ガーナ政府、東京大学、JICAが実施した「EMBRACE(Ensure Mothers and Babies’ Regular Access to Care)実施研究(2012-2016 )」の結果を踏まえ、ガーナ政府は、妊婦手帳、子ども手帳、継続ケア(Continuum of Care:CoC)カードなどを一体化した統合型母子手帳を開発して母子継続ケアを推進することを決めました。JICAは2016年より技術面や資金面から母子手帳の開発を支援し、2018年3月に全国展開版の母子手帳が完成しました。続けてJICAは2018年4月から2022年1月にかけて「母子手帳を通じた母子継続ケア改善プロジェクト」を実施し、母子手帳の全国展開と制度化を支援しました。全国16州において研修、モニタリングなどを行った結果、2021年時の調査では、母子手帳は全国の公立、私立、NGOなどの医療機関で活用され、出生記録の記入率向上、効果的なコミュニケーションや尊厳あるケア提供に寄与したことなどが確認されました。しかし、母子手帳を母親の妊娠中(胎児期)から一定期間継続的に活用した効果については検証されていません。また、母子手帳を全国展開し、自国政府予算で制度化したガーナ母子手帳プログラムの促進・疎外要因についても分析・評価が必要です。
本研究では、Demographic Health Survey(DHS)などの2次データを活用し、母子手帳の全国展開による母子保健指標への効果を確認するとともに、母子手帳の活用状況の観察や聞き取り調査を通じ、母子手帳を妊娠期から乳児期まで継続的に有効活用した結果や、子どものヘルスアウトカムや家庭でのケア行動の向上に貢献したかを確認します。また、全国展開プログラムを進める上での促進要因や阻害要因を実装科学や保健システムの視点で分析することで、ガーナ母子手帳プログラムのさらなる強化に役立てるとともに、今後の母子手帳を活用した支援の在り方に示唆を与えることを目指します。また、JICAはWHOやUNICEFとともに家庭用保健記録の実施ガイド を作成し、母子手帳の全国展開のための成功要因を提示しています。本研究の結果は、実施ガイドにさらなる知見を与えるものとしても意義があります。
主査:
萩原明子(JICA 国際協力専門員(保健))
Samuel Kaba Akoriyae(ガーナヘルスサービス総裁)
共同研究者:
柴沼 晃(東京大学)
Abraham Rexford Oduro (ガーナヘルスサービス)
Keneddy Tettey Coffie Brightson(ガーナヘルスサービス)
Olivia Mawunyo Timpo(ガーナヘルスサービス)
Gifty Ampah(ガーナヘルスサービス)
Joshua Billy(ガーナヘルスサービス)
牧本 小枝(JICA)
大町 檀(JICA)
波多野 奈津子(JICA)
梶野 真由奈(JICA)
関連リンク
- 研究領域
- 人間開発
- 研究期間
- 2025年04月01日 から 2026年03月31日
- 関連地域
-
- 開発課題
-

















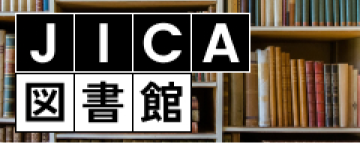
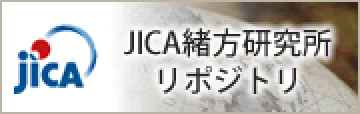

scroll