【杉村美紀客員研究員インタビュー】グローバル・シチズンシップは世界のつながりを保つ鍵
2025.10.29
世界の分断が懸念される中、重要性を増す“グローバル・シチズンシップ”とは?上智大学学長としてグローバル・シチズンシップ教育に注力し、JICA緒方貞子平和開発研究所(JICA緒方研究所)の数々の研究プロジェクトにも携わってきた杉村美紀 客員研究員に、JICA緒方研究所の亀井温子 副所長と日上奈央子 リサーチ・オフィサーが聞きました。
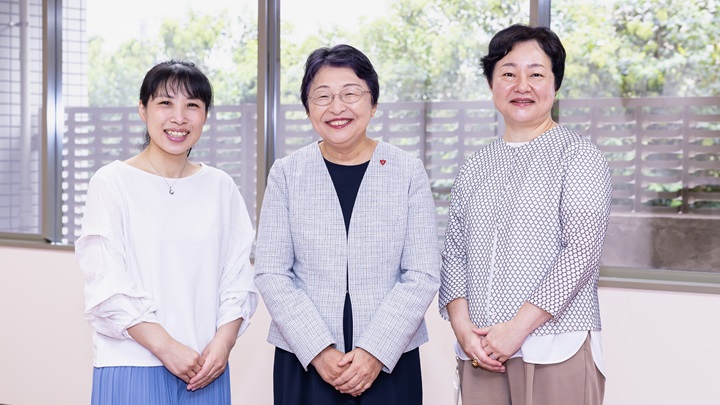
日上:これまで杉村先生は、比較教育、国際教育、多文化共生、インクルーシブ教育など、教育に関わるさまざまな分野を研究されています。こうした分野に関心を持ったきっかけを教えていただけますか?

研究プロジェクト「日本の国際教育協力」に携わったJICA緒方研究所の日上奈央子リサーチ・オフィサー
杉村:大学では教育学を専攻していて、教育は社会の成り立ちや人の暮らしにつながっている重要なものだということに気づきました。そして、受講した国際関係論の講義で、「国際関係を動かすには、政府や国際機関だけではなく、国際交流や民間交流も大事」という話を聞いたのをきっかけに、将来は教育を通して国際交流と平和に役立つ仕事をしたい、と思いました。卒論のテーマは、マレーシアの国民教育政策。特にマレーシアのような多民族国家では、教育が国づくりや人材育成に非常に重要であり、興味深い事例だと思って調べ始めたのがマレーシアとの出合いでした。
学部卒業後、そのまま大学院に進学したものの、自分の関心と研究がなかなか結びつかずにいました。しかしながら、ある“へんてこりん”なきっかけがあったのです。横浜の中華街で大好きな「エビそば」を食べていた時、店員さんが中国語で会話していることに気づきました。そのとき、「あれ?このコミュニティーってなんなのだろう?日本の中にもこのような多文化の社会があるとは。この中華コミュニティーを研究してみると面白いのではないか」とふと思ったのです。まさか中華街のおいしい味から多文化共生につながるとは、という出来事でした。上智大学に勤め始めてからは国際教育学を担当し、国際理解教育、多文化共生、国際教育開発など、まさにさまざまな分野に取り組んできました。
日上:杉村先生には、JICA緒方研究所の研究プロジェクト「障害と教育 」や「日本の国際教育協力:歴史と現状 」にもご協力いただきましたね。
杉村:研究プロジェクト「障害と教育」では、ネパールに実際に調査に行き、学ばせていただきました。障害と教育がテーマですが、広く見れば、障害の有無というよりも、共に学ぶことの意味を公正という観点から考えるインクルーシブ教育は、結局、多文化共生や誰一人取り残さない持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals: SDGs)につながっていくことに改めて気づかされました。教育は人のために生まれた分野。私自身、さまざまなきっかけをいただき、人とつながって、この魅力的な教育分野の研究に取り組んでこられたと思っています。
日上:さらに杉村先生にご協力いただいた研究プロジェクト「途上国における海外留学のインパクトに関する実証研究-アセアンの主要大学の教員の海外留学経験をもとに- 」では、インドネシア、カンボジア、ベトナム、マレーシアの主要大学の教員の留学経験が大学の教育活動全般にポジティブなインパクトを与え、大学の国際化が推進・促進されたという研究成果が出ています。この研究の意義をどう考えますか?
杉村:この研究プロジェクトで私はマレーシアを担当させていただき、誰に何を質問するか検討したり、教員向けの質問項目をつくったりと関わらせていただきました。実際に調査をしてみると、なかなか回答していただけなかったりと、大変なこともたくさんありましたが、分析の結果、国や大学によって特徴が違っていることがよく分かりました。例えばマレーシアではアメリカよりイギリスに留学したいという希望がはっきり表れていたり、インドネシアでは日本の国際協力を通じた両国関係が色濃く反映されて日本への留学が最も多かったりと、さまざまな留学の形を知ることができました。

数々のJICA緒方研究所の研究プロジェクトに携わってきた杉村美紀客員研究員
中でも、留学経験のある教員が培ったグローバル・シチズンシップという要素が見えてきたのが、とても印象的でした。大学教員の留学では、個人にとっての学位取得という目的が大きいわけですが、決してそれだけではなく、帰国してからも日本あるいは他の国の大学の教員たちとつながり、次世代の教育に生かす人間的なつながりも生み出している側面も見えました。留学のインパクトが持つ将来的な意味は大きい。それは当たり前のように思えますが、この研究プロジェクトでエビデンスをしっかり示したことはとても意義深いと思います。
日上:現在の日本の大学の国際化については、どうお考えですか?
杉村:日本の大学では“内向き”や“安定志向”の学生が増えていると言われます。日本政府は「留学生送り出し50万人計画」を掲げて奨学金を出したり、高校生の送り出しにも力を入れたりしていますし、短期や長期のプログラムを通じた留学のチャンスもたくさんあります。上智大学でも、例えばアフリカへの短期スタディーツアーなど、さまざまなプログラムを実施しており、それらをきっかけに世界に羽ばたいてもらえたらと考えています。ただ、今日では、円安、世界の分断、地政学的な影響が大きく響いており、今、世界における留学生の地図は大きく塗り変わっているといっても過言ではないと思います。
亀井:そうした日本国内の現状や世界の分断が懸念されている中で、世界のつながりを保つために重要なことは何だと考えますか?
杉村:今ほど、グローバル・シチズンシップが大事な時代はないと思います。グローバル・シチズンシップは、もともとユネスコなどが掲げてきた「地球市民」という概念につながります。ただ、グローバル・シチズンシップを考える上では、難しさもあります。なぜならば、それぞれの国には、政策を進める上で優先順位があるからです。グローバル・シチズンシップ教育を推進するよりも、まずは教育を通して自分の国民を育て、国としての一体感を持たせたい、という国もあるでしょう。そのような中でも、平和で持続可能な世界を目指して、学生が国際的な問題に向き合い、その解決策を積極的に考えることを促すグローバル・シチズンシップを掲げることの重要性は変わらないでしょう。同じ目標を掲げながらも、そこへ行くためのルートはみな同じである必要はなく、その国のコンテクストに合わせて違って良いし、いろんな考え方があっても良いのではないかと思います。
亀井:平和を追求し、分断や偏見を乗り越えるために、グローバル・シチズンシップ教育は重要な役割を果たすと言えますね。
杉村:日本の社会も、手を取り合って多文化共生社会にならなくてはやっていけませんから、その取り組みはまだまだ必要だと思います。ただし、簡単なことではありません。例えば中国系、インド系、マレー系の人々が暮らす多文化社会のマレーシアは、最近、国際化の波の中で留学生の受け入れを盛んに行っています。ところが、そのようなマレーシアであっても、中東やアフリカからの留学生が来ると、“自分とはちょっと違う”と思ってしまうマレーシア人学生もいるのです。日本の私たちから見ると、十分多様性に富んだ国であるマレーシアでさえ、そうなのです。今日、さまざまなレベルの分断が世界中で起きています。日本は、アジアに位置しつつ、欧米ともグローバルサウスともよい関係を築いています。だからこそ、それを生かして、国際社会の調整役、あるいはプラットフォームという役割を担うことができればいいのではないかと思います。
亀井:次世代の育成を担う大学の立場から、JICAとの連携も含め、どのように社会に貢献していきたいと考えていますか?

JICA緒方研究所の亀井温子副所長
杉村:上智大学では、これまでJICAと連携してさまざまな活動をしています。例えば、JICA職員や青年海外協力隊OBが経験をお話しくださる出前講座を開催し、それに刺激を受けて海外協力隊に参加した学生もいます。地球ひろばには、学生と共に何度も訪問したことがあり、それがきっかけでアフリカについての卒論を書いた学生もいます。今、私が所属する教育学科にはガーナからのJICA留学生が2人いて、グローバル・シチズンシップ教育をテーマにした国際教育学ゼミに参加してくれているのですが、彼らならではの視点からの発言のおかげで、ゼミが活性化しました。さらには、2025年8月に開催された第9回アフリカ開発会議(The Ninth Tokyo International Conference on African Development: TICAD9)でも、ユネスコチェアの大学として、学生が参加するサイドイベント「模擬アフリカ連合」をJICAとUNDPと共催させていただきました。若い世代にとって、世界を知る小さなきっかけが大事だというのは、最近とみに感じます。JICAが持つ知見やリソースをお借りして、刺激をいただき、いい意味での連鎖反応が起きると素晴らしいと思っています。
亀井:JICA留学生やJICAの現場経験を持つ人たちとの交流によって、少しでも学生たちがグローバル・シチズンシップや多文化共生について考えるきっかけになっていればうれしいです。これからも大学と一緒にさまざまな取り組みができたらと思います。最後に、JICA緒方研究所への期待をお聞かせいただけますか?
杉村:私がJICA緒方研究所の研究プロジェクトに参加させていただいたように、JICAが持っているネットワークを生かし、日本の、そして世界の研究者をつなぐ存在として発展されることを期待しています。世界も日本も複雑な課題が山積している中で、最も大切だと思うのが、JICA緒方研究所が追究する理念である「人間の安全保障」です。一人一人に注目し、それぞれの可能性を広げることを目指す「人間の安全保障」を、今だからこそ、あらためて見つめ直すことが重要であると考えます。
亀井:JICA緒方研究所が目指すビジョンは、「平和と開発のための実践的知識の共創」です。一人一人に注目する人間の安全保障の考え方を大切にしながら、これからも研究を通じてどう世界や日本の課題に貢献できるのか、共生と平和を目指していけるのか、考えていきたいと思います。ありがとうございました。

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.
scroll