『ペルーでの愉快な、でも少し壮絶なスポーツ協力―国際協力をスポーツで』
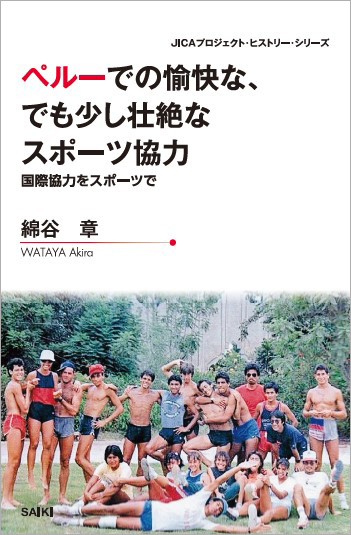
累積債務を抱え、低迷する経済に悩む1980年代のペルー。ハイパーインフレが貧富の差を拡大させ、労働人口の80%が失業や半失業に陥り、テロも発生していた激動の時期でした。貧困や格差の中で青少年は犯罪や事故に巻き込まれる危険にさらされ、とてもスポーツを楽しむ余裕などありませんでした。
そんな1980年8月、著者の綿谷章氏は青年海外協力隊員として陸上競技を指導するため、ペルーに赴任します。着任初日に「おまえを雇った覚えはない」と言われる衝撃の失業騒動を乗り越え、地方を巡回して陸上競技の指導を始めます。選手個々人の育成にとどまらず、自分たちの地域に誇りや愛着を持ち、地域づくりにかかわる人材を育てるという理念を掲げて活動を展開し、さらにはナショナルチーム候補選手の指導にもあたりました。綿谷氏は、スポーツを通して自身の心身を鍛え、仲間と協力し、自己形成につなげることが、きっとペルーの未来を開くことにつながると信じ、青少年に夢を追いかけ、自分の手で夢をつかむことの素晴らしさを伝えようと奮闘します。
そして協力隊員としての任期終了後も、国際交流基金のスポーツ専門家、そしてペルー教育省体育庁での顧問やコーチとして、さまざまな形で10年にわたりペルーの陸上競技発展のために尽くします。その結果、教え子たちはのべ63のペルー新記録を打ち立て、1988年には教え子の一人が、みんなの夢であったソウルオリンピックへの出場を果たしました。
一方で、その10年間は「疑問」「苦悩」「葛藤」「貧困」「挑戦」「創造」の繰り返しでもあり、綿谷氏は自身の「休職」「復職」「退職」「失業」「再就職」「再失業」という進退とも向き合わざるを得ませんでした。それでも、人生の半分以上をペルーの選手育成や陸上競技の普及に捧げることができたのは、スポーツを通じて国際協力をしてみたいという少年時代からの夢と、2年間の協力隊の活動があったからこそだと言います。
現在、かつての教え子たちは中央省庁や陸上競技連盟でスポーツ界をけん引したり、教員やコーチ、研究者として活動したりするなど、1980年代に綿谷氏と共有した理念を引き継ぎ、進化させながらペルーの社会で活躍しています。本書は、著者とペルーの教え子たちが織りなす心温まるヒューマンストーリーであると同時に、JICAが進める「スポーツによる国際協力」の現場からの貴重なレポートともなっています。
scroll