学びの質を変える教育政策とは?ポスト2015の教育協力に向けて、JICAと世界銀行の連携SABERから考える
2014.05.15
子どもたちの学習の質を高めるために、有効な教育政策とは何か。政策と現場のギャップを把握するために必要なことは何か。2014年5月1日、世界銀行(世銀)と連携してきたSABER(System Approach for Better Education Results)の研究成果を踏まえて、JICAと世銀双方の研究者と実務者、大学研究者が集まり、SABERと教育分野のポスト2015について議論するセミナーが開催されました。
SABERとは、世銀が進める教育政策・システムを比較するツールやデーターベースの構築を含む包括的なプログラムです。JICAはこのSABERについて、2011年2月からスタッフの派遣やJICA研究所による共同研究を通じた連携を進めてきました。特にJICAが協力実績を多く有する学校運営とアカウンタビリティ制度(School Autonomy and Accountability: SAA)の分野について、研究やツール改善などを行っています。今回のセミナーはこのような背景のもと、世銀の人間開発ネットワーク関係者の来日の機会をとらえて開催されました。

Patrinos氏
セミナーでは、世銀教育セクターマネージャーのHarry Patrinos氏から、ポスト2015に向けた教育課題を象徴する二つの指標として、「5700万人の不就学児童」および「2億5000万人の学校にいても読み書きができない児童」が挙げられました。SABERはグローバルな研究成果のレビューを基に分析ツールを開発していますが、これを活用して教育政策、法令整備、プログラム形成支援が行われているウガンダ、ナイジェリアなどの例が紹介されました。また、SABERのツールのさらなる活用に向けた研修プログラムについては、シニア教育スペシャリストのYiden Wang氏が紹介しました。
SAAの分野については、世銀のシニア教育スペシャリストであるAngela Demas氏がツールの概要や、カザフスタンで政策対話に活用された事例を紹介しました。その後、JICA人間開発部の澁谷和郎職員が、JICAの技術協力の知見を基に、学校運営委員会の透明性や活動に係る指標などを考慮したツールの改善について報告し、セネガルにおいて世銀、グローバル教育パートナーシップ、JICAが連携した事例を踏まえて、政策と現場をつなぐ手段としてのSABERの有効性に言及しました。さらに、共同研究を代表して結城貴子主任研究員が、ブルキナファソやセネガルでの研究調査を踏まえて開発した政策と実践のギャップや、実践と学習成果の関係を分析する補完ツールを紹介しました。この中で、学校運営制度に関しては、分権化、学習評価政策、情報活用策などとのバランスも考えた施策の検討をすること、同時に包括的で継続的な政策モニタリングを行っていく体制を確立することの重要性を指摘しました。
その後、東京大学の北村友人准教授がモデレーターを務め、「ポスト2015における学習目標」というテーマで、世銀のPatrinos氏、EFA(Education for All:万人のための教育)運営委員会副議長の広島大学吉田和浩教授、JICA人間開発部の石原伸一グループ長が発表し、意見交換を行いました。ポスト2015の教育開発で目標とすべき学習成果の向上に向けて、SABERが「どのような状況の下で、どのような政策が機能するのか?(what policies work under what contexts)」という問いに応えるものであること、教育評価制度の能力強化など個別の支援においても、政策分析の側面で果たす役割があることについて言及されました。
JICA研究所は、世界銀行と学識者とのSABERに関する共同研究を通じ、その有効な活用方法や課題をまとめ、教育開発協力の向上に向けた貢献を行っていきます。
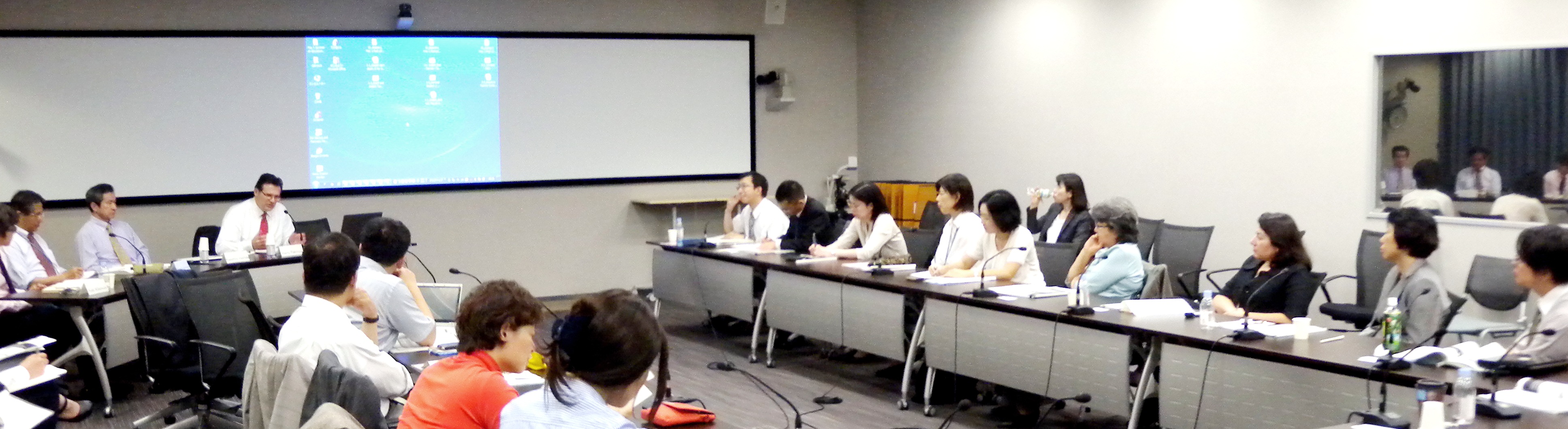
開催日時:2014年5月1日(木)
開催場所:JICA本部

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.

事業事前評価表(地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)).国際協力機構 地球環境部 . 防災第一チーム. 1.案件名.国 名: フィリピン共和国.
scroll