終了プロジェクト
概要
人工知能(Artificial Intelligence: AI)にかかる急進的な技術開発は、その応用において、人間がこれまで担ってきた労働の相当部分を代替するレベルにまで達しつつあります。2024年には、ノーベル賞の化学および物理の2部門で、それぞれAIに関する研究者が受賞し、まさにエポックメイキングな年となりました。一方で、同受賞者自身から「急速に発展するAIへの制御の必要性」が発言されるなど 、AIに代表される情報通信技術(Information and Communication Technology: ICT)の急速な発展と浸透は、人間社会における光と影のコントラストをこれまで以上に増幅させる可能性も指摘されています。
このようなデジタル技術の急進性は、人々の間における「デジタル不平等」を加速させ得る構造的な要因になりつつあります。さらには、膨張するAI開発競争で急増している電力ニーズが環境負荷に対して負の影響を与え得ることも指摘されており、その影響が脆弱な立場にいる人々の生活をさらに脅かす可能性も否定できません。
一方、デジタル技術の進展は、多方面に正の効果も見せています。スマートフォン、高速ブロードバンド通信網、クラウド・コンピューティングの世界的な普及と実装は、これまで困難だった社会的な課題を改善・解決するきっかけにもなっており、特に若年層が国境を超える経済圏に参加することを可能にするなど、脆弱な立場にいる人々に対しても社会参加を促す可能性を増幅する事例も急増しています。
本研究会は、以上のような問題意識、すなわちデジタル化が及ぼす脆弱な立場にある人々への影響とその内容に対し、人間の安全保障の観点から検討することを試みました。
ケーススタディ では、脆弱な立場や環境にいる人々が、デジタル化の進行によってどのような影響を受け得るのか、という視点に立ち、各国・地域ですでに社会実装されてさまざまな手法による客観的な評価がなされた異なる分野での事例を複数検証することを通じて、「人間中心のデジタル化」とはどうあるべきか、について緊急的に論じることを試みました。
また、文献レビューでは、デジタル不平等に着目し、関連する内外の代表的な先行研究と議論を紹介しています。デジタル化により何の不平等が生じ、人々にいかなる影響を与えているのか、それは人間の安全保障上のどのような脅威なのかを整理し、デジタル化のリスクを抑制し、その可能性を最大化するための重要な視点を考察しました。
これらを総合的に俯瞰することで、「人間中心のデジタル化」という今後重要性がますます高まるであろう問題意識に対して、本研究会による分析と教訓の抽出が、今後のわが国における開発協力政策および支援方針において重要な参考情報となることを目指しています。
【研究会メンバー】
主査:内藤智之(神戸情報大学院大学)
アドバイザー:狩野剛(金沢工業大学 )
アドバイザー:山中敦之(JICA)
JICA緒方研究所:宮原千絵、齋藤ゆかり、竹内海人、梶野真由奈、李千晶、難波祥子
JICA内関係者:福原一郎、宮下良介、井本佳宏


















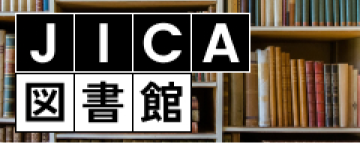
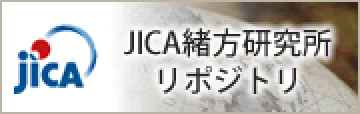

scroll